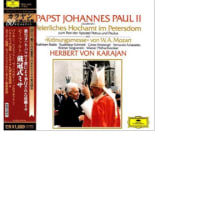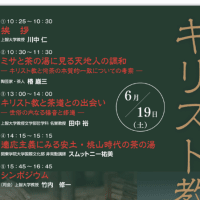「ゲーテが<エペソ人のディアナは大なるかな>といえる詩の中にいった様に、人間の脳中における抽象的の神に騒ぐよりは、専心ディアナの銀龕(ぎんがん)を作りつつパウロの教を顧みなかったという銀工の方が、ある意味においてかえって真の神に接して居たともいえる。」(西田幾多郎『善の研究』、岩波文庫新版253頁)
西田は四高のドイツ語と倫理学の教師をしていたころ、ゲーテの詩劇「ファウスト」を輪読し、「自然のなかに神を、神の中に自然を見る」ゲーテの詩の世界に傾倒していた。
「吾人は基教の所謂有神論者にあらずして無神論者なり、無神論者にあらずして汎神論者なり、汎神論者にあらずして汎神論者よりも大なるもの也」とは、若き日の鈴木大拙が書いた『新宗教論』の根本思想のひとつであるが、
西田の『善の研究』の宗教論の一つの課題は、この「汎神論者よりも大なるもの」の立場を究明する事にあったと言って良い。
その場合、ゲーテの詩劇と叙情詩が、藝術の創作(ポイエーシス)に於て西田の課題を表現するものとして、関心を惹いたのであろう。1905年2月1日の西田の日記には、「鈴木大拙からオープン・コート社の雑誌が送られてきた」という記述がある。この雑誌に編者のポール・ケーラスによる論説「ゲーテの多神教とキリスト教」が掲載されており、ケーラス自身によるゲーテの当該の詩の英訳(Great is Diana of the Ephesians) とドイツ語のゲーテ著作集にあるH.Knackfuss のイラストが掲載されている(その挿絵をここに転載ー日本の仏師にも通ずる印象深い畫である)。
ゲーテの詩に触発された西田は「一幅の画、一曲の譜において、その一筆一声いずれもいずれも直に全体の精神を現さざるものはなく、また画家や音楽家おいてに一つの感興である者が直に溢れて千変万化の山水となり、紆余曲折の楽音ともなるのである。斯くの如き状態に於ては神は即ち世界、世界は即ち神である」と書く。
不注意な読者にはスピノザ的な汎神論と響くであろうが、私の理解するところでは、そこには既に「汎神論者よりも大いなるもの」の立場がいかなるものであるかが予感されている。「芸術家の創造作用は、それが行であると共に知である。筆の先、鑿の先に眼があると云うべきであろう。我々はこの立場に於て、知識によって達することの出来ない世界を歩みつつあるのである」という藝術論(『藝術と道徳』(全集3-468))が、純粋経験を根本実在とし、そこから真善美の統一を求めた西田の創造作用論から帰結するのである。
この時期の創造作用論は、「無の場所の自覚」を創造作用とした中期西田の「絶対無の自覺的限定の神学」、そして最晩年の「場所的論理と宗教的世界観」へと展開していく。それは、「汎神論者よりも大いなるもの」の宗教的自覚の展開であった。
西田は「神は即ち世界」「世界は即ち神」と書いた。この「即」は、決して否定を含まぬ即自的な一体性を表現しているのではない。「即」は「即非」によって成りたつ。「神は即ち世界であり、世界は即ち神である」の倒置反復語法(キアスムス)に深い意味がある。
絶対否定の峻厳さを忘れぬ「即」の意味こそが、「西田幾多郎と鈴木大拙と共に考えるもの」の課題であり、それは大乗仏教の枠組みを超えた普遍性、キリスト教にも通ずる普遍性を持たねばなるまい。鈴木大拙の「即非」、西田の「矛盾的自己同一」の場所的論理の試みは、「汎神論」と「超越神論」「一神教」と「多神教」の抽象的な対立、「我々の頭の中で捏造された宗教の教義上の対立」を越えた活きた宗教的世界のロゴスとなりうるのである。