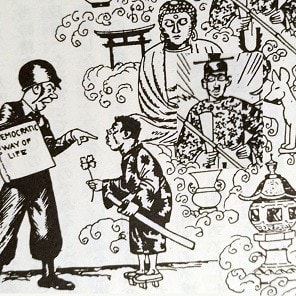
きょうの朝日新聞の『(異論のススメ)民主主義がはらむ問題』で、佐伯啓思は民主主義は非効率で、滅びの道に進むと相変わらず主張している。「戦後レジームからの脱却」を唱える安倍晋三も同じ主張である。元首相の吉田茂もそう主張していたとジョン・ダワーが『敗北を抱きしめて』で書いている。
佐伯は書く、
「だが、利害が多様化して入り組み、にもかかわらず人々は政治指導者にわかりやすい即断即決を求めるという今日の矛盾した状況にあっては、由緒正しい民主主義では機能しない」
「民主主義を民意の実現などと定義すれば、民主政治とは、民意を獲得するための政治、つまりポピュリズムへと傾斜するほかなかろう。」
「古代ローマ帝国の崩壊は、民衆が過剰なまでに「パンとサーカス」を要求し、政治があまりに安直にこの「民意」に答えたからだ」。
この佐伯の民主主義への批判は、大衆に対する恐れ、敵意からくると私は思う。
佐伯の「古代ローマの崩壊は・・・・・・「民意」に答えたからだ」は間違っている。「古代ローマの崩壊」の前に、すでに、古代ローマの民主主義が崩壊している。民主主義の崩壊は市民社会の崩壊によるものである。
古代の市民社会は、自分の土地を自分の手で耕すことでなりたっていた。それが、戦争で大量の奴隷が安価に手に入り、奴隷を購入する大土地所有者が有利になった。すなわち、小規模の自作農がなりたたくなる。古代ローマで起きたことがこれである。何度か反乱が起き、農地解放が行われたが、私有制が維持されたので、自作農の没落の趨勢は止められなかった。
「プロレタリアート」とは、もともと、生産手段を失ったローマ市民のことをさす。彼らの反乱を防ぐために、統治者は「パンとサーカス」で民衆を抑え込んだのである。
古代ローマの市民社会が崩壊し、雇用兵で帝国を守るようになれば、ローマ帝国が滅んでいくのも自然な流れである。それが公平というものである。
* * * * * *
佐伯は書く、
「自由や民主主義と経済成長を謳歌するはずであった冷戦以降のグローバリズムにおいて、経済の混迷に直面する民主主義国が深い閉塞感にさいなまれていることは疑いえない」。
私は、このかた、「深い閉塞感にさいなまれた」ことはない。1981年にカナダから日本に戻ったとき、満員電車に乗り込む勇気がなく、貧困な日本文化にあきれただけである。2000年代に大学の先生とつきあったが、彼らの言う「閉塞感」を理解できなかった。1990年のバブルの崩壊の後遺症ではないか。「閉塞感」を感ずるのは、既得権層に属しているからではないか。
私はいま日本が民主主義の国とは思わない。私の子ども時代、「戦後民主主義」が生き残っていたが、1980年代には ほとんど消え失せている。いま、「民主主義の危機」ではなく、「民主主義」とは これから闘いとるものである。
* * * * * *
佐伯は、「民主主主義」が「真理は不明であり、絶対的に間違いのない判断をなどありえない」を前提としていると言う。これを「価値相対主義」と呼び、多数派を形成するために、「ポピュリズム」に陥るしかないと主張する。
科学においては、「真理」は追い求めるものであり、手元にあるのは「真理」ではなく、「仮説」と考える。「仮説」が役立たなくなれば、仮説を改めれば良いのだ。同様に民主主義においても「真理」や「正義」は仮説であり、「価値相対主義」とは異なる。
民主主義社会では、政治家は、個人的な権力闘争に窮するのではなく、何をなすべきかを社会のメンバーに提起し、社会の合意を形成していくべきだ。
安倍晋三や岸田文雄は権力を握ることだけに執着し、強い自分を演出しようとする。
「民意」を尊重することが悪いのではなく、自分に都合の良い主張をあたかも「民意」のように見せかけたり、人々を不安に落とすことで「民意」をつくり出したりすることが悪いのである。
電力不足で国民を脅して原発政策の転換をはかったり、たいしたことのない北朝鮮のミサイルにJアラートで国民を脅して防衛政策の転換をはかったりすることこそが、悪いのである。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます