先日、親戚のお葬式に参列しましたが、
葬儀会場で、待ち時間に流れていたBGMは、なんとバッハの『主よ人の望みの喜びよ』 でした。
教会の礼拝のために作られたバッハの曲が、仏式の葬儀会場の待ち時間のBGMに使われているので、
主人に耳打ちすると、「心が落ち着く曲なら、なんでもいいんじゃないの。」と。
そうでした。日本人はよいと思われるものはなんでも採り入れて吸収してしまう民俗でした。
結婚式だけでなくお葬式でもそうなんだ・・・
そう心の中でつぶやいて、目を閉じると、不思議と心が落ち着きました。
ピアノ演奏で聴いてみましょう。
“『主よ、人の望みの喜びよ』、
目にすると美しいけれど口にすると舌をかみそうな不思議なタイトルを持つこの曲は、
もともとオーケストラを伴った合唱楽章として作曲されたものである。
バッハは、若い頃から教会の毎週の礼拝のために教会カンタータなどの声楽作品を作曲し、
そして演奏するという仕事をしていたが、
『主よ、人の望みの喜びよ』が含まれる『カンタータ第147番《心と口と行いと生活で》』は、
1723年7月2日の礼拝のために書かれている。
この時バッハは38歳、ライプツィヒに越してきて、まだ1ヵ月ちょっとであった。”

にほんブログ村に参加しています。
よろしければワンクリックお願いします。
↓ ↓
 にほんブログ村
にほんブログ村
葬儀会場で、待ち時間に流れていたBGMは、なんとバッハの『主よ人の望みの喜びよ』 でした。
教会の礼拝のために作られたバッハの曲が、仏式の葬儀会場の待ち時間のBGMに使われているので、
主人に耳打ちすると、「心が落ち着く曲なら、なんでもいいんじゃないの。」と。
そうでした。日本人はよいと思われるものはなんでも採り入れて吸収してしまう民俗でした。
結婚式だけでなくお葬式でもそうなんだ・・・
そう心の中でつぶやいて、目を閉じると、不思議と心が落ち着きました。
ピアノ演奏で聴いてみましょう。
“『主よ、人の望みの喜びよ』、
目にすると美しいけれど口にすると舌をかみそうな不思議なタイトルを持つこの曲は、
もともとオーケストラを伴った合唱楽章として作曲されたものである。
バッハは、若い頃から教会の毎週の礼拝のために教会カンタータなどの声楽作品を作曲し、
そして演奏するという仕事をしていたが、
『主よ、人の望みの喜びよ』が含まれる『カンタータ第147番《心と口と行いと生活で》』は、
1723年7月2日の礼拝のために書かれている。
この時バッハは38歳、ライプツィヒに越してきて、まだ1ヵ月ちょっとであった。”

にほんブログ村に参加しています。
よろしければワンクリックお願いします。
↓ ↓










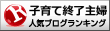

















と・・・式の疲れが今頃出てきました。
歳だね^^;
安らぎを与えてくれるBGMは、
参列者の心も癒されます。
おかぴさんのブログのあじさいも
ステキですね。
おかぴさんのお宅のお庭は
季節ごとの花が咲いて、
訪問される方々も癒されることでしょうね^^
私も癒されました~
何も知らない私が聴いたら
故人のことを思いながら優しい気持ちになりますもの。
亡くなられたご親戚さまのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
「形じゃない、弔う心があればそれでいいのだ」と思うことにしています。
そうですね。
弔う心が一番大事ですよね。
ちなみに、この曲を聴いて意見をする人は
誰もいませんでした。
残念ですね。
でも、この曲は安らぎを与えてくれるので、故人も喜んでくれるでしょう。
きっとそう思います。
本当に安らぎを与えてくれる曲ですよね。
バッハのこの曲は、村治佳織さんのギター演奏や
藤澤ノリマサさん(「ダッタン人の踊り」でよく知られている)
が歌っているので
若い人にも馴染みがあるようです。
でも私は、「形じゃない、弔う心があればそれでいいのだ」と思うことにしています。
私は祖父の代から仏教なのか、キリスト教は無縁です。でも、原曲の「カンタータ」で生きる喜びを味わっています。
音楽の父・バッハは場所を選ばず、あらゆるBGMに使いやすいですね。