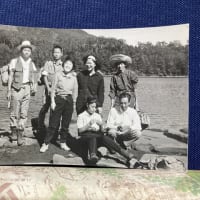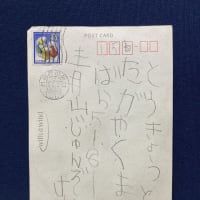今年は意識的に蝶の撮影をしないでいるのだけれど、さっきWi-Fi電波を拾いに外に出かけたら、アパートのそば(大学駐車場の脇)の草むらにタテハモドキがいたので撮影しておきました。近所(福岡県飯塚市)の蝶、52種目ですね。タテハモドキが九州北部まで分布を伸ばしていることは知っていたのですが、これまで出会うことがなかった。新鮮な個体(越冬型)が同じ場所に2頭いました。屋久島のアオタテハモドキと言い、揃って北上しているようです。
驚いたことが一つ。この場所の植生環境が、昨年、一昨年とガラリと変わっている。これほどまでに極端に変わるとは驚きでしかありません。草刈りの時期や回数(春にシルビアシジミの件で言及した公団住宅中庭はともかく今年は近所の草刈りがなぜか少ない)に関係するのかもしれませんが、、、。草刈りをしようがしまいが、最終的には同じような環境(それは必ずしも極相に向かわない)に落ち着くのではないかと。
植生は一変したけれど、蝶のメンツはあまり変わっていませんね。さっき出会ったのは、タテハモドキのほか、クロマダラソテツシジミ、ウラナミシジミ、ヤマトシジミ、ツバメシジミ、ツマグロヒョウモン、チャバネセセリ、キチョウ、アゲハチョウと、いつものメンツです。セイタカアワダチソウに群がるはずのキタテハを見かけなかったのは偶然でしょうか?
イチモンジセセリをチェックしようと、蚊に刺されながら小一時間粘ったのですが、チャバネセセリばかりでした。
大事なことに気が付いた。ベニシジミがいない。一昨年(昨年も)の10月中旬は、ここはベニシジミだらけだったのですが、一頭も見かけません。そういえば、今日のこの場所だけでなく、今年の夏以降は、ベニシジミにほとんど出会っていない(屋久島では南下定着しているのに)。これはどういうことでしょうか? まあ、(自然のシステムは複雑ゆえ)一年や二年で衰栄の判断を下すわけにはいかないのだけれど、気になる現象ではあります。