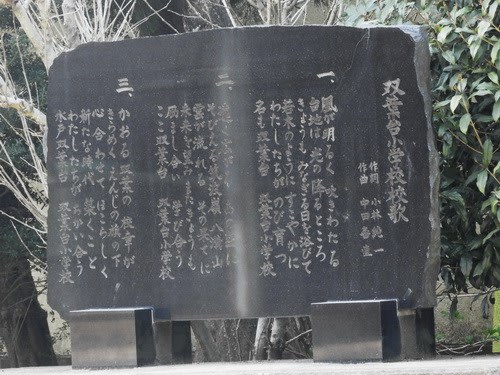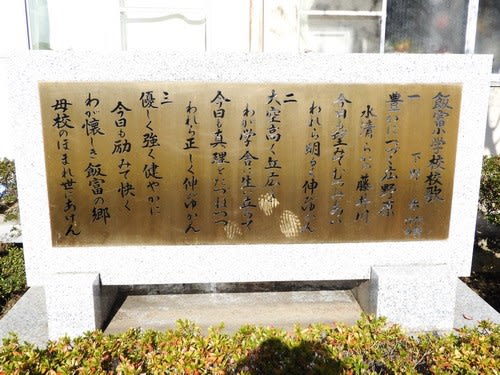徳川家の蘭(ラン 水戸市植物公園 小吹町504)
水戸徳川家14代圀斉(くになり)が交配してつくったパフィオペディルムという種類の蘭に、マユミという品種があるそうです。寒水石のとれる真弓山からとった名前のようです。徳川家や水戸植物公園が英国王立園芸協会に登録した蘭には、その外にも、サクラガワ(桜川)、サンノマル(三の丸)、タカショウ(鷹匠)、ミガワ(見川)などの、水戸に関係ある名前がついた品種もあるようです。

梅刺繍コースター(阿波屋染物店 本町1-13-16)
去年の11月に千波公園で行われていた地元産品展示会で見た、水戸黒で染めた布地に刺繍で紅梅をあしらったコースターです。水戸黒は、水戸を代表する江戸時代からの染織手法だそうです。

梅開花日(水戸地方気象台(金町1-4-6)のホームページ)
水戸地方気象台のホームページによると、今年の梅の開花日は2月16日で、去年と同一日、平均の開花日は1月30日だそうです。最も早い開花日は平成16年12月15日で、最も遅い開花日は平成24年3月14日だそうです。写真は水戸地方気象台の入口付近です。

蛙股の梅(吉田神社 河和田町(かわわだちょう)2895)
蛙股は、並行する二本の横柱の間にある装飾的支えの材のことをいうそうです。本殿入口上部につけられた蛙股には、その中央部分に開いた一重の梅とつぼみが彫りこまれています。

梅の異名
香雪(こうせつ)、清友(友や客には香りが漂ってくる意味が入っているのでしょう)、清客(せいかく)、寒客(かんかく)、花魁(かかい 花のさきがけ)、玉蘂(ぎょくずい 目立つオシベをいうのでしょう)、君子香など、たくさんの中国古典で使われた梅の異名があり、日本でもつかわれたようです。また、日本の古語では、くちき(朽木 木の心部がなくなって樹皮部分ばかりが残っている梅が多いからなのでしょう)、にほひぐさ(匂い草)、はつなぐさ(初名草)、はるつげぐさ(春告草)などの異名があるそうです。芳賀矢一・校閲の類語辞典にあります。写真は16日に撮った八重紅梅ですがすでにさかりをこえています。
水戸の梅の話題(11)