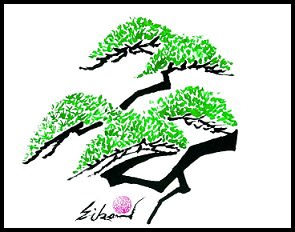~ 恩師の「心行の解説」下巻より ~
講演 十五
先の続き・・・
他の宗教の批判をいうことはないのですが、
間違った宗教からは目覚めて、
幸せにならなくてはいけません。
ある宗教では選挙闘争、折伏闘争、
題目闘争ということを教えております。
これは決して安らぎは得られないのです。
闘争の中に安らぎがあるはずがないからです。
闘争を教えるような宗教はどの宗教もすべて同じで、
ほんとうの神様から離れた教えです。
神は争い戦いなさいとはいわれません。
神は完全なる愛、完全なる許しであり、
その愛の行いこそ神の御心です。
「私の宗教は正しい、他の信仰をしていたら地
獄へ行く」と、
他を非難中傷するのは、神の御心から離れます。
常に自然を愛し、人間を愛し、
完全なる許しを教えることこそ
ほんとうの教えではないかと思います。
他を裁く時間があれば自分自身を裁く時間を持つほうが
大事ではないかと思います。
全く無償の、何ものをも求めないご奉仕の愛を
させていただくことです。
午前中三十人ほどの癒しをさせていただきました。
間違ってもらっては困るのは、
私たちの学びはあくまでも自力であって、
病気治しではないということです。
病気治しはただ方便であるということを理解することです。