書籍名>;「哭きいさちる神=スサノオ」[1989]
著者;ネリー・ナウマン 発行所;言叢社同人 発行日;1989.10.16
初回作成年月日;H29.2.5
ネリー・ナウマンは、ウイーン大学で民俗学を専攻し、1949年からこの年までに、日本古代の神話や民俗学的な伝統に関する37本の発表された論文のリストが巻末に示されている。彼女の姿勢は、通説には決して満足せずに、あらゆる方面からの資料を駆使して、神話や日本書記などから新たに、より本質的な発見を試みるもので、その姿勢と方法論は、メタエンジニアリングに共通するところがあるように思う。それは、次の記述に表れている。

『しかし何よりも、神話を古代の日常生活の反映だとしたり、文学的研究や史的研究において民族の起源に関して利用される物語モチーフや物語タイプの集合だとするだけでは十分でないことを次第に意識するようになった。
それは、古代のこうした物語の一つの、すなわち表面的な一面でしかないのである。ミルチア・エリアーデやラファエ・レベッタツオーウェルナー・ミューラー、カール・ケレーニーなど、宗教学からも民俗学、古典古代学の立場からも神話理解のために新たな手掛かりを求め、その分野で重要な貢献をなした人々を読んでから、日本の神話にもその本質的な確信、あらゆる「本当の」神話に見られる存在論的叙述を探求しようと試みたのである。』(pp.2)
『縄文土器の不思議な装飾や奇妙で独特な土偶に魅了されたのである。不満に感じたのは、豊穣儀礼用の土偶であるといったありきたりでじつに愛すべき指摘以外には、この対象のもつきわめて複合した象徴表現を解明する企ては何一つなされておらず、いやこうした方向では何も真剣な試論がなされていないことだった。』
『頭の上に蛇が巻きついている藤内出土の小さな土偶がはからずも道を示してくれた。別の手段で表現されているものの、同一の連関で同一の象徴が、中国の新石器時代の仰韶文化に求められるからである。』(pp.2)
『誤って理解されていた神話のモチーフが、縄文図像のモチーフと何の困難もなく結びつき、そうすることでその本来の意味が認識できることがわかったのである。さらに、神話のモチーフと縄文図像のモチーフとの一致は、このモチーフの成立時期を神話についてもほぼ特定する可能性を示している。』(pp,3)
最初の「哭きいさちる神=スサノオ―生と死」の日本神話像の章では、鬼、人食い、死霊、山姥、多様な森の霊、悪魔的存在の擬人化などの実例に言及した後で、古事記と日本紀のイザナギとの説話を西欧の同様の昔話への民俗学者の解釈を加えて、次のように結論している。
『事件の核心は、火の神を生んだ時に死んだイザナミの死にあります。イザナミは最初の死者であり、物語の成り行きには、死がまったく新たな経験として理解されることが具体的に示されているのです。』(pp.17)
確かに、その後の物語の展開は、死者の醜くなる姿を見てしまったイザナギが、あらゆる手段でそこから離れようとする、すなわち死から逃げようとする行動が具体的にあらわれている。逃げる際に使われたタケノコや葡萄や桃といったものは、当時の日本ではあまり一般的ではなく、中国などの影響もみられるとしている。
『当時の日本は葡萄の実を知ってからそう時間がたっていないからです。葡萄は中国から輸入されたもので、中国にさえ紀元前126年にはじめてトルキスタンからもたらされました。3番目の物として投げられた桃が呪力をもつとする信仰も中国の考え方を取り入れたものに他なりません。』(pp.19)
さらに、「縄文時代の若干の宗教的観念について」では、
『土偶の宗教的意味を個々に考察しようとした真剣な試みはまだなされていない。土偶は主として、あるいはもっぱら女性像であり、したがって地母神の表現であるとか、土偶は豊穣性の象徴として見做すべきだとかいった再三表現される見解は、一般論で責任を負うところがないので、どんな方法をもってしてもこれ以上進まないのである。』(pp.29)
としたうえで、個々の土偶の形や文様についての、膨大な数の比較検討を始めている。さらに、中国の土器、古代オリエントの遺物、イランの動物像などとの比較なども行っている。その中には、『三日月を角として捉える』 や『琉球では、月の神が人間の生に限りがあるのを憐れんで、人間には生の水を、蛇には死の水をあたえてのませようとしたという。』や『 人間の代わりに蛇が不死性をもつ。ちなみにこれは誰でも目にすることができる。蛇は、硬直して「死んで」横たわったのちに、古い皮を脱ぎ捨てて、若がえってそこからはい出てくる』などの民俗学的な知見も多く述べている。
『折口信夫氏は「万葉集」の歌を手掛かりとして、この神話が日本にもあったと仮定してよいと考えた。とにかく岡氏はここで、「月―水―不死性―蛇―生命を授ける月の神―若水」という諸要素が一つにされているとみて、この月の神話が、きわめて古い広範に(シベリアのさまざまな民族やユーラシアのほとんどの部分)伝播した一つの型であるという見解を述べている。』(pp.40)
『したがって月は、大地の実り豊かにする雨という普通の水を持っているだけではなく、「生の水」をも持っているのだ。このことをさらに裏付け、明らかにできる。古代オリエントでも、角としての三日月の観念とならんで、皿としての三日月の見解も登場する。(中略)世界の中心ないし生命の木に結び付く観念には必ず、世界樹や生命の木の根元に棲んだり大地の臍に巻きついている蛇が含まれている。』(pp.41)
つづく、「逆剝―天の斑駒を逆さに剝ぐこと」では、日本書紀などでは、スサノオの悪事の一例である「馬の皮を逆さにむくこと」が示されているが、この行為に対しても、次のように考察している。
『逆剝そのものの正確な意味や、それが神話の脈絡の中で正確に何を意味するのかを理解して初めて可能になる。(中略)したがって神話を理解しようとするときに、そうした落差を埋めることが本論の目的である。』(pp.103)
『スサノウの本来の使命が世界を支配することにあるのがはっきりわかる。』、『ふつう動物は、尻から頭部へ向かって皮を剝ぐ。』などとしたうえで、
『この場合正反対にされた行為はもともと、「生」を呼び起こす祝福行為である。高く差し上げた杯をもって健康と長寿を願う祝杯であり、(中略)重要な点はただ、ある行為をまったく逆にすれば、本来の効果とまったく逆のものが生まれるという思考である。と同時に、こうした逆の行為がもっぱら生と死という存在の両極に関係するのを強調しておかねばならない。』(p113)
ごく最近になって。これと似た見解が示された書籍が、出版され始めているが、西欧人的な合理性から出発して、広い知見を適用すると、結論は今まではなかなか得られていなかったものの発見につながる。
これは、メタエンジニアリングやイノベーションと通じるものがあると思う。
もう一冊のナウマンの書を紹介する。
「生の緒(いきのを)」[2005] 著者;ネリー・ナウマン
発行所;言叢社 発行日;2005.3.10
初回作成年月日;H29.2.5

この本の副題は、「縄文時代の物資・精神文化」で、私にとっての彼女の書の3冊目になる。冒頭の写真集の中には、1989年秋、諏訪郡富士見町の井戸尻考古館で発掘後の縄文土器を多くの研究者と観察する姿が写っている。彼女の縄文に関する研究生活の長さと、深さと、その発表された論文の数は、日本のどの研究者にも負けないほどと思う。
多くの特徴ある文様を有する縄文中期の土器の膨大かつ詳細な観察から、それらの文様は、必ず何らかの象徴的な意味があり、それ等はすべて、当時の精神文化と密接につながっているとの信念からの解読を試みている。
また、西欧人の特徴として、古代ギリシャ、初期の地中海文化、アステカ、コロンブス以前のアメリカ、古代インドなどの文様との比較を随所で行っている。
特に挙げられている特徴は、「後頭部に刻まれた十字に分割された円」(これは、有名な蓼科の縄文のビーナスにも刻まれている)、「渦巻」、「三日月」、「巻貝」、「蛇の頭」、「蛇のとぐろ」などである。これらはすべて、生と死と復活に繋がってくる。
そして、「精神世界―旧観念と新たな象徴」としての「生の緒(いきのを)」に繋がってくる。要所のみを引用する。
『縄文時代中・後期の多くの土偶についても、刻線が臍から上方へ伸びるとともに、小さな渦巻きで臍が表現されている。』(pp.250)
『人体にはそんな線がないので、精神ないし象徴のレベルにその意味内容を求める必要があろう。ひょっとすると意味の手掛かりは、「古事記」や少しだけ異文で「日本書記」に記録された古代歌謡に示されているかもしれない。歌謡は、おのがヲ「緒」に気をつけよという大和の支配者御真木入日子への警告だとされる。敵が「盗み殺せむ」恐れがあったためで、彼の生命はこの緒次第であった。「緒」と「生」は二つのものではない。この歌謡のヲは、「万葉集」の十五の歌にあるイキノヲ「生の緒」という表現に対応するようだ。』
『じつに多くの縄文土器に見られる臍から胸部ないし喉へとつながる縦線は、ほぼ確実にこの緒の描写であろう。右の推定は、この線が多くの場合臍の造形や表示、強調のために渦を巻いているという事実からも説得力を増す。』
『臍が生命のはじまる中心の象徴として、あるいはそれ自体が渦巻の形状をとり、あるいは渦巻に囲曉されているならば、これもやはり生の進展という同一観念を指示しているにちがいない。その進展は生の緒によってさらに拡充されて視覚化されている。そしてイキが息と生きの両方を意味するので、線が胸部と喉のあたりの部位で終わるのはしごく当然というほかない。』(pp.251)
また、多くの土偶に見られる冠型の突起については、「光」を象徴しているとしている。その形が、甲骨文字から金文、漢字の光への変化の過程に現れる、数種類の文字と同じ形をしているというわけである。
縄文時代の文化が、ひろくオリエントと共通する観念を持っていたことは事実だと思う。このことは「日本人とユダヤ人」など、多くの著作と共通している。また、縄文時代人が古代のオリエントや黄河文明人と同じような民族的な観念を持っていたということは、「縄文文明」にとって有力な援軍になってくる。
著者;ネリー・ナウマン 発行所;言叢社同人 発行日;1989.10.16
初回作成年月日;H29.2.5
ネリー・ナウマンは、ウイーン大学で民俗学を専攻し、1949年からこの年までに、日本古代の神話や民俗学的な伝統に関する37本の発表された論文のリストが巻末に示されている。彼女の姿勢は、通説には決して満足せずに、あらゆる方面からの資料を駆使して、神話や日本書記などから新たに、より本質的な発見を試みるもので、その姿勢と方法論は、メタエンジニアリングに共通するところがあるように思う。それは、次の記述に表れている。

『しかし何よりも、神話を古代の日常生活の反映だとしたり、文学的研究や史的研究において民族の起源に関して利用される物語モチーフや物語タイプの集合だとするだけでは十分でないことを次第に意識するようになった。
それは、古代のこうした物語の一つの、すなわち表面的な一面でしかないのである。ミルチア・エリアーデやラファエ・レベッタツオーウェルナー・ミューラー、カール・ケレーニーなど、宗教学からも民俗学、古典古代学の立場からも神話理解のために新たな手掛かりを求め、その分野で重要な貢献をなした人々を読んでから、日本の神話にもその本質的な確信、あらゆる「本当の」神話に見られる存在論的叙述を探求しようと試みたのである。』(pp.2)
『縄文土器の不思議な装飾や奇妙で独特な土偶に魅了されたのである。不満に感じたのは、豊穣儀礼用の土偶であるといったありきたりでじつに愛すべき指摘以外には、この対象のもつきわめて複合した象徴表現を解明する企ては何一つなされておらず、いやこうした方向では何も真剣な試論がなされていないことだった。』
『頭の上に蛇が巻きついている藤内出土の小さな土偶がはからずも道を示してくれた。別の手段で表現されているものの、同一の連関で同一の象徴が、中国の新石器時代の仰韶文化に求められるからである。』(pp.2)
『誤って理解されていた神話のモチーフが、縄文図像のモチーフと何の困難もなく結びつき、そうすることでその本来の意味が認識できることがわかったのである。さらに、神話のモチーフと縄文図像のモチーフとの一致は、このモチーフの成立時期を神話についてもほぼ特定する可能性を示している。』(pp,3)
最初の「哭きいさちる神=スサノオ―生と死」の日本神話像の章では、鬼、人食い、死霊、山姥、多様な森の霊、悪魔的存在の擬人化などの実例に言及した後で、古事記と日本紀のイザナギとの説話を西欧の同様の昔話への民俗学者の解釈を加えて、次のように結論している。
『事件の核心は、火の神を生んだ時に死んだイザナミの死にあります。イザナミは最初の死者であり、物語の成り行きには、死がまったく新たな経験として理解されることが具体的に示されているのです。』(pp.17)
確かに、その後の物語の展開は、死者の醜くなる姿を見てしまったイザナギが、あらゆる手段でそこから離れようとする、すなわち死から逃げようとする行動が具体的にあらわれている。逃げる際に使われたタケノコや葡萄や桃といったものは、当時の日本ではあまり一般的ではなく、中国などの影響もみられるとしている。
『当時の日本は葡萄の実を知ってからそう時間がたっていないからです。葡萄は中国から輸入されたもので、中国にさえ紀元前126年にはじめてトルキスタンからもたらされました。3番目の物として投げられた桃が呪力をもつとする信仰も中国の考え方を取り入れたものに他なりません。』(pp.19)
さらに、「縄文時代の若干の宗教的観念について」では、
『土偶の宗教的意味を個々に考察しようとした真剣な試みはまだなされていない。土偶は主として、あるいはもっぱら女性像であり、したがって地母神の表現であるとか、土偶は豊穣性の象徴として見做すべきだとかいった再三表現される見解は、一般論で責任を負うところがないので、どんな方法をもってしてもこれ以上進まないのである。』(pp.29)
としたうえで、個々の土偶の形や文様についての、膨大な数の比較検討を始めている。さらに、中国の土器、古代オリエントの遺物、イランの動物像などとの比較なども行っている。その中には、『三日月を角として捉える』 や『琉球では、月の神が人間の生に限りがあるのを憐れんで、人間には生の水を、蛇には死の水をあたえてのませようとしたという。』や『 人間の代わりに蛇が不死性をもつ。ちなみにこれは誰でも目にすることができる。蛇は、硬直して「死んで」横たわったのちに、古い皮を脱ぎ捨てて、若がえってそこからはい出てくる』などの民俗学的な知見も多く述べている。
『折口信夫氏は「万葉集」の歌を手掛かりとして、この神話が日本にもあったと仮定してよいと考えた。とにかく岡氏はここで、「月―水―不死性―蛇―生命を授ける月の神―若水」という諸要素が一つにされているとみて、この月の神話が、きわめて古い広範に(シベリアのさまざまな民族やユーラシアのほとんどの部分)伝播した一つの型であるという見解を述べている。』(pp.40)
『したがって月は、大地の実り豊かにする雨という普通の水を持っているだけではなく、「生の水」をも持っているのだ。このことをさらに裏付け、明らかにできる。古代オリエントでも、角としての三日月の観念とならんで、皿としての三日月の見解も登場する。(中略)世界の中心ないし生命の木に結び付く観念には必ず、世界樹や生命の木の根元に棲んだり大地の臍に巻きついている蛇が含まれている。』(pp.41)
つづく、「逆剝―天の斑駒を逆さに剝ぐこと」では、日本書紀などでは、スサノオの悪事の一例である「馬の皮を逆さにむくこと」が示されているが、この行為に対しても、次のように考察している。
『逆剝そのものの正確な意味や、それが神話の脈絡の中で正確に何を意味するのかを理解して初めて可能になる。(中略)したがって神話を理解しようとするときに、そうした落差を埋めることが本論の目的である。』(pp.103)
『スサノウの本来の使命が世界を支配することにあるのがはっきりわかる。』、『ふつう動物は、尻から頭部へ向かって皮を剝ぐ。』などとしたうえで、
『この場合正反対にされた行為はもともと、「生」を呼び起こす祝福行為である。高く差し上げた杯をもって健康と長寿を願う祝杯であり、(中略)重要な点はただ、ある行為をまったく逆にすれば、本来の効果とまったく逆のものが生まれるという思考である。と同時に、こうした逆の行為がもっぱら生と死という存在の両極に関係するのを強調しておかねばならない。』(p113)
ごく最近になって。これと似た見解が示された書籍が、出版され始めているが、西欧人的な合理性から出発して、広い知見を適用すると、結論は今まではなかなか得られていなかったものの発見につながる。
これは、メタエンジニアリングやイノベーションと通じるものがあると思う。
もう一冊のナウマンの書を紹介する。
「生の緒(いきのを)」[2005] 著者;ネリー・ナウマン
発行所;言叢社 発行日;2005.3.10
初回作成年月日;H29.2.5

この本の副題は、「縄文時代の物資・精神文化」で、私にとっての彼女の書の3冊目になる。冒頭の写真集の中には、1989年秋、諏訪郡富士見町の井戸尻考古館で発掘後の縄文土器を多くの研究者と観察する姿が写っている。彼女の縄文に関する研究生活の長さと、深さと、その発表された論文の数は、日本のどの研究者にも負けないほどと思う。
多くの特徴ある文様を有する縄文中期の土器の膨大かつ詳細な観察から、それらの文様は、必ず何らかの象徴的な意味があり、それ等はすべて、当時の精神文化と密接につながっているとの信念からの解読を試みている。
また、西欧人の特徴として、古代ギリシャ、初期の地中海文化、アステカ、コロンブス以前のアメリカ、古代インドなどの文様との比較を随所で行っている。
特に挙げられている特徴は、「後頭部に刻まれた十字に分割された円」(これは、有名な蓼科の縄文のビーナスにも刻まれている)、「渦巻」、「三日月」、「巻貝」、「蛇の頭」、「蛇のとぐろ」などである。これらはすべて、生と死と復活に繋がってくる。
そして、「精神世界―旧観念と新たな象徴」としての「生の緒(いきのを)」に繋がってくる。要所のみを引用する。
『縄文時代中・後期の多くの土偶についても、刻線が臍から上方へ伸びるとともに、小さな渦巻きで臍が表現されている。』(pp.250)
『人体にはそんな線がないので、精神ないし象徴のレベルにその意味内容を求める必要があろう。ひょっとすると意味の手掛かりは、「古事記」や少しだけ異文で「日本書記」に記録された古代歌謡に示されているかもしれない。歌謡は、おのがヲ「緒」に気をつけよという大和の支配者御真木入日子への警告だとされる。敵が「盗み殺せむ」恐れがあったためで、彼の生命はこの緒次第であった。「緒」と「生」は二つのものではない。この歌謡のヲは、「万葉集」の十五の歌にあるイキノヲ「生の緒」という表現に対応するようだ。』
『じつに多くの縄文土器に見られる臍から胸部ないし喉へとつながる縦線は、ほぼ確実にこの緒の描写であろう。右の推定は、この線が多くの場合臍の造形や表示、強調のために渦を巻いているという事実からも説得力を増す。』
『臍が生命のはじまる中心の象徴として、あるいはそれ自体が渦巻の形状をとり、あるいは渦巻に囲曉されているならば、これもやはり生の進展という同一観念を指示しているにちがいない。その進展は生の緒によってさらに拡充されて視覚化されている。そしてイキが息と生きの両方を意味するので、線が胸部と喉のあたりの部位で終わるのはしごく当然というほかない。』(pp.251)
また、多くの土偶に見られる冠型の突起については、「光」を象徴しているとしている。その形が、甲骨文字から金文、漢字の光への変化の過程に現れる、数種類の文字と同じ形をしているというわけである。
縄文時代の文化が、ひろくオリエントと共通する観念を持っていたことは事実だと思う。このことは「日本人とユダヤ人」など、多くの著作と共通している。また、縄文時代人が古代のオリエントや黄河文明人と同じような民族的な観念を持っていたということは、「縄文文明」にとって有力な援軍になってくる。















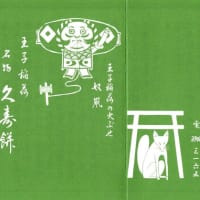




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます