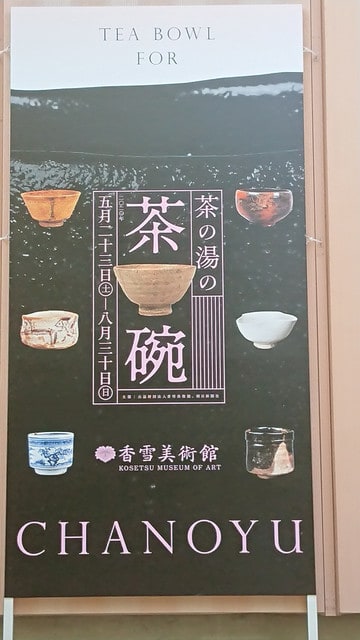『白の闇』 ジョゼ・サラマーゴ 雨沢泰訳 NHK出版
ある男が、突然失明した。それは原因不明のまま次々と周囲に伝染していった。事態を重く見た政府は、感染患者を隔離しはじめる。介助者のいない収容所のなかで人々は秩序を失い、やがて汚辱の世界にまみれていく。しかし、そこにはたったひとりだけ目が見える女性が紛れ込んでいた……。
ノーベル文学賞受賞作家による「疫病小説」。視界が真っ白になり見えなくなる原因不明の感染症が蔓延する。隔離された収容所の中では、介助者も治療者もおらず、やがて食料の独占や暴力がはびこっていく。コロナ禍の最中に、この本を読むとは思わなかった。現代との違いは、感染症が失明するもので感染力が強いこと。次々と人々は感染し、社会は麻痺してしまう。電気、水はとまり、食料はない。異臭。略奪。糞便だらけ、死体だらけの街を人々は夢遊病者のようにさまよう。
突然失明し、見えない中で、人々は如何に人間らしく生きて行けるのか。人の視線がないことで、人間の獣性がむき出しになる。なぜか一人失明を免れた医者の妻は見えるがゆえにすさまじい光景を見ることになる。見えることが、いいのか、悪いのか。あまりのことに驚きつつも、一気に読んだ。「」がなく、誰が話したのか主語もないため、読みにくさはあるが、それがかえって臨場感や緊迫感を増す感じがした。災厄が去った後のことを思うと、いろいろと考えてしまった。
『浮遊霊ブラジル』 津村紀久子 文藝春秋
定年退職し帰郷した男の静謐な日々を描く川端康成文学賞受賞作(「給水塔と亀」)。「物語消費しすぎ地獄」に落ちた女性小説家を待ち受ける試練(「地獄」)。初の海外旅行を前に急逝した私は幽霊となり旅人たちに憑いて念願の地を目指す(「浮遊霊ブラジル」)。自由で豊かな小説世界を堪能できる七篇を収録。
一言で言えば、軽妙。なんかおかしい。
ある男が、突然失明した。それは原因不明のまま次々と周囲に伝染していった。事態を重く見た政府は、感染患者を隔離しはじめる。介助者のいない収容所のなかで人々は秩序を失い、やがて汚辱の世界にまみれていく。しかし、そこにはたったひとりだけ目が見える女性が紛れ込んでいた……。
ノーベル文学賞受賞作家による「疫病小説」。視界が真っ白になり見えなくなる原因不明の感染症が蔓延する。隔離された収容所の中では、介助者も治療者もおらず、やがて食料の独占や暴力がはびこっていく。コロナ禍の最中に、この本を読むとは思わなかった。現代との違いは、感染症が失明するもので感染力が強いこと。次々と人々は感染し、社会は麻痺してしまう。電気、水はとまり、食料はない。異臭。略奪。糞便だらけ、死体だらけの街を人々は夢遊病者のようにさまよう。
突然失明し、見えない中で、人々は如何に人間らしく生きて行けるのか。人の視線がないことで、人間の獣性がむき出しになる。なぜか一人失明を免れた医者の妻は見えるがゆえにすさまじい光景を見ることになる。見えることが、いいのか、悪いのか。あまりのことに驚きつつも、一気に読んだ。「」がなく、誰が話したのか主語もないため、読みにくさはあるが、それがかえって臨場感や緊迫感を増す感じがした。災厄が去った後のことを思うと、いろいろと考えてしまった。
『浮遊霊ブラジル』 津村紀久子 文藝春秋
定年退職し帰郷した男の静謐な日々を描く川端康成文学賞受賞作(「給水塔と亀」)。「物語消費しすぎ地獄」に落ちた女性小説家を待ち受ける試練(「地獄」)。初の海外旅行を前に急逝した私は幽霊となり旅人たちに憑いて念願の地を目指す(「浮遊霊ブラジル」)。自由で豊かな小説世界を堪能できる七篇を収録。
一言で言えば、軽妙。なんかおかしい。