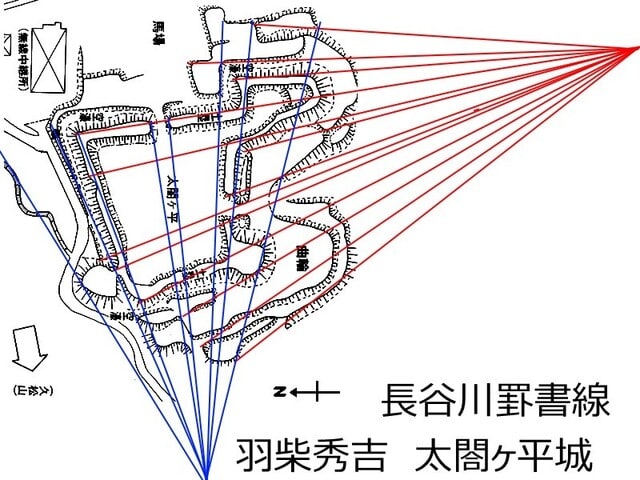『城歩会』の評判 越中安田城と越後安田城 城郭定理
◆質問者
この投稿の趣旨や目的とは何?
◆長谷川
日本の城の縄張に関わる定理
や基礎知識の重要項目定義!
◆一般者
長谷川先生に越中と越後の両安田
城を比較研究して頂きたいのです。
◆『城歩会』会員
音楽にはカノン進行和音とか
黄金和音進行CAḿFGなどの
黄金律と言う法則があります。
越中越後の両安田城に通底
する城郭縄張の黄金律つまり
縄張手法を解明する事は日本
の城の設計理論の発見と言う
城郭研究の定理に関わるもの
明治大正昭和平成の城郭論
で城郭ビイスタは語られる事
なく無視され続けていました。
城郭ビイスタ論は幾何数学
て言えば345の比率を持つ
三角形の図形を証明する様な
ピタゴラス定理、三平方の定理
に相当最重要事項に相当する
城郭定理の法則発見なのです。
◆『城歩会』会員
我々は城郭研究の進捗
を望む米原『城歩会』ですが
この会こそ『余呉城郭研究会』
よりも早く設立された前身組織
母体であり良心的な本格城郭
見学組織と言えます。我々とし
ては長谷川先生に活動の本拠
を米原に帰還され東海、近畿、
北陸の各地の城郭遺跡見学を
各地の城郭遺跡見学希望こそ
望む声が根強く残っています。
私にすればこの会こそ本家本元で
その活動履歴『余呉城郭研究会』
よりはるかに古い本命の組織です。
是非『城歩会』復活復興を願う!
◆長谷川
困ります!私自身は人気が0!
私の元『城歩会』に集合する人
も0ですよ。当然の事なからも
私のブログも誰も読んでない!
私には人を集める人気が無い
肩書や著書もなき無位無官の
隠者と言う事なのです!確かに
『城歩会』は城郭遺跡を検分す
る事に関して『余呉城郭研究会』
よりより特化した城郭見学専門の
組織とは言えますが、、、、、、、。
◆対談者
学術的に重要な意味を合い含む
越中安田城のビイスタ工法を是非
御教示下さい。
◆長谷川
ウィツキペデイア掲載の越中安田
城の航空写真からは 美しいビイ
スタ工法腺が読取みとる事が可能!


◆一般様
まさか?この様に城郭を読むとは
流石は城郭ブームから深堀時代
へと時代が移り変わる時代の前兆
◆長谷川
2方向から放射状に縄張位置決
めする重複型ビイスタも読み取
れます。日本の城、越中安田城
の見事なるコンポーズ城郭組立
つまり城郭縄張の定款と言える。
▼越中安田城 重複型ビイスタ

◆対談者
長谷川先生!自分が知っている
自分の町の城に城郭ビイスタが
存在する事を知って一番驚く人
はその土地の郷土史家さんでは
なく私の様に歴史を全く知らない
人が一番驚く訳なのですよ!
歴史が得意な郷土史家さんは文字
中心に思考して5W1Hに従い歴史を
語る「語り部」さんな訳です!それは
それで従来より貴重な存在でありま
す。それは地域集団学習の世界とも
言える地域活動の重要な事ですが
でも私の様に城跡の形を見る城址
形状見る見学者には長谷川先生
の城郭ビイスタ論はすさまじい電撃
を伴い心に響いて来ます。従来の
地方郷土史や自治体歴史観念と
は全く異なる斬新な研究の世界が!
◆対談者の友人女性
私達少女時代は糸取り綾取りと
言う遊びをよくやったものです。
だから長谷川先生の城郭ビイ
スタ論一発で解りました!詰り
視点が根本的に私と違う郷土
史の先生はなにやら口を濁され
怪訝な顔をされビイスタ論否定
をされるのが常な訳です5W1H
という固定概念や通念に縛られ
て城跡を図形として捉える事が
苦手な方が多いかと思います。
そもそも文字は左脳分野の事
図や形状は右脳分野と言える
人間は用途により使う脳が異な
るのです。ですからこれ生理的
に別分野の学問世界と言える。
◆反論者
ふん!なまいきな事を言う奴ら!
ワシこそが城郭の権威で象徴!
◆達観者
裸の大様を看破できない愚物
とは何時の世も存在するモノ!
◆対談者
郷土の城跡に城郭ビイスタ工法
が存在する事は設計測量なされ
た一流の城と言えます。昔よく
言葉をよく耳にしました。正直に
言わせてもらうと昭和平成と城郭
のJiS規格に相当する城郭ビイスタ
論が語られなかった。しかし令和
になり長谷川先生の城郭ビイスタ
論は正に定理で城郭JiS規格にも
ISOにも相当する理論である事が
長谷川先生のブログでは次々と
登場して来ました。これが令和の
城郭研究のトレンド「花形」である
事はもう確実になって来ました!
◆対談者の友人女性
じやあ私の郷里蒲原郡の安田城
に城郭ビイスタは存在しますか?
長谷川先生解答解説を願います。
▼越後安田城図

◆長谷川
新潟県阿賀野市の安田城
には城郭ビイスタ工法存
在致します。それも極め
て幾何学測量の基本に徹
した非常に精緻な城です。



◆長谷川
新潟県阿賀野市の安田城は
重複型城郭ビイスタ工法で
堅実に築城されています。
つまりは
越中安田城も
越後安田城も
城郭ビイスタの定理に従い
縄張設計された城と言える

◆みんな
どこまでスゴイんだよ!城郭
ビイスタ論これ本物金字塔だ!
俺は長谷川先生の一番弟子だ!
いえ私が先生の一番の理解者
◆対談者
ビイスタ工法理論って素晴らし
い。黒田如水の福岡城だって

◆みんな
東海の今川方 村木砦にせよ

◆長谷川
羽柴秀吉の太閤ケ平城にせよ
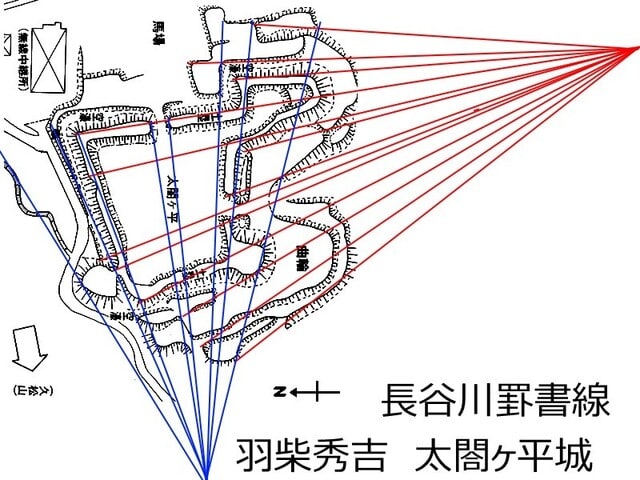
◆長谷川
家康の初期江戸城にせよ
ビイスタ工法を駆使して
築城しております。

安田城(やすだじょう)は、越後国蒲原郡
(現在の新潟県阿賀野市)にあった日本の城。
白河庄(現在の新潟市北区の一部を含む阿賀野市
周辺)の地頭に任ぜられた伊豆の大見氏が、
鎌倉時代の初頭に入封し築城されたと言われて
いる。また、築城された頃は周囲の沼地を天然
の堀とした主郭のみの館であったが、他の鎌倉期
から存在する城と同様に戦国期に外郭や堀を増設し、
本格的な城郭となったと考えられている。
越後大見氏は地名の安田を名乗り、その分家は分地先
の水原を名乗っている。安田氏は戦国時代には、
揚北衆と呼ばれる北越後の国人衆として上杉謙信を
始めとする上杉家の家臣として活躍。城主安田長秀
は謙信より血染めの感状をうけており、この書状は
現存している。慶長3年(1598年)に上杉氏が会津
に移封となると、その後に本庄城に入った村上頼勝
の配下である吉武右近が入城。さらに元和4年
(1618年)に堀直寄が村上城(本庄城から改名)
に入り、配下の番城となる。元和8年(1622年)に
一国一城令が発布された事により一旦は廃城。
寛永16年(1639年)、直寄の次男の直時が3万石で
安田藩を創設した事により安田城も陣屋としてでは
あるが復活する。しかし、その子直吉は正保元年
(1644年)に領地替え(領地交換)により村松
(現在の五泉市)に移り再び廃城となった。