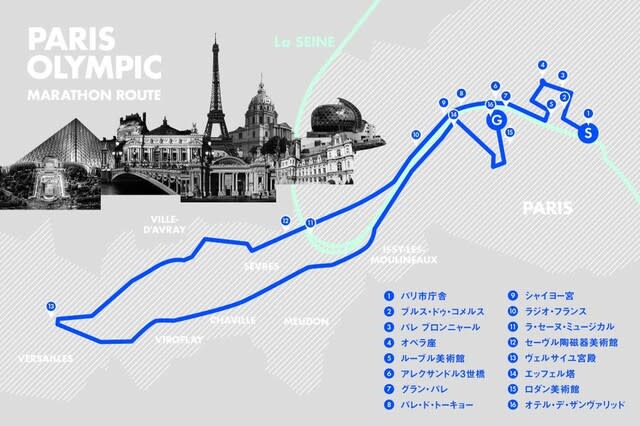藤田嗣治 パリを歩く
清水敏男 著
東京書籍 発行
2021年9月9日 第一刷発行
藤田嗣治のフランスでの足跡を追っかけています。
文章と絵画と写真が、見事に調和とれています。
この本で扱っている絵画の中で自分が好きなのは『ホテル・エドガー・キネ』と『フレール河岸 ノートルダム大聖堂』です。
チューリヒにて 序にかえて
スイスが山岳の地と地と思うのは間違いで平地の国だ、と思う。
山岳が注目されるようになったのは啓蒙主義の時代に言語学者ソシュールの祖先が山岳の文化に関心を持って以来の事に過ぎない。
チューリヒもバーゼルもジュネーヴもヨーロッパと地続きだ。決して山岳の中の孤立した街ではない。
(バーゼルでドイツ国境まで簡単に歩いて行ったことを思い出します)
絵画が非物質の世界と物質的世界とのちょうつがいのような存在だとしたら、藤田が確実にいた場所、つまりこの世の側もできるだけ見ておくことは無意味ではないだろう。
藤田は1968年1月29日、チューリヒで亡くなった。
パリ篇
第1日 ホテル・エドガー・キネ 14区
ホテル・オデッサが藤田が1913年の夏、初めてパリに来た時に泊まったホテル
その道路の反対側にホテル・エドガー・キネ
ホテル・エドガー・キネを描いた絵(1950年)は藤田の二つの時期を象徴している。青春のパリと初老のパリ、しかも傷心で戻ってきたパリである。
その絵には赤い帽子の少女が描かれている。犬に挨拶する少女は新しい時代に挨拶している。
第2日 ヴィクトル・シェルシェ街 14区
ピカソは目に見える対象をバラバラに分解し、その後画面上で自由に再構成する、という絵、いわゆるキュビスムを推し進めたが、
ルソーの天性はそれをごく自然にやっている。
藤田の驚きは何層にも重なっている。
ピカソの描いた『アヴィニョンの娘たち』を見てピカソに驚き、ピカソがルソーを大切にしていることに驚き、そしてルソーに驚いた。
黒田清輝の教えとあまりにも違う。
第3日 税関吏ルソー緑地(マラコフ市)
ブルーデル美術館は昔は忘れられたような質素な美術館だったが、今は活発に活動している。
藤田の『パリ風景』
線路の向こう側はイッシー=レ=ムリノー市、線路のこちら側で画面の左側はマラコフ市。
(以前イッシー=レ=ムリノーのIT化についての原稿を書くために、当市を訪問したり会議に出席したことを思い出します)
マラコフ市でルソーが税関吏として働いていた。
ヴェルサンジェトリックス街はガリア人ウエルキンゲトリクスにちなむ。
なぜその名がついたのかというと、アレジアとジェルゴヴィという、彼とシーザー軍との主戦場の地名を冠した通りが近くにあったから。
第4日 パンテオン 5区
ピュヴィ・ド・シャヴァンヌがパンテオンに描いた壁画。
その草を同じように藤田と小杉未醒も描いていた。
第5日 ラ・ポエジー街 8区
第6日 グラン・パレ 1区
ド・ゴールの彫刻。都市景観と彫刻の関係がよい
第7日 パリ国際大学 14区
第8日 フレール河岸 4区
1950年、疲れ切った藤田をノートルダム大聖堂は受け入れた。その感謝の気持ちを絵にすることを考えた。しかし藤田は壮麗な大聖堂を描かなかった。フレール河岸から見た尖塔をもってしてノートルダム大聖堂とした。
戦争の傷は自分もパリも未だ癒すことのできない深手の傷だったに違いない。パリに戻ってきた喜びは抑えられ、深く内面に沈んでいた。ノートルダム大聖堂をわずかに拝む光景を選んだのはそうした藤田の心だったのではないだろうか。
第9日 カンパーニュ・プルミエール街23番地 14区
タルティーヌはバゲットを長めに切り、半分に割って内側にバターが塗ってある。そこにジャムをつけて食べる。フランス人はよくそれをカフェにつけて食べている。
(ランボーは『居酒屋みどり』でハムのタルティーヌをビールと一緒に食べていました)
第10日 カンパーニュ・プルミエール街17番地bis 14区
第11日 蚤の市 18区
『日曜日の蚤の市』の成立の連鎖
ピカソ→アンリ・ルソー→市壁→ラ・ゾーヌ→スラム街→蚤の市→(骨董・ブロカント趣味)→スラム街の撤去→野原
第12区 ガリエラ美術館 16区
藤田が出展した『誰と戦いますか』という絵。格闘家の面々を描く。若い時にパリの舞踏会で柔道のパフォーマンスをした藤田。
パリ市立近代美術館が国立近代美術館だった時に、展示室の窓からエッフェル塔を見た著者。いまだに心の網膜に残っているとのこと。
(ひょっとした自分がそこから見たエッフェル塔と同じだったかも?)
遠足編 第1日 ヴィリエ=ル=バークル
藤田の住居兼アトリエがある
遠足編 第2日 アヴィニョン
1918年アヴィニョンにいた藤田。1920年代のパリの成功をもたらした白い下地の技法をほぼ完成させたのはアヴィニョン滞在中だったと著者はみている。
藤田のいた場所はアヴィニョン新町(ヴィルヌーヴ・レザヴィニョン)
ダラディエ橋を渡り切り左に折れる。
(コローがアヴィニョン教皇庁を描いた場所と同じ角度ではないだろうか?)
遠足編 第3日 ランス
藤田と君代夫人の墓があるシャペル(礼拝堂)
ランスの大聖堂を集中的に爆撃したドイツ軍。歴代フランス国王の戴冠式を行った大切な場所だからだろうか。