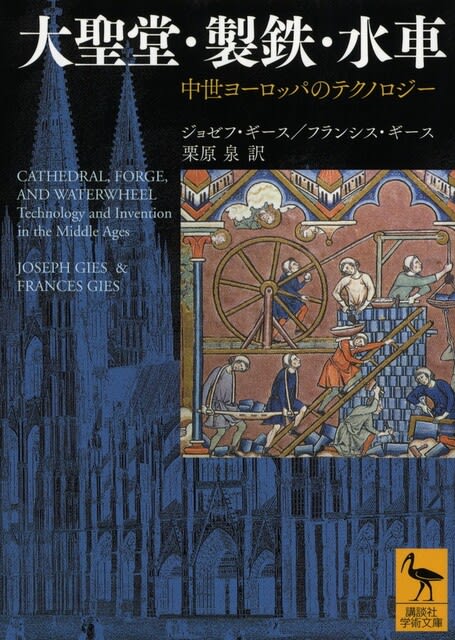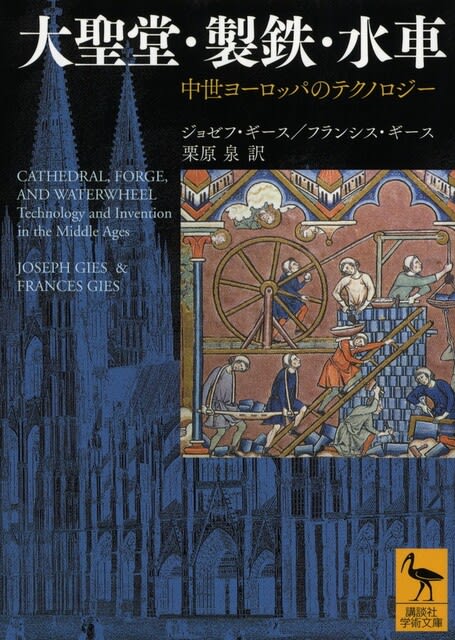
大聖堂・製鉄・水車
中世ヨーロッパのテクノロジー
ジョゼフ・ギース/フランシス・ギース 著
栗原泉 訳
講談社学術文庫
2012年12月10日 第1刷発行
第一章 バベルの塔・ノアの箱舟 キリスト教とテクノロジー
第二章 古代のテクノロジー 功績と限界
ヘレニズム時代の占星術の関心から、アレクサンドリアで「アストロラーベ(天体観測儀)」が生まれた。発明者は知られていない。
これは「世界で最初の科学機器」である。
アストロラーベ(星の皿)の原形は、天体図を描いた木製の円盤で、外縁に360度の目盛りが刻んであった。
ローマ人は工学技術に優れ、他から借り入れる才にも長けていたものの、動力利用の面で二つの重大な失敗を犯したために技術的な弱点を抱えていた。
その第一は馬のハーネスだった。馬の力をわずかしか引き出せなかった。
第二の失敗は水車の利用にあった。ローマ人は水車という実に貴重な発明をまったく利用しなかったとまではいえないが、その大きな可能性に気付かなかった。
この二つの技術的弱点に加えて、ローマ人に欠けていたものは、理論科学と経済学であった。
ギリシャ人が行動より知識を優先させたのに対し、ローマ人はその逆だった。知識を得ることより行動を優先した。
経済については、ローマ帝国は政治、軍事の点で立派に機能しているかに見えたが、実は恒常的に貧しく停滞した農民経済を抱えていた。
農園の経営は奴隷たちの労働に支えられていた。
大地主は技術開発によって労働コストを削減する気は毛頭なかったし、奴隷たちは顧客になりえなかった。
第三章 それほど暗くはなかった暗黒時代 西暦500~900年
「ローマの滅亡」では、実際に何が滅びたのか。テクノロジーに関していえば、ほとんど何も滅びていない
六世紀 「蛮族」の世紀
七世紀 イスラムの世紀
八世紀 カロリング朝の世紀
九世紀 ヴァイキングの世紀
中世の船頭も竿をさして川を下り、目的地に着くと船を材木として売り払い、歩いて帰った。
第四章 アジアとのつながり
古代から中世にかけて、技術が伝わる方向はほぼ常に東洋から西洋だった。
ヨーロッパにはアジアに伝えるべきものが何もなく、一方でアジア、とりわけ中国は西洋につたえる技術をたくさん持っていた。
中世の特徴といえば、ヨーロッパ、アフリカ、アジアで科学技術が広範に伝播したことだが、これに特異な役割を担ったのはアラブ人である。
香料や絹だけでなくアジアの発見や発明も西洋に伝えたアラブ人は、ヨーロッパがギリシャの知の遺産をついに取り戻す手助けもした。
第五章 商業革命の技術 西暦900~1200年
西洋で初めて公開羅針儀に言及したのは、12世紀英国の学者アレクサンダー・ネッカムである。
著書『事物の本性について』の中で次のように言っている。
「船乗りたちは・・・曇天で太陽の光の恵みにあずかれないとき、あるいは夜の暗闇に包まれて・・・航路がわからない時は針のついた磁石に触れる。すると磁石が回転し、回転運動が止まると磁針の先は北を指している」
これをネッカムはおそらくパリで1190年頃書いた。
羅針儀の船上での使用は、当時はまだ決して一般的ではなかった。
フランシス・ベーコンの錬金術についてのたとえ話
「ある男がブドウ畑に黄金を埋めておいたと、息子たちに言い残して逝く。息子たちは畑を掘り返すが、黄金は見つからない。だが畑土を掘り返したことで上々の収穫を得ることができた。錬金術についていえば、黄金を作るための努力をとおして、多くの有益な発明や啓発的な実験がなされたのだ」
(それだと、畑はむちゃくちゃになるだけだと思いますが・(笑))
十二世紀末の西ヨーロッパはその姿にも大きな変化が起きていた。
城や大聖堂が登場し、土地の開墾や沼地の干拓が進み、水車や風車が回り、病院や大学が姿を現した。
第六章 中世盛期 西暦1200~1400年
第七章 レオナルドとコロンブス 中世の終わり
レオナルドがあちらこちらに描いた走り書きの寄せ集めを「手稿集」と呼ぶが、その歴史的価値は、作者の技術への貢献というよりも、作者が生きた時代の空気を他の誰にもできないような方法で描いた点にある。
発明だけでなく、ルネサンスの華であった文学や美術もまた、中世に深く根をおろしている。
ジョット、ダンテ、ペトラルカ、ボッカチオ、チョーサーはみな1400年以前に生きた。
そしてジョットを除く四人はみなプロヴァンスの吟遊詩人や滑稽譚作者たちの影響を受けている。
中世に芽生え、15世紀に花開いた技術システム
・大洋航海術
・活版印刷
・火薬の改良による有効な火器
香辛料貿易の謎を解く二つのカギ
・腐りにくくて高い値がついた
・香辛料と呼ばれたのは、鍋の中に放り込まれたのはほんの一部。風味付け、香水、染料、医薬品などさまざまな用途があった。