読書の秋となり、少し真面目な本を読むには良い時期である。県図書館で先月借りてきた10冊の中で最後に読んだのは、宮下洋一「死刑のある国で生きる」という370ページ余りの本である。日本の死刑制度については、このブログの2019年6月15日付け「映画ダンサー・イン・ザ・ダークの一場面が今でも」の中でディビッド・T・ジョンソン「アメリカ人のみた日本の死刑」で触れた。
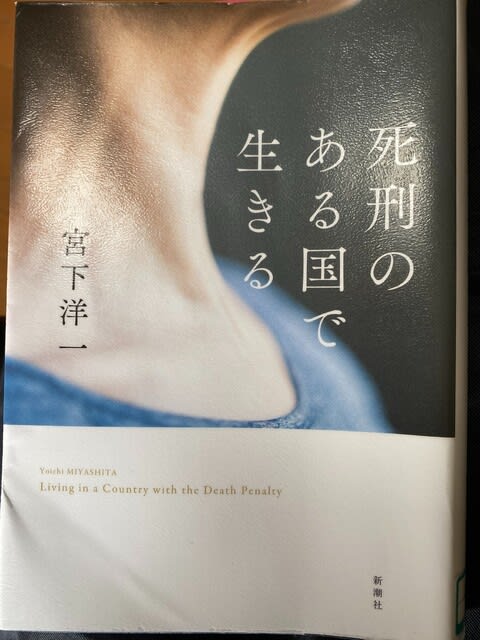
「死刑のある国で生きる」の著者はフランスやスペインなどに28年間住んでいるジャーナリストである。彼は、エピローグでこう言っている。「私は、死刑はあっても安全な国と、死刑はなくとも危険な国のどちらが良いかと問われれば、前者であると断言できる」(前者は日本、後者は欧米の国)と書いているように、死刑制度を支持する大半の国民の気持ちを理解できると書いている。先進国で死刑制度を採用しているのは、今やアメリカ(連邦と軍と27州が採用)と日本だけとなった。世界では死刑制度を廃止ないしは停止している国が増えつつあるの中で、日本の国民の死刑制度への支持はむしろ高まっている。これについて著者は、欧米人とは異なる正義や道徳の中で暮らしているとして、井田良教授(法制審議会会長、中央大学法科大学院)の「死刑制度と刑罰理論ー死刑はなぜ問題なのか」から「日本人にとっての死と生は、武士道の思想につながっており、自らの罪ないし恥を、死をもって贖い、精算することは日本人の感覚に根を下ろしている」と引用する。だからこそ、西側先進国の流れに合わせ、死刑を廃止することは、たとえ政治的に実現不可能ではなくとも、日本人にとっての正義を根底から揺るがすことになりかねない。
もちろん、著者がこのような考えに至るまでの関係者へのインタビューと思索の中でのことである。その思索の旅を少したどってみよう。まずは、アメリカテキサス州(「死刑大国」と呼ばれる)の刑務所に収容された死刑執行日が一ヶ月を切った死刑囚とのインタビューから始まる。彼は、妻、娘、妻の父を殺害していた。驚くのは、著者はその死刑囚にたどり着くのに、全てオンラインで公開された情報(顔も)を基に刑務所長に連絡をとり、許可を得ていることである。面会する中で、罪を悔やみ、反省の言葉を述べている純朴そうな顔を思い出すと彼に与えられた刑罰が本当に正しかったのかと考えるに至る。新型コロナのために、この死刑囚の執行は延期され、再度の面会が可能になったのは、執行の10日前であった。テキサス州では、被害者及び加害者の親族そしてプレス関係者が薬物注射による執行現場に立ち会うことができるが、著者は立ち会いが許可されなかった。
次にフランスの死刑制度についての調査が始まる。フランスではヨーロッパで死刑を廃止したのが、最も遅く1981年。それまでの執行方法は名高いギロチンだった。私たちは、これを残酷な方法だと考えるが、フランスの関係者には執行は一瞬で行われ、残酷ではないと主張する。確かに一理あると思ってしまう。江戸時代の死刑の一つ斬首(江戸時代の死刑には6種類あり、軽い方から下手人、死罪、獄門、磔、鋸引、火罪、前の3つが斬首で、ただし執行後の処理が異なる)の場面がドラマや小説で見られるが、これだと失敗する可能性が高いと思われる。訪れた刑務所からは既にギロチンは撤去されており、刑場には流れ出るおびただしい血が流れるように溝が作ってあった。
フランスが遅まきながらも死刑制度を廃止を促したのは、ミッテラン時代に司法大臣を務めたロベール・バダンテールの議会での大演説だった。国民あるいは議会ではまだ死刑制度に賛成するものが多い中で演説を行った。「フランスは偉大であります。ヨーロッパで最初に拷問の廃止を実現した国」「奴隷制を世界で最初に廃止した国の一つでもある」「しかし、西ヨーロッパでは、死刑を廃止する最後の国のひとつ、ほぼ最後の国になりそうです」「明日、みなさまのおかげで、フランスの司法はもはや人を殺す司法ではなくなります。明日みなさま方のおかげで、明け方にフランスの刑務所の黒いひさしの下でこっそり行われる、我々の共通の恥とも呼べる死刑がなくなります。」
次に著者は日本の3人の死刑囚ないしは未決死刑囚の関係者に会いに行く。そこでの問いは、「死刑は被害者遺族を救うのか」というものだった。被害者親族の裁判への参加が認められるようになった。そこでは加害者に極刑を望みますという願いを聞くことが多い。しかし、彼らは心底そのように考えているのだろうか。母親を殺された被害者宅を著者は訪れる(このようなインタビューに応じることが日本では少ないのではないか)。3時間に及ぶインタビューの最後に、著者は遺族に「N(実名あり)の刑が執行されたら、心の平和は訪れると思いますか」と尋ねた。父親は「ひと段落したと思うでしょうね、きっと」と答える一方で「Nが死のうが生きようが、母親は帰ってこないですからね」。著者はさらに「ならば、死刑でなくても、仮釈放のない終身刑という考え方もあるのでは」と尋ねる。父親は「それやったらまだ分からないです(死刑と終身刑とどちらが良いのか)」と答えた。
以上で本の紹介は終わる。本を読んで思ったのは、終身刑は想像以上に過酷な刑罰であるかもしれないということだった。死の恐怖からは逃れられても、拘束された状態は死ぬまで続くことは普通の人間にとって耐えがたいことではないか。しかし、日本の死刑は執行まで長い年数が経過している例が多いうえに、いつお告げが来るかわからない。これは極めて残酷なことではないだろうか。私は、フランスのような政治家が出てきて、死刑制度がなくなる形が最も望ましいと考えるようになってきた。時間がどれだけかかるかわからないが、その希望は失いたくない。
親鸞は、私たち全員がお念仏を唱えれば成仏できると言った(浄土真宗大谷派(お東)は日本の宗教界で初めて死刑制度の廃止を訴えた)。
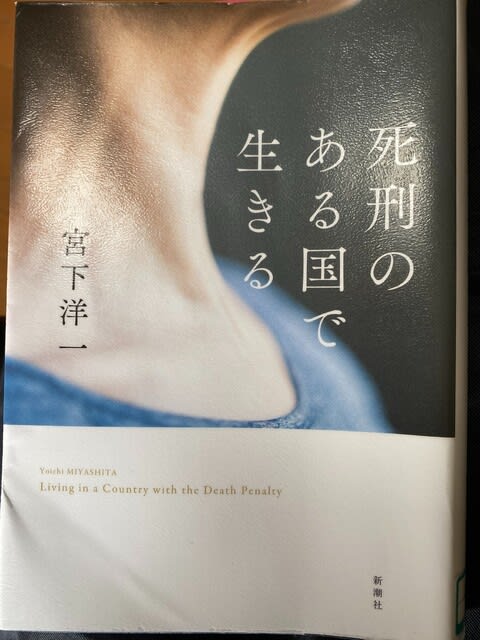
「死刑のある国で生きる」の著者はフランスやスペインなどに28年間住んでいるジャーナリストである。彼は、エピローグでこう言っている。「私は、死刑はあっても安全な国と、死刑はなくとも危険な国のどちらが良いかと問われれば、前者であると断言できる」(前者は日本、後者は欧米の国)と書いているように、死刑制度を支持する大半の国民の気持ちを理解できると書いている。先進国で死刑制度を採用しているのは、今やアメリカ(連邦と軍と27州が採用)と日本だけとなった。世界では死刑制度を廃止ないしは停止している国が増えつつあるの中で、日本の国民の死刑制度への支持はむしろ高まっている。これについて著者は、欧米人とは異なる正義や道徳の中で暮らしているとして、井田良教授(法制審議会会長、中央大学法科大学院)の「死刑制度と刑罰理論ー死刑はなぜ問題なのか」から「日本人にとっての死と生は、武士道の思想につながっており、自らの罪ないし恥を、死をもって贖い、精算することは日本人の感覚に根を下ろしている」と引用する。だからこそ、西側先進国の流れに合わせ、死刑を廃止することは、たとえ政治的に実現不可能ではなくとも、日本人にとっての正義を根底から揺るがすことになりかねない。
もちろん、著者がこのような考えに至るまでの関係者へのインタビューと思索の中でのことである。その思索の旅を少したどってみよう。まずは、アメリカテキサス州(「死刑大国」と呼ばれる)の刑務所に収容された死刑執行日が一ヶ月を切った死刑囚とのインタビューから始まる。彼は、妻、娘、妻の父を殺害していた。驚くのは、著者はその死刑囚にたどり着くのに、全てオンラインで公開された情報(顔も)を基に刑務所長に連絡をとり、許可を得ていることである。面会する中で、罪を悔やみ、反省の言葉を述べている純朴そうな顔を思い出すと彼に与えられた刑罰が本当に正しかったのかと考えるに至る。新型コロナのために、この死刑囚の執行は延期され、再度の面会が可能になったのは、執行の10日前であった。テキサス州では、被害者及び加害者の親族そしてプレス関係者が薬物注射による執行現場に立ち会うことができるが、著者は立ち会いが許可されなかった。
次にフランスの死刑制度についての調査が始まる。フランスではヨーロッパで死刑を廃止したのが、最も遅く1981年。それまでの執行方法は名高いギロチンだった。私たちは、これを残酷な方法だと考えるが、フランスの関係者には執行は一瞬で行われ、残酷ではないと主張する。確かに一理あると思ってしまう。江戸時代の死刑の一つ斬首(江戸時代の死刑には6種類あり、軽い方から下手人、死罪、獄門、磔、鋸引、火罪、前の3つが斬首で、ただし執行後の処理が異なる)の場面がドラマや小説で見られるが、これだと失敗する可能性が高いと思われる。訪れた刑務所からは既にギロチンは撤去されており、刑場には流れ出るおびただしい血が流れるように溝が作ってあった。
フランスが遅まきながらも死刑制度を廃止を促したのは、ミッテラン時代に司法大臣を務めたロベール・バダンテールの議会での大演説だった。国民あるいは議会ではまだ死刑制度に賛成するものが多い中で演説を行った。「フランスは偉大であります。ヨーロッパで最初に拷問の廃止を実現した国」「奴隷制を世界で最初に廃止した国の一つでもある」「しかし、西ヨーロッパでは、死刑を廃止する最後の国のひとつ、ほぼ最後の国になりそうです」「明日、みなさまのおかげで、フランスの司法はもはや人を殺す司法ではなくなります。明日みなさま方のおかげで、明け方にフランスの刑務所の黒いひさしの下でこっそり行われる、我々の共通の恥とも呼べる死刑がなくなります。」
次に著者は日本の3人の死刑囚ないしは未決死刑囚の関係者に会いに行く。そこでの問いは、「死刑は被害者遺族を救うのか」というものだった。被害者親族の裁判への参加が認められるようになった。そこでは加害者に極刑を望みますという願いを聞くことが多い。しかし、彼らは心底そのように考えているのだろうか。母親を殺された被害者宅を著者は訪れる(このようなインタビューに応じることが日本では少ないのではないか)。3時間に及ぶインタビューの最後に、著者は遺族に「N(実名あり)の刑が執行されたら、心の平和は訪れると思いますか」と尋ねた。父親は「ひと段落したと思うでしょうね、きっと」と答える一方で「Nが死のうが生きようが、母親は帰ってこないですからね」。著者はさらに「ならば、死刑でなくても、仮釈放のない終身刑という考え方もあるのでは」と尋ねる。父親は「それやったらまだ分からないです(死刑と終身刑とどちらが良いのか)」と答えた。
以上で本の紹介は終わる。本を読んで思ったのは、終身刑は想像以上に過酷な刑罰であるかもしれないということだった。死の恐怖からは逃れられても、拘束された状態は死ぬまで続くことは普通の人間にとって耐えがたいことではないか。しかし、日本の死刑は執行まで長い年数が経過している例が多いうえに、いつお告げが来るかわからない。これは極めて残酷なことではないだろうか。私は、フランスのような政治家が出てきて、死刑制度がなくなる形が最も望ましいと考えるようになってきた。時間がどれだけかかるかわからないが、その希望は失いたくない。
親鸞は、私たち全員がお念仏を唱えれば成仏できると言った(浄土真宗大谷派(お東)は日本の宗教界で初めて死刑制度の廃止を訴えた)。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます