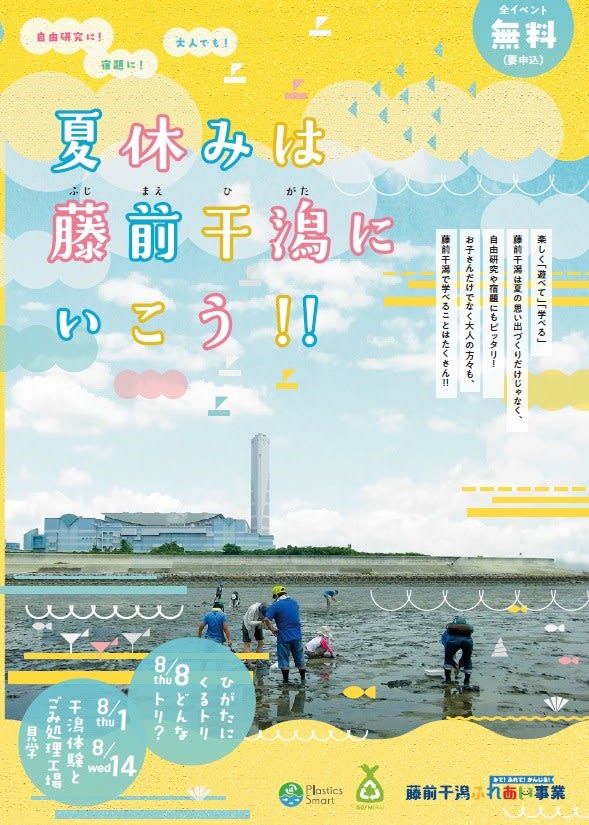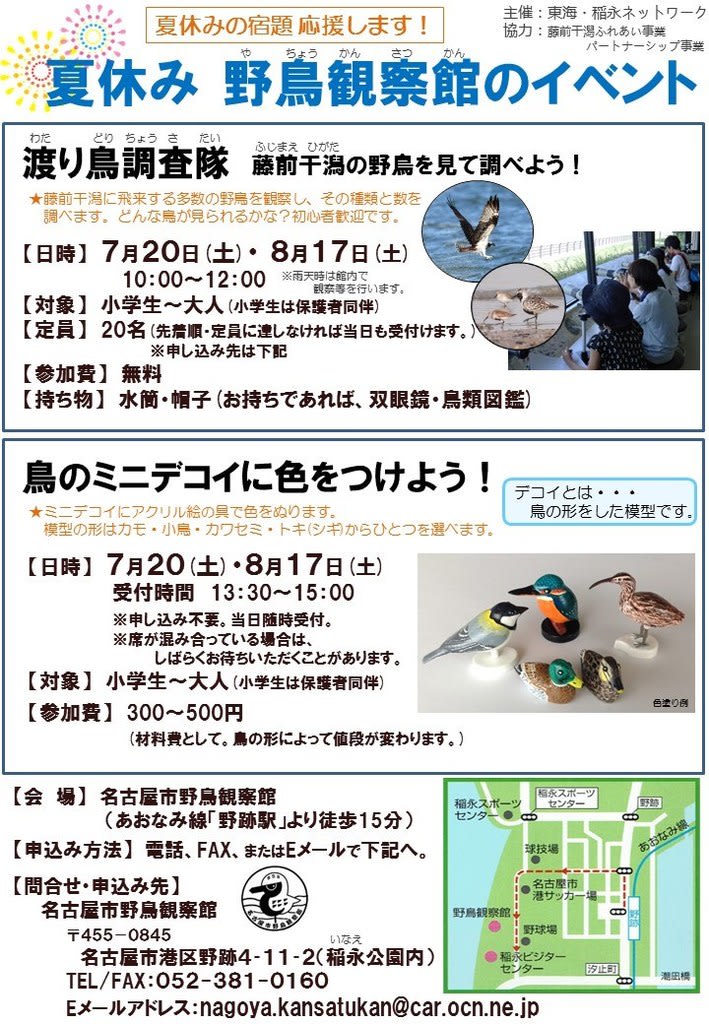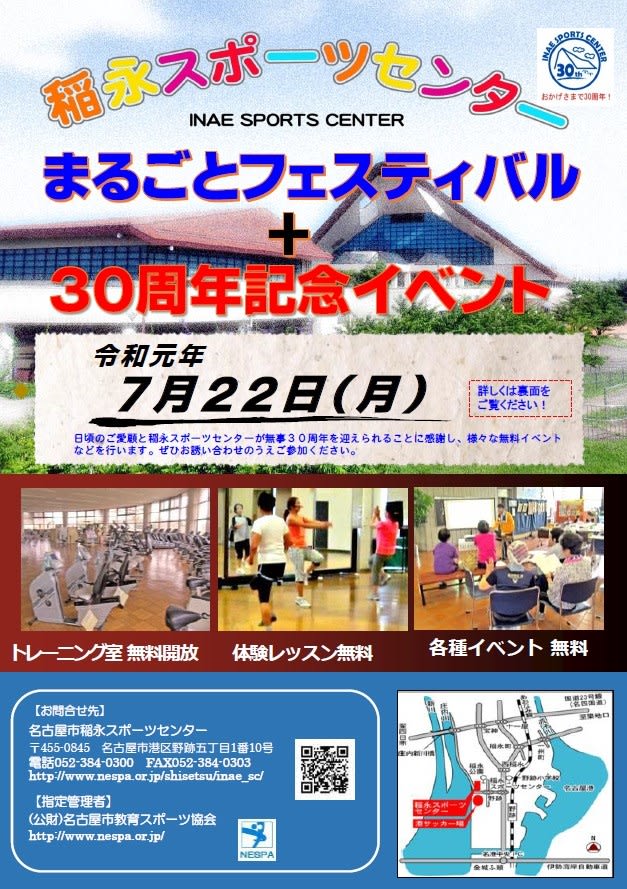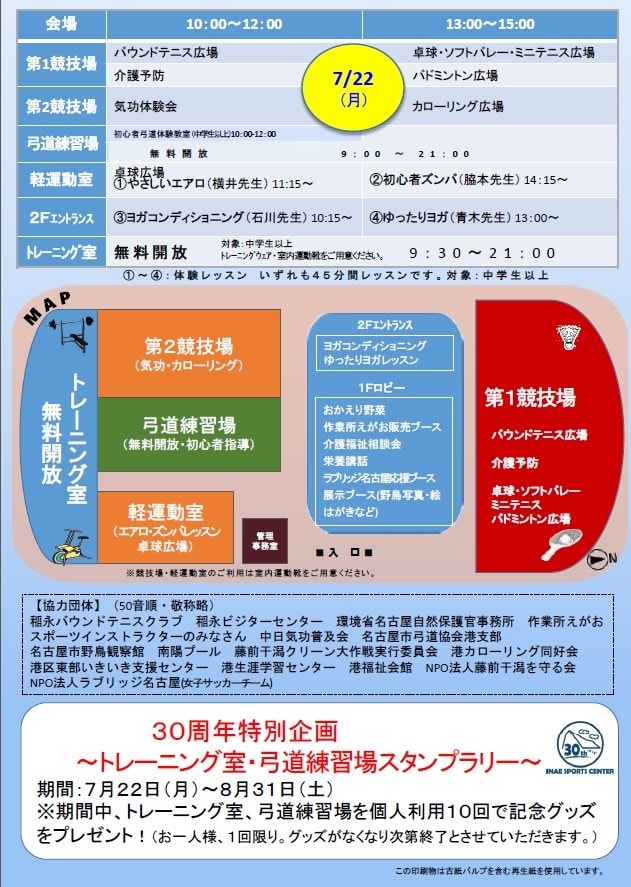藤前干潟
今日の満潮時間 7時04分 潮位142cm
今日の干潮時間12時29分 潮位179cm
1月17日(金)〜19日(日)に名古屋市が行った令和6年度国内湿地交流事業の派遣に同行してきました。
今年度で4回目となる派遣ですが、今回の派遣先は日本一の干満差のある有明海でした。
有明海にある3つのラムサール条約登録湿地と、藤前干潟の保全に影響を与えたと言われている諫早干拓地を訪れました。
初日は佐賀県鹿島市にある肥前鹿島干潟へ。藤前干潟と同じラムサール条約に登録された干潟です。

広がった干潟の野鳥観察をしてみると、たくさんのツクシガモやズグロカモメが。さらにはクロツラヘラサギも観察できました。

干潟が広がる向こうには海苔を育てている場所が見えました。

その後、鹿島市干潟交流館「なな海」の見学へ行きました。この施設の前はガタリンピックが行われる場所でもあります(ここはラムサール条約登録地ではありません)。

魚類などの干潟の生きもの展示が充実していました。

さらには、ラムサール条約推進室の職員さんから鹿島市の取組を紹介いただいたり、小学校で行っている授業を体験させてもらったりしました。

小学校で行っている干潟の泥の実験を体験しているところ↓。

その後、さらには佐賀県佐賀市の東よか干潟ビジターセンター「ひがさす」とオンラインでつないで、センター長と佐賀市環境政策課の職員さんから東よか干潟や佐賀市の取組についてお話いただきました。
佐賀県佐賀市にある東よか干潟もラムサール条約登録湿地で、シギチの聖地とも呼ばれる渡り鳥で有名な場所です。

2日目は長崎県諫早市へ行き、諫早干拓地を見学しました。
諫早湾はかつて広大な干潟が広がり、多くの干潟の生きものがすみ、渡り鳥が飛来する場所でしたが、干拓事業のため湾を締め切って農地などになりました。
この諫早湾の締め切り(潮受け堤防の締切り、ギロチンとも言われる)が行われたのは、1997年4月のこと。
この頃、名古屋市では藤前干潟にごみの処分場をつくるための埋め立て計画があり、それに対する反対運動が行われていました。
諫早湾が締め切られる光景は大きな衝撃を与え、藤前干潟の埋め立て反対運動が大きくなるきっかけになったと言われています。
その後、1999年1月に名古屋市は藤前干潟の埋め立て中止を決めました。
最初に訪れたのは広大な農地の先にあった諫早湾の前面堤防中央部公園。
堤防の前には草原が広がっており、干潟ではないものの、草原の野鳥をたくさん見ることができました。
また、諫早湾、さらには有明海の自然を守る活動をされている方から干拓地の現状などを聞くこともできました。

その後、諫早湾干拓堤防道路を走って、諫早湾干拓北部排水門を見学。

さらに諫早湾干拓堤防道路潮受け堤防展望所へ。
とても天気が良く穏やかな日で、水面には多くのカモが浮いているのが見えました。

展望所で海を背景に元漁師でタイラギという二枚貝を海に潜って獲っていた方からお話を伺いました。
かつての諫早湾がいかに豊かな海であったか、そして湾締め切り後の今は干潟の生きものは激減しているということでした。
特にタイラギは現在はほとんど生息していないそうです。
環境が悪くなっていることは今まで聞いたことがありましたが、改めてこんなに壊滅的なのかということにショックを受けました。

その後、複雑な気持ちを抱えたまま諫早干拓地を後にして、多比良港(長崎県雲仙市)から有明フェリーに乗り長洲港(熊本県長洲町)へ。
お天気がよく、水面は凪いでいました。参加者の中にはスナメリが見られた方もいました。

フェリーから下りた後は、熊本県荒尾市にある荒尾干潟の「荒尾干潟水鳥・湿地センター」へ。
荒尾干潟もラムサール条約登録湿地です。

館内見学後は、干潟で野鳥などを観察しました。
荒尾市の鳥であるシロチドリや、クロツラヘラサギ、ミサゴ、ズグロカモメなどを観察できました。

さらに、ハマヒバリが少し前から飛来していたそうで、センタースタッフの方の案内でハマヒバリも見ることができました。

その後、荒尾干潟のボランティアの方などと交流をしたりもしました。
荒尾干潟はアサリや海苔などで有名で、マジャク(アナジャコ)釣りなども行われています。
さらに、夕日スポットとしても知られています。

最終日の3日目は、佐賀県佐賀市の東よか干潟へ。
東よか干潟センター「ひがさす」を見学し、東よか干潟に生えるシチメンソウや干潟の生きものについて学びました。

その後、東よか干潟のボランティアの方などと交流。
諫早湾の締め切り後、干潟の渡り鳥であるシギ・チドリの国内最大級の飛来地となり、今やシギチの聖地と呼ばれる東よか干潟ですが、干潟の生きものも渡り鳥も減っているとのことでした。

最後に干潟で野鳥観察なども行いました。

ツクシガモやズグロカモメ、シギ・チドリなどを観察できました。

シチメンソウの芽↓。シチメンソウも減っており、種をまいたりする保全活動が行われています。
ですが、秋には赤く紅葉したシチメンソウを見に、とても多くの人が訪れるそうです。

今回訪れた有明海は藤前干潟と比べ物にならないくらい大きな干潟が広がり、渡り鳥などの生きものが多く、ムツゴロウやワラスボなど特徴的な生きものがいて、干潟や海の幸が豊かで、私にとってはとてもうらやましい場所なのですが、どこの訪問先でも有明海の環境が悪くなり、生きものが少なくなっており危機感を感じているというお話が聞かれたのは驚きでしたし衝撃でした。
藤前干潟は市民などの努力によって埋め立てから守られ、ラムサール条約に登録されて20 年以上が経ちました。
普及啓発やごみ清掃活動などが盛んに行われてきていますが、渡り鳥の減少や干潟環境の変化、訪れる小学生の減少、歴史を知る人の減少、活動に関わる人の高齢化などの課題があります。
訪れた有明海の3つのラムサール条約登録湿地が抱える課題と共通する課題もありました。
また、ずっと訪れたかった諫早干拓地に個人的には初めて訪れ、現地の方のお話を聞いたことが最も印象に残りましたが、様々な気持ちが湧いてきて、今もうまくまとめられないくらいです。
しかし、生きものが豊かだった干潟がなくなってしまったことは、ただただ悲しいと思います。
今回の湿地交流事業の参加者のほとんどの方は、すでに藤前干潟でガイドや生物調査、環境教育などに関わる活動をしている方で、どこの訪問先でも興味津々で見学をしていましたし、今回得られた学びや体験を藤前干潟でどのように生かせるかを話し合っている姿も見られました。
今後、この経験を藤前干潟の活動に生かしていってもらえると良いと思っています。
今日藤前干潟で観察できた主な野鳥 ハジロカイツブリ8、カムリカイツブリ114、カワウ1,150、ダイサギ1、アオサギ5、ヘラサギ1、マガモ35、カルガモ48、オカヨシガモ6、ヒドリガモ2、トモエガモ55、オナガガモ1,167、キンクロハジロ2、スズガモ660、ミサゴ9、トビ2、シロチドリ4、ダイゼン47、ハマシギ658、コアオアシシギ3、イソシギ1、ダイシャクシギ2、ユリカモメ4、セグロカモメ16、カモメ5、ズグロカモメ37
キジバト、カワラヒワ、ジョウビタキ、メジロ、ウグイス、ヒヨドリ、ハクセキレイ、ハシボソガラス
明日の干潮時間 8時56分 潮位142cm
明日の満潮時間14時00分 潮位179cm