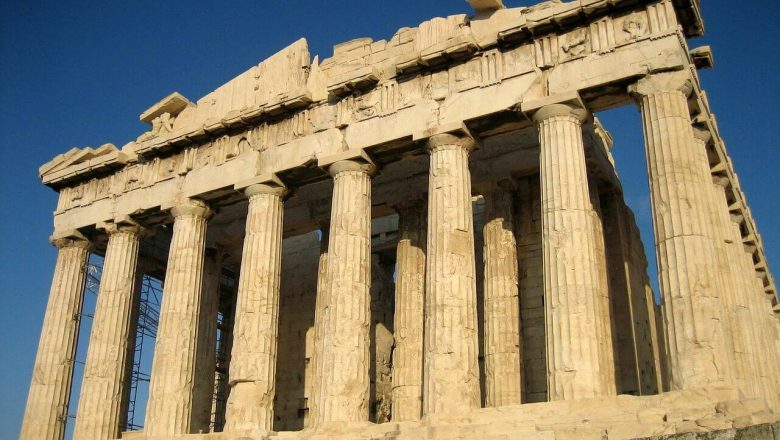2018/4/8 使徒の働き二〇章17-38節「与える幸いの御国」
現在の日曜休みのカレンダーはキリストの復活を祝うことから始まりました。使徒20章7節は教会が
「週の初めの日」
に集まっていた最初の記録です。この章は、エペソ教会の育成や三回の伝道旅行という大きな流れが落ち着き、「使徒」の新しい段階に進んでいく転換点です。
1.長老たちへの決別説教
読んで戴いた17節から35節は、パウロがエペソ教会の長老たちに語った説教です。港町ミレトで40km離れたエペソまで、わざわざ使いを出し、そこに来てもらって語ったという大事な説教です。三年間、手塩に掛け、また様々な困難がありながら過ごしてきた格別に思い入れのあるエペソ教会への熱い説教です。その説教の要点だけを今日はお話しします。
パウロはエペソでの戦いの日々を回想して思い起こさせ、今これからエルサレムへ向かう先にも危険が待ち構えていると覚悟していることを話しています。もう二度とあなたがたの顔を見ることはないだろうとさえ言います。27節では
「私は神のご計画のすべてを、余すところなくあなたがたに知らせたからです」
と自分の果たした責任を確認します。牧師はここから、神のご計画の全体像を知らせる務めを教えられます。そして、
「28あなたがたは自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなたがたを群れの監督にお立てになったのです。」
と言われます。
今も
「凶暴な狼」(29節)
と言われるような様々な圧力や暴力が外から教会に入ってくるかも知れません。いや、
「あなたがた自身の中からも」
と言われるように、自分自身が
「曲がったことを語って、弟子たちを自分のほうに引き込もうとする者」
になりかねません。そういう危うさがあることをまずリーダーが自戒して謙るよう言われるのです。自分自身に気を配るとはそういう事です。教会は、神のご計画のすべてを知らされて、神の御国、恵みの福音を伝えられ、それを宣べ伝えていく集まりです。しかし御国の福音が頭だけになり、神の国より自分の国を造り上げ、人を引き込もう、コントロールしよう、となり易いものです。だから、私たちは御言葉に聴いて、神の恵みに立ち帰りながら、その恵みに生きるよう自分に気を配る必要があるのです。その鍵となるのが、33節から35節で結ばれているパウロの生き方そのもののメッセージです。主イエスご自身が
「受けるよりも与えるほうが幸いである」
と言われた御言葉です。
2.「受けるよりも与えるほうが幸い」
実はイエスが
「受けるよりも与えるほうが幸い」
と仰った記録は福音書にはありません[1]。勿論イエスが仰った言葉は福音書にも世界中の書物にも書ききれないぐらい多くあったのですから[2]、書かれていないけれども本当にイエスがこう仰った可能性もあるでしょう。しかしそれよりは、イエスの教えの要約、いいえ、イエスのなさったこと、イエスというお方丸ごとが
「受けるよりも与えるほうが幸い」
というメッセージだった、とパウロは言っていると考えた方が、筋が通ります。神御自身が「与える」方、惜しみない恵みの方でした。労苦して弱い者を助けるお方でした。28節に
「神がご自分の血をもって買い取られた神の教会」
という言葉があります。
「神がご自分の血」
というのは不思議な言い回しです。神には血も体もありませんから、おかしな表現です。この「ご自分の」はとても強い愛着や近さを表す言葉です。
「私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神」
も同じ語です[3]。神が愛するご自分の御子ですから、御子の血は神にとって「ご自分の血」なのです。そのご自分の血、愛する御子の命さえ惜しまないで私たちを買い取って教会としてくださった。その驚くべき恵みが福音です。神の御国です。その王である神は、偉そうに力尽くで治めて、私たちの奉仕や献身や犠牲を求めるお方ではなく、礼拝を受けるよりも恵みを与えることを幸いとし、喜びとなさる王です。神のご計画の全体像とは、その恵みが土台であり、恵みによって私たちを建て上げ、恵みの心で生きる者として成長させてくれます。
その実例がパウロでした。パウロ自身が、受けるよりも与える人、仕える人でした。エペソでの彼の生活そのものが福音の見本でした。そして今も、エルサレムに行くのはアジアやアカイア諸教会の献金を届けるためでした。危険や困難があっても、エルサレムの貧しい教会に献金を届ける事で、異邦人教会とエルサレム教会とを橋渡ししたいと願ってやまないからでした。パウロは言葉だけで「神の恵みの福音を証しする任務」を果たしたとか、教会の伝道のために労苦を惜しまなかったのではなくて、労苦して弱い者を助けること、主イエスご自身をその全生活で証しするものでした。
それは
「御国の福音」
とは別の話でしょうか。恵みの神の
「ご計画」
とは、必ず私たちに御国を継がせるから幸いな計画なのでしょうか。神の御国が
「受けるよりも与えるほうが幸い」
で満ちた御国なのです。神の国の「憲法」は
「神があなたがたを愛されたようにあなたがたも互いに愛し合いなさい」。
言い換えれば
「受けるよりも与えるほうが幸い」
なのです。御国に入るとは、今ここでの私たちの生活、考えが、神がご自分の血をもって買い取ってくださった恵みに根差して、感謝し、与え、分かち合い、その幸いに生かされるようになる事です。
3.「受け身」から「与える」へ
しかしこの言葉もとても誤解され、手垢がたっぷり付いている文句です。「もらい下手」な方はこの言葉でますます受けることが苦手になるでしょう。自分の優位を保ちたい、借りを作りたくなくて与える人もあります。形の上で与えるのが実は自分をガードする壁なのです。中には「ボロボロになっても与えるのが愛だ、キリスト者の使命だ」という痛々しい誤解もあります。人から求められたら何でも拒まない、本当は嫌なのに与えなきゃ悪い気がして、相手の期待に応えないと苦しくて反射的に与えてしまう…。でもそれは「与える」の逆の「受け身」ですね。
イエスは「受け身になれ」でなく、主体的で心から与える幸いを示されました。内心で相手を裁きながら何かを与えるより、喜んで出来るまで待っても良いし、時には相手への愛や尊敬を込めて、正直に「ノー」を伝えるのがイエスの示された「与える」かもしれません。
それにはまず
「自分自身と群れの全体に気を配りなさい」。
自分の状態を十分にケアすることが必要です。自分を後回しにせず、主が私にすべての善い物を与えて、御自身の血を流すほどの愛で私たちを愛してくださった恵みを、十分に味わい、戴く事です。主は「受けるよりも与えなさい。惜しまずに与えよ」と命令されたのでなく
「受けるよりも与えるほうが幸いです」
と「幸い」を語るのです。いいえ、私たちに御自身の命を惜しまず与えて、私たちを愛し罪を赦し、命を下さる御自身に立ち戻らせてくださいました。私たちを、幸せを求めて物にしがみついたり人と比べたりする生き方から、本当に幸いな生き方、神の恵みの御国へと移してくださいました。だから私たちは、もう失うことを恐れないし、逆に批判されたくなくて与えよう、出しゃばるまいと受け身になるのではなく、自分で考えて出来る事を喜んで与えるのです。幸せを見失ったり、実際に貧しかったり助けが必要だったりする世界だからこそ、その中で自分に出来る事を僅かでもするのです。道徳としてでなく、心から与えるのです。すると、もらうことも、遠慮したり躊躇する必要はなくて、喜んで受け取る「もらい上手」になれるでしょう。
恵みの神は、ご自分が惜しみなく与える方だからこそ、与え合い、受け取り合う世界を作られたし、その幸いの中に私たちを置かれ、成長させてくださいます。言い換えれば、私たち自身が贈り物なのです。自分の人生や働きや労苦、存在そのものをこの世界への贈り物として受け取らせていただくのです。まず神が私たちに下さった恵み、神のものとされた幸いを十分に受けて、御言葉から感謝の心を養われましょう。与える幸いにも受ける幸いにも成長させていただきましょう。そんな姿こそ、世界に希望の泉を湧き上がらせる御国の証しになるのです。
「恵み溢れる神。あなたが御自身の血をもって私たちを買い取り、幸いな御国の民として下さいました。まだ無い物を数え、受ける事にも苦手な私たちも、あなたの測り知れない恵みに支えられてあることを感謝し、御名を賛美します。どうぞ私たちを受け身の生き方から救い出し、幸いを喜び、ともに祝い、主の恵みを言葉と生き方と働きで証しする教会とならせてください」
[1] 似た言葉として、マタイ十8「病人を癒やし、死人を生き返らせ、ツァラアトに冒された者をきよめ、悪霊どもを追い出しなさい。あなたがたはただで受けたのですから、ただで与えなさい」が挙げられます。しかし、これは「受けるよりも与える方が幸いである」とは、通底してはいても、飛躍のある言葉です。
[2] ヨハネの福音書二一25「イエスが行われたことは、ほかにもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと、私は思う。」
[3] ローマ八32「私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして、御子とともにすべてのものを、私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。」