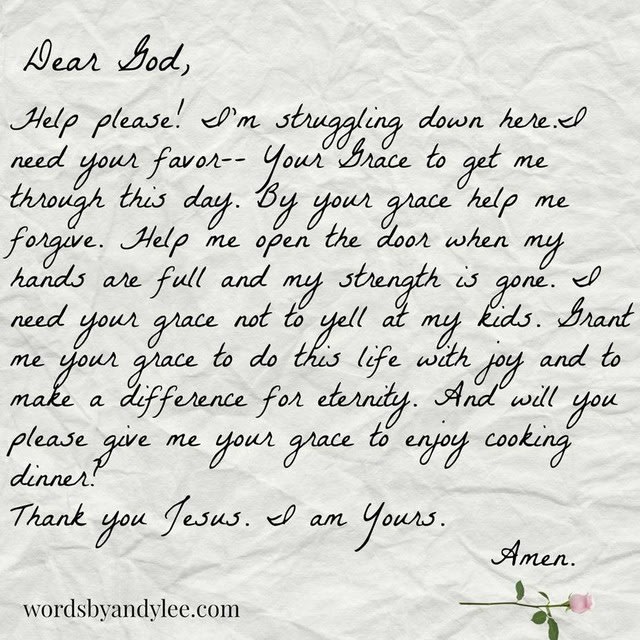2018/7/8 使徒の働き二七章27-44節「嵐の中をくぐり抜け」[1]
1.二転三転
嵐で二週間漂流して、最後の夜から翌日の上陸までの一日が、今日の出来事です。直前の26節でパウロが
「私たちは必ず、どこかの島に打ち上げられます」
と言ったとおりになります。けれど船を操る水夫たちも、パウロを護送するローマ兵たちも、パウロの言葉を信じたわけではないし、パウロに一目置くようになっていたわけでもありません。もうパウロが信頼されていたと勘違いしそうになりますが、まだです。水夫たちはベテランの感覚で陸地が近いと気づいて水深から確かめました。ところがそれなら自分たちだけ助かろうと、錨を降ろすように見せかけて小舟を海に降ろすのですね。これに気づいてパウロが注意を促すと、兵士たちは早合点して、小舟の綱を断ち切って避難の手段を失ってしまいます。この兵士たちもパウロを信頼したわけではなくてピリピリしています。42節では、囚人達が逃げないよう殺してしまおうと計ります。最後まで「パウロの言う通り助かった」と思った様子はありません。まだ不安や疑心が渦巻く中で一喜一憂が続きます。陸地が近いらしいと喜んだり、朝まで待ったり、朝になって見たらどこの陸地かよく分からず、砂浜のある入り江が見えて、錨も舵の綱も切って船を軽くし、帆を上げて風に乗って進む。すると見えない浅瀬に座礁して船首がめり込み、船尾が壊されるほど激しい波に打たれる。最後は、泳げる者は泳ぎ、泳げない者は何かに捕まって、もう本当に二転三転、船も気持ちも浮き沈みを繰り返しての上陸だったのです。
私は泳げないカナヅチですから、この場にいたら最後まで生きた心地がしなかったでしょう。パウロの言葉があっても、いいえ直接主が幻で現れて、
「恐れることはありません」
と言ってくださったとしても、それでも次々に起きる困難に、意気消沈したり怖じ気づいたり、泣き喚いたかもしれません。主がともにいてくださるとは、すべて順調でスムーズに行くことではありませんね。まさに下が見えない海の船旅です。浅いのか深いのか。凪かと思えば嵐になり、遠くまで運ばれて、そう旅立った人が二度と帰ってこない。聖書で海は恐怖や死と結びつけられていて、黙示録には
「新しい天と新しい地」
には
「海がない」
と言われるぐらいです。(ヨハネの黙示録二一章一節)そういう「海」の旅路を、翻弄されつつ、色々な出来事や嵐の中でも主はともにおられて歩み続けるのです。
それは「人間の努力が無意味だ」ということではありません。パニック映画には、祈るだけで何もしない信心深い人たちが出て来ますが[2]、パウロは「天命を信じて人事を尽くす」人でした。水夫たちの働き、経験値や役割を認めています。水夫が逃げようとするのを放っては置かず、「助かるためには彼らが必要だ」と逃がさせない。現実的なパウロの姿が印象的です。
2.パンを裂き
何よりもパウロの行動は、食事を勧めたことですね。嵐で絶望して食欲も失せていたのか、取っておいたのか。十四日丸々絶食していたかはともかく、腹ぺこでは上陸出来ません。パウロが食事を勧め、自分からパンを取って、神に感謝の祈りをささげて、裂いてパクパク食べ始めた。その姿に
「36それで皆も元気づけられ、食事をした。」
のです。22節でも25節でもパウロは
「元気を出しなさい」
と言っていました。その言葉がやっと今パウロの食事の姿を通して、届いたのです。ここでパウロがパンを取り、感謝の祈りをささげて、裂いて、食べた、というのは明らかに聖餐式を思わせます。教会の礼拝で、パンを取り裂いてキリストが十字架で裂かれた体を覚える、あの聖餐式と同じ言葉遣いです。とはいえぶどう酒はなかったのですし、パウロは一人で食べ始めていますから「聖餐式を行った」のではないでしょう。それでも聖餐式を思わせます。主がご自分のいのちを献げて、苦しみの死をもってしてまで、私たちに救いを下さいました。キリストの十字架を思う時、私たちは希望を持つことが出来ます。パンを裂く時、私たちはキリストによって、一つとされていることをありありと味わいます。聖餐式ではなくとも、パウロが嵐の中で、希望をもってみんなに食事を勧めて、神への感謝を祈りつつパンを裂き、飄々とムシャムシャ食べている姿は、確かに皆を元気づけました。私たちも嵐の中でもパンを食べ、キリストからの命を味わって証しをするのです。
この時パウロは34節で
「あなたがたは助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません」
と言います。これはイエスも使われた「失うことは何もない」という強調表現です。文字通りとは思いません。人は何がなくても、毎日50本から100本の髪の毛が抜けるそうです。それ以上に、積み荷は失い、船も失い、手荷物も持ち出せなかった。こういう状態は「何もかも失った」と言わないでしょうか? 「髪の毛一本失われない」よりも荷物を、自分の財産、地位、人生を返してくれ、と言われるとは思わなかったのでしょうか。
ここに大事なポイントがあります。荷物も船も、髪の毛と同じくいずれは必ず失われます。私たちの持ち物や仕事、立場や生活スタイル、健康や人間関係、多くのものは脆いものなのです。私たちはそれを失った時に愕然として、「どうして?」と不公平な目にあったように思ったり、神は意地悪だと腹を立てたりしますが、神が「失われることはない」と仰ったのは、そういう人間の期待とは違う意味でした。イエスは
「人があり余るほど持っていても、その人のいのちは財産にあるのではない」[3]
と仰いました。それは、積み荷より何より大事な体験です。
3.全員が無事に
船長たちは積み荷や商売の事に目が眩んで、無謀にも嵐の中に船出してしまいました。結局そのために、積み荷も船も海の藻屑にしてしまいました。最後には、全員のいのちだけが助かりました。嵐の中をくぐり抜けて、いのちだけが助かり、他のものはすべて失ったようでした。でもその人に対してパウロは言うのです。「髪の毛一本も失われなかったね。よかったねぇ~」と。「生きてくれて良かった。助かってくれて良かった。あなたがいるだけで良かった。失ったと言わなきゃならないものなんて何もない」。それは何と有り難いことでしょう[4]。
先にパウロはコリント人への手紙で、人生を建物に例えてこう書いていました。
「だれかの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。」[5]
木や草や藁、焼けてなくなるようなものを頼みとして生きてきて、最後は全部を失ってしまうこともある。なくなるものを頼みにしてきて、最後に全部を失うことはひどい損害です。でも、「だからその人もダメだ」ではなくて、
「その人自身は火の中をくぐるようにして助かります」。
人生を無駄にしたとしても神はその私たちを受け入れてくださる。喜んで迎えてくださるのが神です。パウロはそういう言葉を語っています。そして、この最後で、人々が上陸したことを
「こうして全員が無事に陸に着いた」
と言い切っていますね。
自分さえ助かればと小舟に乗ろうとした水夫もいました。兵士たちは、保身のため囚人達を殺そうとしました。でも、そういう企みも、船や積み荷ごと神は引っ繰り返されました。人の命よりも物や面子を重んじてしまうような生き方を神は引っ繰り返されます。私たちも、失うようなものを全部失って、嵐の中をくぐり抜けた時、「あの時、あんなことさえしなければ」とか「積み荷も船も失った」と損を数え上げたり、失敗を非難し合ったりするのでしょうか。いいえ、何もかも失ったようでも、「あなたが無事で善かった、命が助かったのだから、何も失わなかった」と言えるなんて素晴らしいことではないでしょうか。この神との出会いが、今ここでの私たちの生き方も変え始めています[6]。私たちの命を喜ばれる神の視点によって、今ここで、嵐の中でも神に感謝を献げ、パンを分け合う場が教会です。嵐の中、一喜一憂する中、パウロのように「元気を出そう」と励まし、助け合うように変えられましょう。浮き沈みの絶えない世界だからこそ、お互いの無事を喜び、神に感謝していく。そのための教会です。
「主よ。外に嵐がある中、今日も私たちはここであなたの善き力に信頼をし、感謝と希望を確かめています。パンを裂き、主の恵みを分かち合っています。嵐や困難に揉まれ、最後には死をくぐって、何も持って行くことは出来ませんが、失ったと言えるものは何一つないと言えるゴールがあります。その途上で、どうぞ助け合い励まし合う歩みを今週も育てさせてください」
[1] 「使徒の働き」を一章ずつ読んで来ましたが、最後の二七、二八章はじっくりと二回ずつ読みたいと思いました。今日は二七章の後半、嵐にあって船が流され絶望した状況から、陸地に辿り着いて、最後は全員が助かるという顛末です。リアルな映画で観たいシーンです。
[2] 「タイタニック」「ポセイドンアドベンチャー」など。「神が守ってくださるのだから」と無理をするか何もしないか、どっちか極端になりがちです。
[3] ルカ十二15「そして人々に言われた。「どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人のいのちは財産にあるのではないからです。」
[4] ルカ二一18にも「しかし、あなたがたの髪の毛一本も失われることはありません。」とイエスが同じ言葉を仰っていますが、その前後関係は「10「それから、イエスは彼らに言われた。「民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、11大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きなしるしが現れます。12しかし、これらのことすべてが起こる前に、人々はあなたがたに手をかけて迫害し、会堂や牢に引き渡し、わたしの名のために、あなたがたを王たちや総督たちの前に引き出します。13それは、あなたがたにとって証しをする機会となります。14ですから、どう弁明するかは、あらかじめ考えない、と心に決めておきなさい。15あなたがたに反対するどんな人も、対抗したり反論したりできないことばと知恵を、わたしが与えるからです。16あなたがたは、両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。17また、わたしの名のために、すべての人に憎まれます。18しかし、あなたがたの髪の毛一本も失われることはありません。19あなたがたは、忍耐することによって自分のいのちを勝ち取りなさい。」という迫害の文脈です。
[5] Ⅰコリント十13。
[6] この経験は、船や積み荷は失う、という知恵をもたらしてくれました。また、自分だけ助かればいい、という水夫たちのような個人主義でもないし、集団として助かるためには囚人は殺して逃がさないという兵士たちのような全体主義でもないことを学ぶ経験でもありました。それぞれが協力し合いつつ、全員を生かすようなあり方へと導かれて行く物語です。