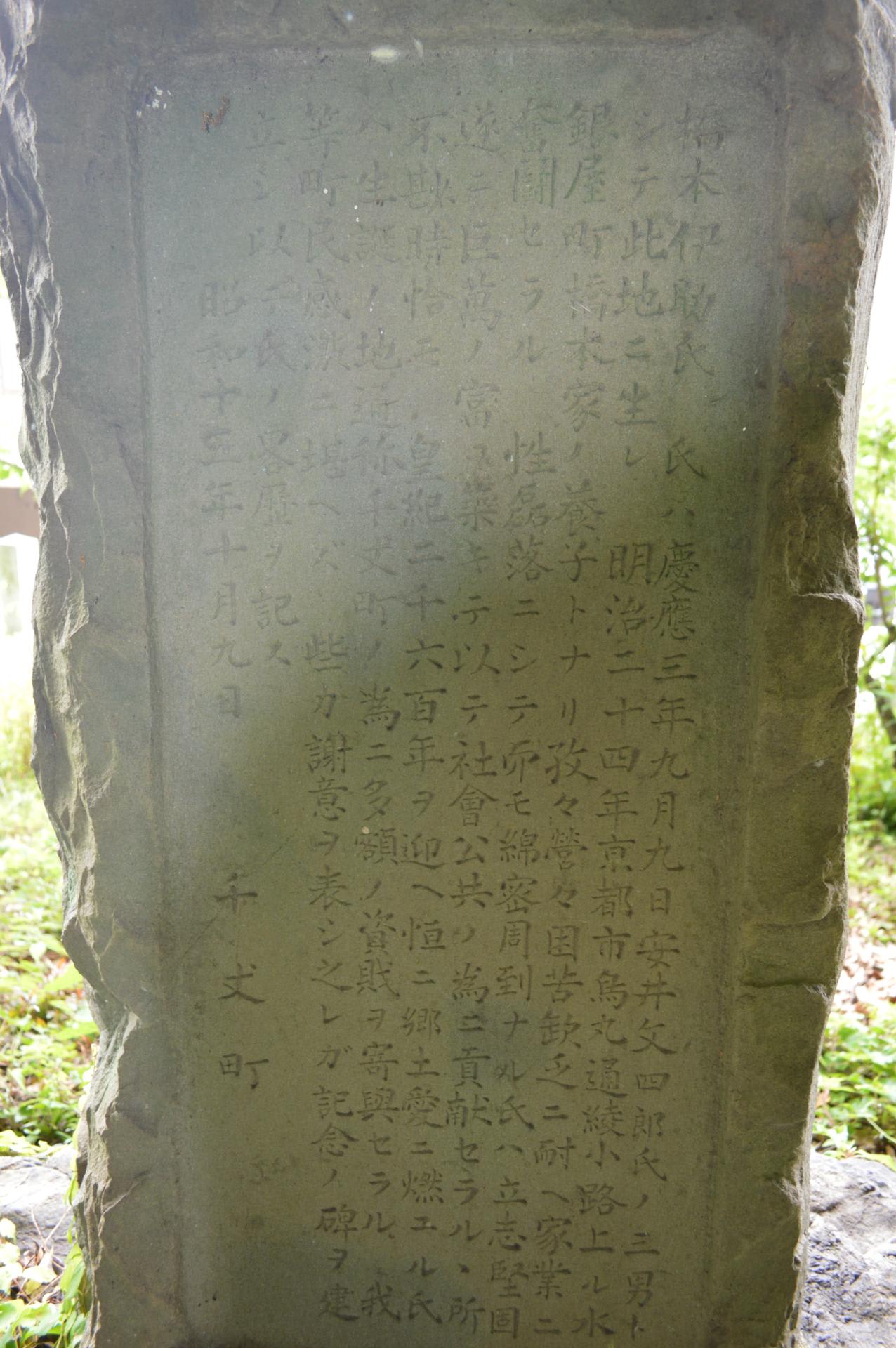勝持寺(花の寺)
小塩山と号する天台宗の寺、境内に桜の木が多いので「花の寺」といわれている。
創建は、寺伝によると白鳳8年(680)天武天皇の勅により、役小角が創建した。その後、伝教大師最澄が比叡山の坤(西南)のこの地に霊感を感じ、薬師如来を安置し、
天台の道場とした。
はじめは小塩山大原寺と号したが、仁寿年間(851~54)仏陀上人(千観僧都)が文徳天皇の帰依を得て伽藍を再興し、名も大原院勝持寺と改め、大原野神社の別当寺とした。
足利尊氏は六波羅攻略にあたってたまたま当寺に立ち寄り、時の住僧から「勝持」としるした旗竿を献じられ、足利氏の庇護を得て、寺は隆盛した。
寺宝に足利将軍の古文書が多い。
応仁の乱で境内は荒廃した。天正11年(1583)青蓮院宮尊澄法親王は寺の再建をした。織田・豊臣も保護し、徳川桂昌院は崇仏の念あつく、堂宇の復興をした。
境内には西行手植えの桜があり、近江の守護大名佐々木道誉は花見をした。
細川幽斎も当寺で連歌を興行した。その時の懐紙が寺宝になっている。
仁王門の仁王像は京都市最古の仁王像とみられている。
弘安8年(1285)の銘がある。現在、収蔵庫に移されている。
西行桜、西行は世を捨ててのち当寺に入り、出家剃髪したといわれ、
その時に植えた桜と伝わる。
西行姿見の池・鏡石 鏡石は西行が剃髪に使ったものといわれています。





関連記事 ⇒ 京の通称寺 39ヶ寺
前回の 寺院の記事 ➡