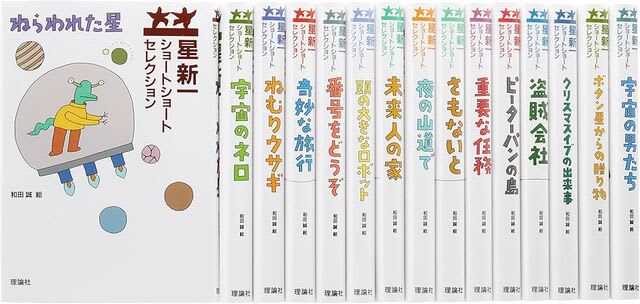2024 12月8日 (日曜日) ②
忘れていたが今日は”太平洋戦争”に突入した日。
生まれる前の事で・・本や映画・ニュースから知る歴史である。
伯父や父親からの話も何回か聞いている。
実践の現場の惨状は阿鼻叫喚の世界で酷いものであったと聞く。
そんな中
夕刊のコラムにあった!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NHKの連続テレビ小説「虎に翼」でも取り上げられた
戦前の首相直属機関「総力戦研究所」が、
米国と戦争した場合の分析を内閣に報告したのは1941年8月末だった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲当時の軍部や官僚らの中堅・若手精鋭がデータを基に進めた。
シミュレーション結果は
「日本必敗」。戦争が長期化し、最後はソ連参戦で行き詰まることまで予測した。
🔵だが、東条英機陸相は「机上の演習と実戦は異なる」と退け。口外を禁じたという。「昭和16年夏の敗戦」(猪瀬直樹著)に詳しい。
しかし天皇は東条を認めていたという・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲報告から3カ月余を経た12月8日、日本は太平洋戦争に突入する。
長引く日中戦争に閉塞(へいそく)感が漂う中での
米英への宣戦布告に社会は快哉(かいさい)を叫び、熱狂した。
総力戦研究所は、政府が自国を客観視できた最後の場だったのかもしれない。
~~~~~~~~~~~~~~
▲来年は戦後80年にあたる。
「8・15」への道は「12・8」で固まった。
〇冷静な議論が通用しない空気がなぜ、形作られていったのか。
ネット時代を迎えたメディアこそ重く受け止めるべき日でもある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲作家、太宰治は短編「十二月八日」で開戦当日を
「日本も、けさから、ちがう日本になったのだ」と記した。
高揚した記述が目立つ他の作家たちに比べ、
ユーモアで不安を包み隠したような作品である
「ちがう日本」に後戻りの道はなかった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲ウクライナやガザ地区で戦闘や攻撃が続く。
戦いがいったん始まれば、止めることがいかに難しいか。
戦争を始めても、始めさせてもならない。
そのために何が必要か
戒めが重みを増す「開戦の日」だ。
========================
★赤字をクリックしてみてください。
太平洋戦争 なぜ開戦したの?


🔵メモ

「昭和16年夏の敗戦」 猪瀬直樹著 中央公論新社
◇昭和16年とは、日米開戦の年です。その年の12月8日に真珠湾攻撃が実行されるわけですが、
その8ヶ月前の4月に各省庁のエリート官僚のほか、陸軍、海軍、さらには民間企業から総勢30名ほどの30代を中心とする精鋭を集めて総力戦研究所が設立されました。
◇彼らは模擬内閣を組織し、机上演習により総力戦のシミュレーションを行います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その結果は、「日米戦日本必敗」でした。
「緒戦は優勢ながら、
徐々に国力の差が顕在化、
やがてソ連が参戦し、
開戦三~四年で日本は敗れる」
となりました。
彼らのシミュレーションの結果は、驚くほど正確で、彼らの予想通り、
戦争継続の絶対条件であったインドネシアの石油は、
輸送中にその多くが撃沈され、
結局必要量が日本に届くことはありませんでした。
その撃沈率も、実際の戦争における撃沈率とほとんど差がないという正確さでした。
◇そうした優れた研究結果が、8月27日28日の両日総理官邸で発表されるわけですが、
その席上、当時陸軍大臣だった東條英機が、総力戦研究所の研究結果を「机上の演習である」とし、
日露戦争の例を挙げ、「勝てると思わなかったのに勝ったのであり、
戦争は計画通りにいかない」ことを理由に黙殺してしまいます。
そして、東條は、日米開戦時の総理大臣となります。
◇もし、東條が総力戦研究所の研究結果を重要視していたら・・と思ってしまいます。
著者の猪瀬氏は、東條英機は、独裁者ではなく気の小さな真面目な官僚だったと記していますが、 その通りだったのでしょう。ただ、その真面目さは、どこを向いていたのだろうと、
考えてしまいます。あれだけ天皇を崇拝し、
天皇の非戦の意思を理解しながら、
なぜ日米開戦に踏み切ってしまったのでしょう?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇結局、彼は、軍という自分の属するグループという視点からしか世界を見ることができず、
俯瞰的な視点を持てなかったのかもしれません。
陸軍には、膠着する日中戦争から手を引くなどということはできないという空気があり、
海軍の中にはアメリカと戦ったら勝てないという予測がありながら、
自分たちからそれを言い出すわけにはいかないという空気がありました。
真面目な東條、そして当時の大臣たちは、その空気に従うことを選んだのでしょう。
その真面目さが、なぜ、空気に逆らっても「国民を守る」という方向に行かなかったのか、
なぜ、そうした発想を思いつかなかったのか・・・、そこはナゾです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇総力戦研究所のシミュレーション結果という論理がありながら、
それよりも身内の空気が勝ってしまったのです。
論理より空気が勝つという傾向は、今でも日本に強くあり、
近年それがますます強くなってきているように感じます。
失敗から学ばなければいけませんね。
=============================
★この日本、80年間も平和が続いているなんて世界を見れば稀有なこと
平和ボケと言われても仕方ないか!
何が起こってもびっくりしないぞ!と思うが・もう自信はない。
忘れていたが今日は”太平洋戦争”に突入した日。

生まれる前の事で・・本や映画・ニュースから知る歴史である。
伯父や父親からの話も何回か聞いている。
実践の現場の惨状は阿鼻叫喚の世界で酷いものであったと聞く。
そんな中
夕刊のコラムにあった!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NHKの連続テレビ小説「虎に翼」でも取り上げられた
戦前の首相直属機関「総力戦研究所」が、
米国と戦争した場合の分析を内閣に報告したのは1941年8月末だった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲当時の軍部や官僚らの中堅・若手精鋭がデータを基に進めた。
シミュレーション結果は
「日本必敗」。戦争が長期化し、最後はソ連参戦で行き詰まることまで予測した。

🔵だが、東条英機陸相は「机上の演習と実戦は異なる」と退け。口外を禁じたという。「昭和16年夏の敗戦」(猪瀬直樹著)に詳しい。
しかし天皇は東条を認めていたという・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲報告から3カ月余を経た12月8日、日本は太平洋戦争に突入する。
長引く日中戦争に閉塞(へいそく)感が漂う中での
米英への宣戦布告に社会は快哉(かいさい)を叫び、熱狂した。
総力戦研究所は、政府が自国を客観視できた最後の場だったのかもしれない。
~~~~~~~~~~~~~~
▲来年は戦後80年にあたる。
「8・15」への道は「12・8」で固まった。
〇冷静な議論が通用しない空気がなぜ、形作られていったのか。
ネット時代を迎えたメディアこそ重く受け止めるべき日でもある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲作家、太宰治は短編「十二月八日」で開戦当日を
「日本も、けさから、ちがう日本になったのだ」と記した。
高揚した記述が目立つ他の作家たちに比べ、
ユーモアで不安を包み隠したような作品である
「ちがう日本」に後戻りの道はなかった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲ウクライナやガザ地区で戦闘や攻撃が続く。
戦いがいったん始まれば、止めることがいかに難しいか。
戦争を始めても、始めさせてもならない。
そのために何が必要か
戒めが重みを増す「開戦の日」だ。
========================
★赤字をクリックしてみてください。
太平洋戦争 なぜ開戦したの?


🔵メモ

「昭和16年夏の敗戦」 猪瀬直樹著 中央公論新社
◇昭和16年とは、日米開戦の年です。その年の12月8日に真珠湾攻撃が実行されるわけですが、
その8ヶ月前の4月に各省庁のエリート官僚のほか、陸軍、海軍、さらには民間企業から総勢30名ほどの30代を中心とする精鋭を集めて総力戦研究所が設立されました。
◇彼らは模擬内閣を組織し、机上演習により総力戦のシミュレーションを行います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その結果は、「日米戦日本必敗」でした。
「緒戦は優勢ながら、
徐々に国力の差が顕在化、
やがてソ連が参戦し、
開戦三~四年で日本は敗れる」
となりました。
彼らのシミュレーションの結果は、驚くほど正確で、彼らの予想通り、
戦争継続の絶対条件であったインドネシアの石油は、
輸送中にその多くが撃沈され、
結局必要量が日本に届くことはありませんでした。
その撃沈率も、実際の戦争における撃沈率とほとんど差がないという正確さでした。
◇そうした優れた研究結果が、8月27日28日の両日総理官邸で発表されるわけですが、
その席上、当時陸軍大臣だった東條英機が、総力戦研究所の研究結果を「机上の演習である」とし、
日露戦争の例を挙げ、「勝てると思わなかったのに勝ったのであり、
戦争は計画通りにいかない」ことを理由に黙殺してしまいます。
そして、東條は、日米開戦時の総理大臣となります。
◇もし、東條が総力戦研究所の研究結果を重要視していたら・・と思ってしまいます。
著者の猪瀬氏は、東條英機は、独裁者ではなく気の小さな真面目な官僚だったと記していますが、 その通りだったのでしょう。ただ、その真面目さは、どこを向いていたのだろうと、
考えてしまいます。あれだけ天皇を崇拝し、
天皇の非戦の意思を理解しながら、
なぜ日米開戦に踏み切ってしまったのでしょう?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇結局、彼は、軍という自分の属するグループという視点からしか世界を見ることができず、
俯瞰的な視点を持てなかったのかもしれません。
陸軍には、膠着する日中戦争から手を引くなどということはできないという空気があり、
海軍の中にはアメリカと戦ったら勝てないという予測がありながら、
自分たちからそれを言い出すわけにはいかないという空気がありました。
真面目な東條、そして当時の大臣たちは、その空気に従うことを選んだのでしょう。
その真面目さが、なぜ、空気に逆らっても「国民を守る」という方向に行かなかったのか、
なぜ、そうした発想を思いつかなかったのか・・・、そこはナゾです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇総力戦研究所のシミュレーション結果という論理がありながら、
それよりも身内の空気が勝ってしまったのです。
論理より空気が勝つという傾向は、今でも日本に強くあり、
近年それがますます強くなってきているように感じます。
失敗から学ばなければいけませんね。

=============================
★この日本、80年間も平和が続いているなんて世界を見れば稀有なこと
平和ボケと言われても仕方ないか!
何が起こってもびっくりしないぞ!と思うが・もう自信はない。