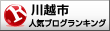「七曲り」とあり、文章と数枚の地図が表示されている。

解説文には次のように書かれている。
七曲(ななまが)り
川越城下の武家地は、城の近くに上級武士、離れるに
従って中・下級武士、街道筋には足軽屋敷が配置されて
いた。こうした構成は江戸時代を通じて変化はないが、
家臣団の規模により武家地の領域には変動があった。
(中 略)
この拡大範囲の道は非常に屈曲が多く、郷分町で
あった側は、通称「七曲り」と呼ばれるようになった。なお、
「七曲り」とは道が幾重にも折れ曲
がっている場所のことをいう。
ふたつの城下図から「七曲り」は、
江戸時代も後半になってつくられた
屈曲路であることが明らかであるが、
防衛上の目的でつくられたのか
どうか定かではない。『秋元但馬守様川越城主之頃図』では既に屋敷割
の原型がつくられており、松平大和守
家時代にはその屋敷割を踏襲する
かたちで武家地は拡大された。そし
て、この屋敷割に沿うとともに各
屋敷へ出入りを容易にするため
に道がつくられ、結果的に複雑な
屈曲路をかたちづくることになった
のであろう。「七曲り」は、武家地の
拡大という事実が生んだ道である
こと。そして、今に江戸時代の名残を
留める道であることは間違いない。
川越市教育委員会
右下の地図には、「七曲り」の道が黒く示されている。
この地図の東側は良く通るが、西側は最近歩いたことがない。
久しぶりに、行って見る事にした。

この角を最初の曲がり角としてスタートする。

七曲りは道路が曲がっているだけではない。
左にバケツが置いてあるが、その手前の縁石がはみ出している。
この様な場所が、この近くには非常に多い。

次の角の正面には、木の塀が2枚前後に並んでいる。
以前ここには、屋根付きの門があり良いか雰囲気を出していた。
家が解体されるとともに門も撤去された。
その後家は集合住宅にかわり、ここもポカンと空いていたが、いつ間にかこの塀が出来ていた。
左手の塀の先も奥にへこんでいる。

右手には新しい住宅があり、新しい道が出来ているが、その角は複雑に折れ曲がっている。

このすぐ先で丁字路になる。

そこから左手(東側)の道は緩い下り坂だが、縁石の凸凹がよく目立つ。

右手の七曲りの道は長い直線に見えるが、左手にやはり出っ張りがある。

少し先の角に「瘡守社」という小さな神社がある。

神社の脇から先も微妙に左右が凸凹している。

道は突き当りを右に曲がる。

曲がって少し先に次の角が見える。
右の赤レンガ状の塀と縁石の間には空地があり、砂利の上に鉄板が置かれている。

すぐ先で左折する。

そのすぐ先で右折する。
この辺の側溝は白く新しいのが目立つ。
右手の家は門の前は出っ張っているが、塀はそれよりも引っ込んでいる。

角を曲がるとやはり両側の側溝が新しい。
左側の家は塀も新しい。
ちょうど家の人が庭にいたので聞いてみると、門を新しくするときに引っ込めたのだと教えてくれた。

次の角が見える辺りでも凸凹が多い。

少し大きめの道路があり、七曲りはここで終わりである。
角に小さな鳥居と社があるが、そこも塀と縁石の間には砂利が敷かれている。
その先の道は中央郵便局へ通じているが、丁度道幅の分だけズレている。

道路を渡り反対側から見る。
当然だが、七曲りは一方通行である。

左手は一直線で、奥に永島家住宅の屋敷林の木が見える。

道の途中に古い2階建ての町家がある。
これは行き過ぎてから振り返って撮ったものである。
2階の全部と1階の半分は格子で覆われている。
1階の半分は白壁とガラス戸で、なにか商売をしているようだ。

2階の軒下に、この白い垂れ幕があった。
ちいさな字で「ちゃぶだい」と書かれている。

道の反対側には、赤レンガの門柱と塀があった。
前のブロック塀と較べると、高く、頑丈そうに見える。

少し先で永島家住宅の前に戻ってくる。
この前の道は七曲りに入って居ないが、七つの角を曲がると丁度一周することが出来る。

途中で見た神社の前は、細い坂道になっている。

坂の途中で、道は半分ほどの狭さになる。
右側の家の塀は、坂道からかなり奥に造られている。

坂道を下ると県道にでるが、向かいにくらづくり本舗のお店がある。

坂道を振り返るとかなり狭い道だが、ここを通る人は多い。
自転車とすれ違うことも良くある。

この坂道は説明板の七曲りに入っていないが、勝手に七曲りへの入口になっている。
うっかりすると通り過ぎてしまうが、くらづくり本舗を目印にすれば大丈夫である。