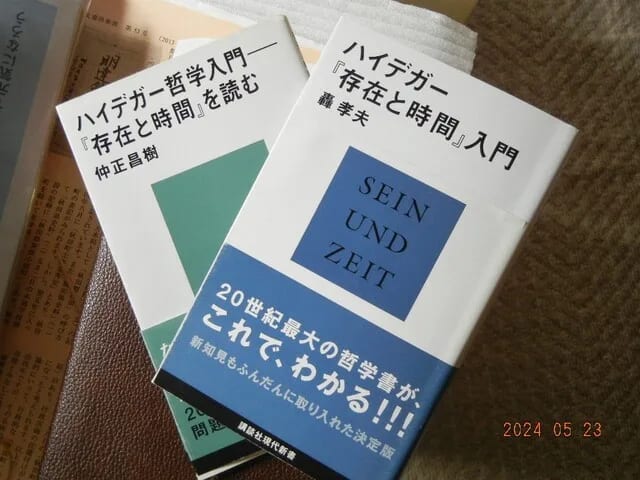天地創造来からという根を持つ思想は幸せだなぁ。人が生き続けるかぎり途絶えることがないだろうから。
勝手に解釈:キリスト教神学からハイデガーが書こうとした源泉をささやかに書いてみたい。源泉がすべて聖書から見てとれる。ところが宗教は、人の誕生時点から、思い込みのように命と一体となっているものなので、生き物である人の先入観からの脱色を図した言語を彼は用いる。ある時は言葉を改造して。
①神は天地を創造し、最後に完成品として人を造られて、7日目に休息された。この創造物のすべてのことに関する解明。
(旧約聖書:出エジプト記三章14節 神はモーセに、「わたしはある。わたしはあるという者だ」と言われた。)「私はあるというものだ」と。まさに『存在』することの何かである。
最終完成形と神の荷姿に創造された人は、すべての現象を言語化することによって、創造世界を理解することができるであろうし、自分を創造した神に近づくことができる。現に僕らの学校のあらゆる学びはそこに行き着くといってよい。
そこで神から離れた罪をもつものとなった人。”罪”を持つといわれる人。その人類の歴史。とりまくすべて、さらにそれも人のどこで、どう思考するのか?、自分という人は?、かかわる周囲の実態物は?、・・・等々。
②文系からではなく理系から追求したのがアインシュタインの『光』についての理論的解析。(旧約聖書:創世記第一章三節『神は言われた。「光あれ」こうして光があった。)光速は、場所によらず不変であること。相対性理論。僕らは光がなければ見て、何かと物体を理解することができない。
①をさらに細かく。神学において『罪』とは的外れ(まとはずれ)といわれる。本来、神の思いにつうづる的の中心を求める生き方でひとは創造されたが、それを彼は『本来性』と彼は語りたいのではないか。
周囲の的外れに生きている多くの大衆。まとの中心を着求めず生きる普段の人々。彼は『非本来性』と語る。むろん、説明であるので道徳性の是非はない。頽落と後者を言っているけれど。
『本来性』と『非本来性』という言葉は、本来性は創造の神の願いに沿った生き方をする、あるいは求めて生きいる人々で、非本来性は神を信じているが神の本心からはずれて、気にもせず生きる多くの大衆、それらを(ひと)と定義したい思いがあるようだ。
まずは、人の思いの『本来性』、『非本来性』という言葉は、そういうイメージを持つとわかりやすかもしれない。本来、堕罪しなければ、アダムは神とともに今も平安に住まうべきであった。しかし、罪を犯し、今も多くの大衆は、神を信じてはいるだろうが、本来のありようから外れ、非本来の姿で多くの大衆(ひと)として漂っている、ということである。
・・・つづく