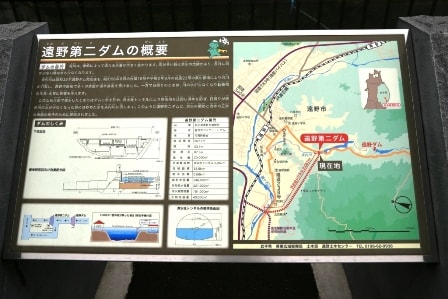2016年5月3日 衣川4号ダム(苗代沢ダム)
衣川4号ダムは岩手県奥州市衣川区国見の北上川水系三沢川にある農地防災目的のロックフィルダムです。
岩手県奥州市衣川区は胆沢川によって形成された扇状地の南縁にあたり、栗駒山の火山堆積物で形成された透水性が高い地質で、豪雨になると河川流量が急増し流域農耕地に多大な被害をもたらしてきました。
そこで農林省(現農水省)の補助を受けた岩手県の防災ダム事業により衣川水系の主要河川に5基の農地防災ダムが建設されました。
5基のダム群を総称して『衣川防災5ダム』と呼んでおり、1995年(平成10年)に5ダム最後のダムとして完成したのが衣川4号ダムでダム下流の地名を採って苗代沢ダムともよばれています。
管理は奥州市が受託しています。
下流から
洪水吐と取水口からの導水路が堤体下で合流しています。

堤体下流面。

上流面。

管理事務所
取水設備も兼ねています。

防災専用ダムのため水位は低くなっています。

天端は立入禁止。

洪水吐導流部と減勢工。

洪水吐。

他の衣川防災ダムと同様堤体は立ち入り禁止ですが、下流から見れるなど見学スポットは多くなっています。
追記
衣川4号ダムには農地防災容量が設定されていますが、治水協定により豪雨災害が予想される場合には事前放流により洪水調節容量が確保されることになりました。
0281 衣川4号ダム(苗代沢ダム)(0363)
岩手県奥州市衣川区国見
北上川水系三沢川
F
R
33メートル
135メートル
570千㎥/440千㎥
奥州市
1995年
◎治水協定が締結されたダム