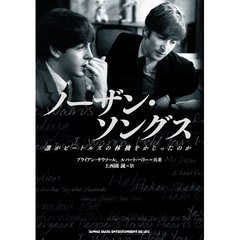<小林 「日本語ってむこうでつくられた音楽にのれないですよ。最近の若い人たちの発音が変わってきて、だいたい音楽にのれるようになってきたけど、昔の日本語、あるいはもともと日本語の性質というのはミュージカル・アクセントの言葉ですから音の高低で進行する。歌みたいな言葉で、ストレス・アクセントじゃない。
つまり、強弱で進行しないから、ロックやジャズのリズムにとてものりにくい言葉なんですよね。それをのせるという話法を糸居さんがつくったということ。
あと、それに関連するんですが、言葉の文体を変えちゃったということ。
ぼくの解釈ですけども、糸居さんが、『おはよう』といった時、もう『ございます』はカットしちゃう。一小節があったら一小節に『おはよう』をぶち込む。そのときの間で進行する。こんにちわ、おはよう、ドン、きょうはいい気分、ドン、みたいなそれでいっちゃう。
そういうふうなスタイルを糸居さんは日本でつくったということですね。ぼくとして、すごく尊敬してます。」
糸居 「人間はリズム人間とメロディー人間とありましてね。玉置さんのはやっぱりメロディー人間のやり方で、じつにうまく言葉をつないでいく。ぼくたちのはリズムで、わりあい切っちゃうことが多い。そういった意味では野球の実況放送なんかによく似ているところがありますね。というのは、話す文体をすぐおしまいにできるようにつねに考えながらやってるから。」(中略)
小林 「たとえば糸居さんが接続でいく時に『さて』とかそういうのより『続いての曲、そう、何とか』というふうに糸居さんが発明した間の言葉があって、みんなそれをいやらしいくらいにコピーしているわけですよ。そういうような意味じゃ初めてですよね、糸居さんのスタイルってのは。」>
(糸居五郎×小林克也 DJは音楽の料理人/糸居五郎『僕のDJグラフィティ』第三文明社刊)
<昭和20年の夏、ボクがあの敗戦を中国の大連でむかえた時、まわりの日本人は、みんな慟哭していたよ。だけど、僕は不思議に泣けなかった。これから、ユダヤ人のような長い放浪の旅が始まるんだな。思ったのはそれだけだった。>
(糸居五郎 81年6月30日午前6時)
つまり、強弱で進行しないから、ロックやジャズのリズムにとてものりにくい言葉なんですよね。それをのせるという話法を糸居さんがつくったということ。
あと、それに関連するんですが、言葉の文体を変えちゃったということ。
ぼくの解釈ですけども、糸居さんが、『おはよう』といった時、もう『ございます』はカットしちゃう。一小節があったら一小節に『おはよう』をぶち込む。そのときの間で進行する。こんにちわ、おはよう、ドン、きょうはいい気分、ドン、みたいなそれでいっちゃう。
そういうふうなスタイルを糸居さんは日本でつくったということですね。ぼくとして、すごく尊敬してます。」
糸居 「人間はリズム人間とメロディー人間とありましてね。玉置さんのはやっぱりメロディー人間のやり方で、じつにうまく言葉をつないでいく。ぼくたちのはリズムで、わりあい切っちゃうことが多い。そういった意味では野球の実況放送なんかによく似ているところがありますね。というのは、話す文体をすぐおしまいにできるようにつねに考えながらやってるから。」(中略)
小林 「たとえば糸居さんが接続でいく時に『さて』とかそういうのより『続いての曲、そう、何とか』というふうに糸居さんが発明した間の言葉があって、みんなそれをいやらしいくらいにコピーしているわけですよ。そういうような意味じゃ初めてですよね、糸居さんのスタイルってのは。」>
(糸居五郎×小林克也 DJは音楽の料理人/糸居五郎『僕のDJグラフィティ』第三文明社刊)
<昭和20年の夏、ボクがあの敗戦を中国の大連でむかえた時、まわりの日本人は、みんな慟哭していたよ。だけど、僕は不思議に泣けなかった。これから、ユダヤ人のような長い放浪の旅が始まるんだな。思ったのはそれだけだった。>
(糸居五郎 81年6月30日午前6時)