
福間良明『二・二六事件の幻影: 戦後大衆文化とファシズムへの欲望』(筑摩書房)。
2.26事件がいかに小説、舞台、映画、テレビドラマ、漫画などのメディアで「演出」され、どのように大衆に受容されてきたのか。2.26事件にまつわるエンタテインメントメディア通史の一冊。終章の結論は正直未だ途上といった印象でしかないのだが、なかなか読ませる内容ではある。
キーワードとされるのは青年将校たちの「情熱(公)」と彼らの個人的な「情愛(私)」。
敗戦後から60年代にかけて2.26事件という“素材”は、「情熱」の在り処や正当性が問われ続ける。勿論「情熱」の描写も60年代末から70年代初頭の“政治の季節”では公の情熱から個の情熱にフォーカスが移り、時代の空気を反映して過激化していく。本書で60年代(前後)に多くのページが割かれているのも、60年安保闘争や学園紛争を背景に、それに危機感を持った右翼勢力によるクーデター未遂事件である三無事件、さらに自衛隊幹部による三矢計画の露見など、実にキナ臭い公と個のせめぎ合いがこの時代に起こり、2.26事件における<行動・理念への情熱>を想起させたこともある。
50年代から60年代にかけて2.26事件を材に日本のファシズム批判を展開していた丸山眞男が、学園紛争の時代に教え子であるはずの学生から軟禁され、2.26事件の青年将校以上に、熱に浮かされただけの<行動・理念への情熱>を目の当たりにするくだりなどは実に皮肉に映る。
その一方で65年に発表された利根川裕『宴』の登場あたりから青年将校の「情愛」にメディアと大衆のフォーカスは移る。当然のことながら過激な“政治の季節”を経て事件から時に経つごとにメディアの演出と大衆の受容の傾向は、「情熱」から「情愛」へと移って行くわけだ。個人的にリアルタイムで観た映画である『動乱』や『226』では「情愛」=メロドラマこそあれ、「情熱」ではもはや燃やすべき対象は、ない。バブル期に公開された『226』に至っては、プロデューサーの奥山和由は<パワーダウンした現代だからこそ、この題材を提起する>として2.26事件を取り上げたものの、その「情熱」の対象は「何か」でしかない。
これには笑った。
<行動・理念への情熱>をシンプルにストレートに受け取ったとしても、さすがに「何か」はないだろう。しかし燃やすべき「情熱」を価値相対化地獄で失った末の80年代の価値観は最終的に「何か」を求めざるを得なかったのだ。
『226』の主人公には、決起に最後まで迷いながら決起後は最後まで戦い続けた安藤輝三でもなく、声高に維新を叫び続けながら一方では策謀家でもあった磯部浅一でもなく、そして事件後も彼らのように法廷闘争の果てに天皇の軍隊に銃殺されたわけではなく、事件の渦中で唯一拳銃自殺を果たした野中四郎が選ばれた。つまり事件の渦中で命を絶った=自己完結した彼は、具体的で何らかの「情熱」を見出さなければならない政治性を纏うことなく、「何か」の純粋や情熱を、純粋に、そして情熱的に描くために選ばれたのだろう。
映画やエンタテインメントメディアは必ずしも「事件」を正確に、そして政治的メッセージを込めて製作される必要はないとは思うが、あの時代はそういう時代だったのだとしか言いようがない。
しかしエンタテインメント的には見るべきもののないこの時代にも興味深い記述もある。
80年に公開された『動乱』をきっかけに青年将校ではなく、半世紀の時を経て末端の兵士たちの証言、手記の刊行が促されたという。青年将校の命令によって駆り出された兵士は1400余名。そのうち1000名は入隊一ヶ月未満の初年兵で、原隊復帰後は満州の最前線、それも<叛乱軍><国賊>としてあえて激戦地に投入された。しかも復員後も戦友会という名の<証言抑制機能>が働き続け、彼らの声は表に出ることはなかった(これは戦地での虐殺行為などの加害証言の抑制にもつながる)。そしてこの時代、戦友会の世代交代が起こり、兵士たちが声を挙げはじめたわけだ。
青年将校の「行動・理念への情熱」は事件直後から60年代にかけて検証され、描かれ続けてきたわけだが、事件に引きずり込まれ、心ならずも汚名を着せられ、物言うことも許されてこなかった兵士たちが描かれ、報われることはない。
主人公はいつでも青年将校である。事件を取り上げたところでエンタテインメントの世界では、本書でも触れられる50~60年代に製作された<軍神映画>とさほど変わりはしないのだ。
(長くなったので続く)

















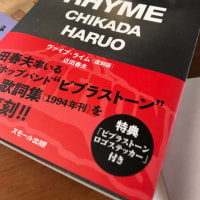


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます