[レビュー]
600年の韓中関係史から眺める朝鮮半島の未来
アイデンティティと知識で独自の民族国家を維持した朝鮮
朝鮮半島の平和と統一を実現するには、歴史から知恵を得よ
『帝国と義理堅い民族:韓中関係600年史、ハーバード大学ライシャワー講演』
オッド・アルネ・ウェスタッド著、オク・チャンジュン訳、ノモブックス刊
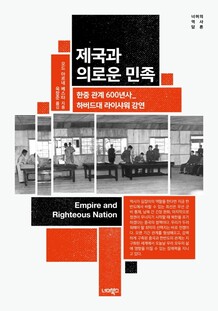
「2002年、韓国の66%が中国を好意的にみていた。(…)米国に対する好意的な意見は52%で、日本は30%を下回った」(米国ピュー・リサーチ・センター)。当時、韓国政府が太陽政策を取る中、北朝鮮の核問題が浮上し、その後中国は6カ国協議を通じて東アジア外交に復帰した。「中国が核交渉と南北間の永久的な和解を合意するのに肯定的な役割を果たすとみていた」というのが多数の世論だった。ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』など、韓流ドラマも中国人民を熱狂的なファンにしていた。いわゆる「嫌中」世論が騒がれている現在を考えれば、隔世の感がある。しかし、朝鮮半島と接した中国との悠久の関係をみれば、驚天動地のことでもない。東アジアを研究してきたノルウェー出身の歴史学者オッド・アルネ・ウェスタッド米エール大学教授の著書『帝国と義理堅い民族』(Empire and Righteous Nation: 600 Years of China-Korea Relations)は、韓中関係史600年を短く太くまとめ、朝鮮半島の今日を探り、未来を見通す洞察を提示する。
「帝国」は中国だ。ウェスタッドの前作『眠れぬ帝国』(Restless Empire: China and the World Since 1750)によると、中国は2000年のあいだ開放的で流動的な境界を持つ帝国であった。少なくとも近代以前の帝国は、膨張し、寛容だった。血筋ではなく文明で境界を区画してきた帝国は、中国文化の内外を分けず、民族や人種、身分を問わず垣根の中に包摂した。『帝国と義理堅い民族』で著者は14世紀以降の明・清に注目している。明帝国は性理学的世界観に基づき、「中国の伝統を復活させると同時に、中国と周辺国の関係を規律しようとした」。 清も「明帝国の代わりに帝国になることを望んだ」。満州族の皇室を中心に中国帝国の伝統を継承した。清が中華帝国であったことは「1644年に明の首都だった北京を占領した後、そこを首都にしたという点でもよく表れている」
「義理堅い民族」は朝鮮半島に定着した韓国(朝鮮)人を指す。「義理堅い」という表現は「義」を追求したという意味に近い。李成桂(イ・ソンゲ)と高麗末期の新進士大夫たちは性理学を基盤に儒教化プロジェクトを推し進め、朝鮮を開国し、全く新しい社会組職に取り組む。「朝鮮は明の企画より進んだ」と著者は評価する。「朝鮮は理念が中心となる国家であり、時に社会的規律と国家に対する忠誠を強調するとき、これが教祖主義に流れることもあった」。特に朝鮮は壬辰倭乱(文禄・慶長の役)と丙子の乱(清の朝鮮侵略)を経験し、中国および日本と区別される民族的アイデンティティが強力に形成されるが、著者は故キム・ジャヒョン米コロンビア大学教授の遺作『壬辰戦争と民族の誕生』(ノモブックス、2019)を引用し、16世紀末の朝鮮に19~20世紀のヨーロッパ人たちの「ネーション」に似た民族(国家)が建てられたと指摘する。

帝国の属性とは大概、周辺諸国と地域を服属させ編入することにあるが、朝鮮はずっと独自国家として存在した。朝鮮を侵犯した清帝国ですらも「朝鮮と対立する代わりに、朝鮮が帝国の中に留まらざるを得ないより良い条件を提示」したが、それは「朝貢品の軽減、帝国の褒賞、そして貿易機会の拡大などだった」。朝鮮が帝国に編入されなかったのには二つの理由があると著者は提示する。その一つが性理学と民族国家というアイデンティティ、すなわち「義理堅い民族」により作用したものなら、もう一つは知識である。朝鮮のエリートたちは、中国が自ら知っていることよりも帝国についてよく知っていた。毎年数回にわたって使臣らが北京を行き来したが、様々な情報が朝鮮の朝廷に報告され、各種の貿易を通じて利益を得た。何より、中国の内部事情をよく把握しており、帝国の提案や要求に適宜に対応することができた。しかし、このような韓中関係は19世紀後半に入り、巨大な挑戦と変化に直面する。朝鮮は民族概念が現代的な形態となるやいなや日本の植民地になり、この過程で中国との久しい関係は解体され、朝鮮半島は分断されるに至る。中国帝国も民族主義国家に変化した。
著者が長編ではないこの本で600年の時間をざっと眺めたのは、結局は今日の朝鮮半島を語るためだ。本書の表紙をめくり序文に進む前に、「平和と統一を成し遂げた未来の朝鮮半島のために」という献呈の言葉がある。朝鮮半島の今日をきちんと読み取って、これを土台に未来を開いていくために、中国と韓国の関係史を正しく理解しなければならないという意図が込められている。著者は前作『冷戦の地球史』(原題:The Global Cold War、日本語題:グローバル冷戦史 ―第三世界への介入と現代世界の形成―)で、帝国の概念を挙げて冷戦を説明する。植民支配を受けたアジア・アフリカに対する関心は地域研究と冷戦の現代史を結合することに進み、最後の冷戦の地である朝鮮半島と、朝鮮半島を説明する中国帝国に関心を持つことは当然の帰結であったのだろう。
著者は朝鮮半島の独自性の原因を、複合主権と複合アイデンティティにまとめている。明・清と朝鮮の間での複合的な主権関係と朝鮮の独特の民族(国家)概念に基づいたアイデンティティが、肯定的で安定的な韓中関係を維持させた秘訣だったということだ。しかし、20世紀に入って植民地支配を経て分断された朝鮮半島と中国いずれも、排他的な民族主義が根付き、様々な葛藤と危機をもたらしている。今こそ「長い期間(…)強力に構築された中国と朝鮮半島の関係」の持つ「潜在力」に注目すべきだと著者は強調する。「歴史が道案内の役割をするなら、今朝鮮半島で望むことのできる最善は、軍備統制、南北間の緊張緩和、最後に政権が崩壊し始めた時に北朝鮮を放棄するという中国の政策だ。我々が恐れるべき最悪の選択肢は戦争だ」。北朝鮮崩壊の可能性を高く見る見解には異見がありうるが、「嫌中」は誰のためにもならないという当然の事実を、そして健康なアイデンティティと相手に対する深い理解で未来を準備しなければならないという当為を、本の内容を読むほどに考えさせられる。






















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます