
- 日銀の緩和は長期化 一定の金利上昇を容認へ
- 債券市場では、日銀が許容する金利上限を探る動きが続く
- 2%の物価目標達成が遠のく中、日銀は苦しい持久戦
「金融緩和を今後も長く続けるが、副作用にも配慮する姿勢を見せる」
日銀が金融政策決定会合で決めた内容だ。
お金のめぐりをよくして、物価を高めることを目標に、日銀が「日本経済」という患者に打ってきた
金融緩和という「点滴」はなかなかうまくいかず、この先も長く続けざるを得ない。
だが、この点滴による副作用が無視できなくなってきたので、ある程度の「薬」も処方しよう。
たとえて言えば、こういうことになる。
「量」から「金利」へ
日銀が、物価を2%上昇させるというゴールに向け、異次元と呼ぶ大規模な金融緩和に踏み出したのは、5年前だ。
当初は、国債などの買い入れで、大量のお金を世の中に流し込む「量」を柱にした政策だったが、2016年2月には、銀行が貸し出しなどにお金を回すよう、日銀に預けるお金の一部の金利をマイナスにする
「マイナス金利」を開始。
その年の9月には、低い金利でお金が借りられるようにしようと、住宅ローンや企業向け融資の金利の目安となる、長期金利を「0%程度」に抑えこむ目標を掲げた。
こうして、政策の軸足を「量」から「金利」に移した日銀は、長期金利が0.1%程度に上がってくると、指定した利回りで無制限に国債を買う「指し値オペレーション」と呼ばれる市場調節を実施し、上昇を抑えることを繰り返してきた。
「超低金利」の副作用無視できず
ところが、金利の変動幅が狭くなったことで、国債の取引で利益を得るのが難しくなり参加者が減って、市場が機能不全に陥る懸念が出てきた。また、超低金利の長期化により、銀行が融資で稼ぎにくくなり、収益が悪化するおそれも強まっていた。
これまで、日銀は経済を押し上げる効果が副作用を上回ると説明してきたが、積もる副作用を無視できなくなったわけだ。
一方で、物価はなかなか上がらない。
直近の6月の物価の伸びは0.8%。今回日銀が公表した物価見通しは、2020年度で1.6%の上昇にとどまり、
2%の達成は、3年後の2021年度以降にずれ込む公算が強まっている。
そこで、日銀は、金融緩和という「点滴」は粘り強く続けていくことにし、同時に、金利は低い水準に
抑えるものの、ある程度まで変動するのはOKとし、一定の上昇を許容することを決めたのだ。
これが、日銀が処方した副作用向けの「薬」だが、これまで抑えつけるのに躍起となってきた金利の上昇を、一定程度とはいえ認めたことは、政策の一部修正だと受け止められた。
長期金利がさらに上昇すれば負担増に
長期金利は、日銀の決定会合の翌日以降、断続的に上がっている。
2日午前には、0.145%に上昇し、1年半ぶりの水準となった。
黒田総裁は、会見で、変動幅について「これまでの2倍程度が念頭だ」とし、0.1%ほどを上限に抑えてきた金利の上昇を、0.2%程度までは容認する考えを表明したが、実際に、日銀がそこまでの上昇を許容するのかどうかに、市場関係者の視線は集まっている。
日銀が、金利を抑える「指し値オペレーション」を発動するのが、金利が0.2%に上がった段階なのか、を見極めるため、債券市場では国債を売って日銀の姿勢を試す動きが続いているのだ。
今回日銀が容認した金利の変動幅では、住宅ローン金利などへの影響は限定的とみられる。
だが、この先も銀行の収益悪化などが続けば、もう一段の金利引き上げが求められる状況になるとの見方は
強く、その場合、家計の借入負担は増えることになる。
物価が上がりにくい環境が続くなか、苦しい持久戦を強いられている日銀。
今回打ち出した「苦心の策」が、金融政策の持続力強化や市場からの信認向上につながるのか、先行きは不透明だ。














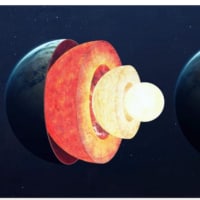

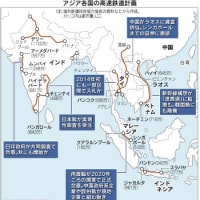
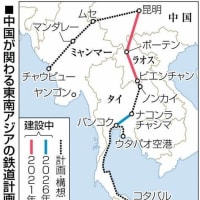

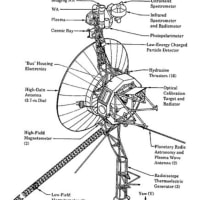
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます