●テレビが面白くない理由
195539 テレビ局に吹き荒れるリストラの嵐~人気芸能人のギャラ払えず
猛獣王S ( 30代 東京 営業 ) 08/12/23 AM11
『「今田耕司もクビ!?」テレビ局に吹き荒れるリストラの嵐』(日刊サイゾー)リンクより転載します。
----------------------------------------------------------------
TX『たけしの誰でもピカソ』HPより。
テレビ朝日の『たけしのTVタックル』でレギュラーを務める大竹まことが、「ギャラを下げても、番組を降ろさないでくれ」とリストラを恐れるシャレにならない発言をしたというが、このほかにもテレビ界ではリストラの嵐が吹き始めている。テレビ東京の『たけしの誰でもピカソ』もリストラにあって、メイン司会のビートたけしが頭を抱えているというのだ。
『誰でもピカソ』は97年4月にスタート。当初はアートをテーマにした珍しいバラエティ番組だったが、その後は、音楽やお笑いなど、あらゆるジャンルに渡って企画を取り上げてきた。
「サブ司会には吉本興業の今田耕司、芸術家の"熊さん"こと篠原勝之、タレントの渡辺満里奈を加えて4人でやってきたんです。ところが12月に入って、番組プロデューサーから、たけしに『今田ら3人を降ろして、若いアシスタントを入れませんか』という相談があったんですよ。たけしは、『それって、3人の首を切るリストラじゃないの?』と返しました。情が厚い彼としては、受け入れられる話ではないですよ」(番組スタッフ)
しかし、たけしが拒否しようが、折からのテレビ不況による制作費削減でリストラは避けられない状況。制作費が削られ、出演者の質が落ちればテレビのさらなる視聴率低下は免れないだろうが、この悪循環はしばらく続きそうだ。
http://www.trend-review.net/bbs/bbs.php?i=200&c=400&m=195539
●【ヒットで振り返る2008年~テレビ編~】 ドラマもバラエティも転換期を迎える - エンタ - 日経トレンディネット 2008年12月22日
昨年、この欄で視聴者の「テレビ離れ」の警鐘を鳴らしたが、2008年のテレビ界はさらに深刻な事態に見舞われた。スポンサーの「CM離れ」である。
・テレビCMの危機
2008年は、スポットCMが大きく落ち込む1年になった。なんと前年比1割減。
CMは大きく分けて、番組を提供する「タイム」と、番組と番組の間に流す「スポット」に分けられるが、タイムは番組の制作費に当てられるため、これまでテレビ局はスポットから利益を生み出してきた。
ところが、このスポットが落ち込み、収益が大きく悪化したのである。在京キー局5社の9月中間決算では、日本テレビとテレビ東京が赤字に転落。フジテレビ以外の4社が営業減益になった。
そこで、この秋からテレビ局はこれまで不文律で禁止してきた業種のCMを解禁し始めた。パチンコホール、宗教法人関連、そして金融商品のFXなどがそう。しかし、利益を追求するあまり、安易にそれらの解禁に走る行為は、改めてテレビ局のモラル・ハザードが問われそうである。
悪い話は止まらない。CM離れは、来年、さらに深刻化すると見られている。
「100年に1度」と言われる不況で、既にトヨタ自動車は広告費の3割削減を打ち出している。CM出稿量5位のトヨタだけに、その影響は計り知れない。また、そんなリーディングカンパニーの行動が他の企業へ波及する恐れもある。そうなると、50年間築き上げてきたテレビというビジネスモデル自体に、黄信号が点りかねない。
・NHKの台頭
そんな中、今年、CMに左右されないNHKが大きく視聴率を上げたことは象徴的である。今年度の上半期(3月31日~9月28日)のゴールデンタイムの視聴率が、1963年の調査以来、フジテレビを抜いて初めて1位となったのだ。
その要因として、全話20%を超えた大河ドラマ『篤姫』の存在、開会式(37.3%)や女子ソフトボール(30.6%)など高視聴率を連発した北京オリンピックの中継、昨年より1.4ポイントも視聴率を上げた『ニュース7』の健闘などが挙げられるが、同時に視聴者の“民放バラエティ離れ”もNHKをアシストした要因の一つと言わざるを得ない。
どの局を回しても、似たような企画に似たようなタレント。そんな安易な番組の乱造に、視聴者が食傷気味になっているのだ。そこで仕方なく、消極的理由でNHKが選ばれるようになったのである。
だが、民放もこのままではいけないと思ったのだろう。この秋からゴールデンタイムでドキュメンタリーをいくつか始めている。NHKに流れた視聴者を戻そうとの狙いだろうが、残念ながら苦戦しているのが実情である。
鳴り物入りで始まったTBSの『水曜ノンフィクション』は、5%前後の視聴率で低迷。関口宏の影響力に翳(かげ)りが見られた。
また、テレビ朝日の『報道発ドキュメンタリ宣言』も、初回こそ長門裕之・南田洋子夫妻の老いと向き合う姿を報じて22.9%の高視聴率をあげたものの、翌週から題材が一般人になったところ、一ケタにダウン。結局、芸能人以外では苦戦している。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20081222/1022123/
●J-CASTニュース : 朝日新聞100億円赤字に転落 広告大幅落ち込み、部数も減少 2008/11/21
朝日新聞社が、半期ベース(連結)で100億円以上の赤字に転落したことがわかった。単体ベースでみても売り上げが約142億円減少しており、販売・広告収入の落ち込みが裏付けられた形だ。新聞業界では「比較的勝ち組」とも言われる朝日新聞でさえ、苦境に立たされていることが浮き彫りになった。ほかの大手の新聞社の決算も悪化するのは確実だ。
・広告・販売とも、収入は「右肩下がり」
朝日新聞社(大阪市)は2008年11月21日、子会社のテレビ朝日(東京都港区)と朝日放送(大阪市)を通じて08年9月中間期(08年4月~9月)の連結決算を発表した。単体ベースの決算もあわせて発表されており、それによると、前年同期には1857億6900万円あった売上高が、7.7%減の1715億3200万円にまで減少。営業利益は前年同期が42億1800万円の黒字だったものが32億3000万円の赤字に転落している。純利益は同92.6%減の2億5300万円だった。
新聞各社の経営状態をめぐっては、広告・販売とも、収入は「右肩下がり」の状況が続いており、先行きが見えない情勢だ。今回の朝日の決算でも、売上高は約142億円も落ち込んでおり、そのかなりの分が広告収入の落ち込みによるものとみられ、関係者からは「前年比、通年ベースで広告だけで200億円近くは落ち込むのでは」との声も根強い。さらに、このところ部数も徐々に落ち込んでおり、ダブルパンチで売り上げが減る形だ。
・連結ベースでも大幅赤字
朝日新聞社は、不動産を大量に所有し、財務体質がいいことから「新聞業界の中では比較的勝ち組」と言われてきたが、11月20日発売の会員制経済誌「ザ・ファクタ」08年12月号が
「2009年3月期、創業130周年にして初の営業赤字転落という憂き目にあう」
などと大々的に報じており、通年ベースでも赤字転落が確実な情勢だ。
一方、連結ベースでは、売上高は前年同期比4.4%減の2698億7100万円、営業利益は前年同期74億4800万円だったものが5億400万円の赤字に転落。中間純利益に至っては、同47億6300万円の黒字だったものが、実に103億2500万円の赤字を記録している。
項目別にみていくと、「持分法による投資利益」が21億7300万円から6億100万円に激減しているほか、営業外費用として寄付金を50億1300万円を計上しているのが目立つ。さらに、特別損失として投資有価証券売却損44億6900万円を計上してもいる。
http://www.j-cast.com/2008/11/21030835.html
●J-CASTニュース : 毎日・産経が半期赤字転落 「新聞の危機」いよいよ表面化 2008/12/26
朝日新聞社の赤字決算が新聞業界に波紋を広げるなか、その流れが他の新聞社にも波及してきた。毎日新聞社と産経新聞社が相次いで半期の連結決算を発表したが、両社とも売り上げが大幅に落ち込み、営業赤字に転落していることが分かった。両社とも背景には広告の大幅な落ち込みがある。景気後退の影響で、さらに「右肩下がり」になるものとみられ、いよいよ、「新聞危機」が表面化してきた形だ。
・「販売部数の低迷、広告収入の減少など引き続き多くの課題」
毎日新聞社は2008年12月25日、08年9月中間期(08年4月~9月)の連結決算を発表した。売上高は前年同期比4.2%減の1380億3100万円だったが、営業利益は、前年同期26億8300万円の黒字だったものが、9億1900万円の赤字に転落。純利益も、同12億5600万円の黒字が16億1900万円の赤字に転じている。
単体ベースで見ると、売上高は前年同期が734億2500万円だったものが、6.5%減の686億8400万円に減少。営業利益は同5億4100万円の黒字が25億8000万円の赤字に転じ、純利益は1億8900万円の赤字がさらに拡大し、20億7800万円の赤字と、約11倍に膨らんだ。
発表された報告書では、
「当社グループを取り巻く新聞業界は、若年層を中心として深刻な購買離れによる販売部数の低迷、広告収入の減少など引き続き多くの課題を抱えている」
とし、業績不振の原因として、販売部数と広告収入の落ち込みを挙げている。
毎日新聞社の常務取締役(営業・総合メディア担当)などを歴任し、「新聞社-破綻したビジネスモデル」などの著書があるジャーリストの河内孝さんは、
「『上期で赤字が出ても、下期で巻き返して通期では黒字にする』ということは、これまでにもあった」
と話す。ところが、今回は事情が違うといい、広告の大幅落ち込み傾向もあって、通期でも赤字が出る可能性が高いと予測している。河内さんは、
「仮に通期で赤字が出たとすれば、事実上倒産し、1977年に現在の『株式会社毎日新聞社』に改組されて以来、初めての事態なのでは」
と話している。
・産経新聞も営業赤字に転落
産経新聞も08年12月19日に、08年9月中間期の連結決算を発表している。こちらも、毎日新聞と同様、不振ぶりが読み取れる。
子会社の「サンケイリビング」をフジテレビに売却した関係で、売上高は978億500万円から17.4%減の808億1900万円にまで落ち込んだ。9億2900万円の黒字だった営業損益は、4億3400万円の赤字に転落。特別損失として「事業再編損」16億8400万円が計上されており、純利益は前年同期では1億1700万円の黒字だったものが、19億8400万円の赤字となっている。
単体ベースでは、売上高は前年同期が588億1200万円だったものが539億4300万円に8.3%減少。営業利益は9億2700万円の黒字が10億7800万円の赤字に転落。一方、純利益は、特別利益として「関係会社株式売却益」39億100万円が計上されたことなどから、前年同期は2億2900億円の黒字だったものが、5億8300万円に倍増している。
同社の報告書では、業績不振の背景として、毎日新聞と同様、広告・販売収入の落ち込みを指摘している。また、同社は新聞社の中ではウェブサイトへの積極的な取り組みが目立つが、報告書でも
「(同社グループ)5サイトは月間合計8億ページビューを記録するなど順調に推移している。『MSN産経ニュース』は産経新聞グループの完全速報体制が構築されており、新聞社系のインターネットサイトの中でも特にユーザーの注目を集めている」
と、自信を見せている。一方で、ウェブサイトが同社の収益にどのように貢献したかについての記述は見あたらない。
http://www.j-cast.com/2008/12/26033024.html
●同じような内容の番組を、同じ時間帯にどのチャンネルも放送するという現象が起きたのである - 株式日記と経済展望 2008年11月14日
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/1682c233c850803d01beeb9ec6a6384d
●広告に頼った経営というのは不況に対するリスクは高いです。 - 株式日記と経済展望 2008年12月23日
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/a4c8b3547c0dca9c8dc2d877cc907ec3
【私のコメント】
インターネットの台頭と世界不況の影響で、新聞・民放テレビ・雑誌といったマスコミ業界に大不況の嵐が訪れている。偏向報道を繰り返してきたマスコミの不況転落は朗報との受け止め方も多い。しかし、事態はそれほど単純ではないように思われる。
私も含めた一般庶民は、自分の専門とする分野以外では、マスコミの報道を鵜呑みにする傾向が強い。報道が真実かどうかを判定する知識がないのだから已むを得ないことではある。しかしながら、その結果として、世論はマスコミの論調を鵜呑みにしたものになっていく。日本の支配階層はこのメカニズムを利用して国民世論を操作し、主権者たる国民は自分の意志で行動しているつもりになっているが、結果的には日本支配階層が国政をほぼ完全に支配することになるのだ。このシステムは恐らく日本だけではなく、あらゆる民主主義国で機能しているのではないかと想像する。
現在起きているインターネットというメディアの台頭は、決して革命的なものではない。産業革命期の欧州で新聞という最も古いマスメディアが誕生した後、1895年に映画がフランスで、1920年にラジオが米国で、1941年にテレビが米国で、それぞれ商業的活動を開始している。これらの新しいメディアが台頭する度に、マスメディアの世界の中で既存のメディアとの役割分担が変化するという事件が起きている。例えば、日本におけるテレビの台頭は従来花形のメディアであった映画産業の低迷を作り出している。インターネットの台頭もそれらの事件の繰り返しに過ぎない。テレビや新聞といったレガシーメディアはデジタル化に適したデータの送信という観点から見てインターネットと言う環境に適しており、徐々にその活動の場をインターネットの世界に移しつつある。課金の問題がクリアされればその移行は一気に進むだろう。無論、インターネット上の無料ニュースサイト(新聞のホームページを含む)に視聴者を奪われる新聞やテレビは収益が悪化し、社員の給与引き下げやリストラ、救済合併による弱小企業の消滅といった変化が起きることは確実だ。ただ、取材する・記事を書くという記者の仕事は決してなくなることはない。そして、世論を作り出すことで支配階層が国政を支配するというマスメディアの機能も変化することはないだろう。仮に大手マスコミや主要地方紙などの経営危機が起きるならば、場合によっては日本支配階層は公的資金を注入してもその破綻・消滅を回避すると想像する。
インターネットは自由な空間であり、そこは日本支配階層も大手マスコミも影響力を及ぼせない、と考える人もいるだろう。しかしながら、インターネットに流れるニュースのほとんどは大手マスコミの記事である。また、インターネット上で記事を公表し活動する人々の中で、多くの人々からのアクセスを集める質の高い記事を書く人々の大部分はマスコミ関係者であるように思われる。例えば国際ニュース解説で有名な田中宇氏は元共同通信記者だし、池田信夫ブログの主催者である池田信夫氏は元NHK社員である。株式日記のTORA氏は素性不明だが、彼は(表向きは元銀行員と名乗っているが、実際には)電通関係者ではないかと私は想像している。TORA氏がマスコミや電通を時に激しく非難するのも、逆に彼がマスコミ関係者であることを示しているように思われる。
2chの様な匿名掲示板はどうだろうか?一見すると一般大衆が自由に書き込んでいる様に見える。しかし、ニュース系の板に限定すると、一定の論調をもった書き込みが多いことが分かる。それによって、いわば2chの世論らしきものが形成されており、アクセスした一般大衆はそれに洗脳されていくのだ。これは自然な現象ではあり得ないことであり、日本の支配階層が関与していることは間違いない。恐らくは電通関係者の指令の元に多数の人々が雇用され、2chのニュース系の板に24時間体制で書き込みを行っているのだと思われる。そもそも、著作権法から見て違法の可能性が高いニュース等の全文引用が大量に行われている2chに対してマスコミ各社による法的措置が行われず、未だに閉鎖されていないのは、2chが日本支配階層の影響下に置かれているから、としか考えられないのだ。
結論を言おう。一見するとマスコミはインターネットの台頭で危機に瀕しているように見える。しかし、実際にはインターネットもマスコミ関係者の強い影響下に置かれている。そして、一般大衆はインターネットを含めたマスメディアに洗脳されて、マスメディアの流す記事を鵜呑みにして、それをあたかも自分の意見であるかの様に思い込み、それによって日本支配階層は自由自在に国民世論を形成して民主主義国家日本を隠然と支配し続けるのだ。全体としては何も変わらない。変わったのは、マスメディアの種類に新たにインターネットが加わったことだけなのだ。
↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

195539 テレビ局に吹き荒れるリストラの嵐~人気芸能人のギャラ払えず
猛獣王S ( 30代 東京 営業 ) 08/12/23 AM11
『「今田耕司もクビ!?」テレビ局に吹き荒れるリストラの嵐』(日刊サイゾー)リンクより転載します。
----------------------------------------------------------------
TX『たけしの誰でもピカソ』HPより。
テレビ朝日の『たけしのTVタックル』でレギュラーを務める大竹まことが、「ギャラを下げても、番組を降ろさないでくれ」とリストラを恐れるシャレにならない発言をしたというが、このほかにもテレビ界ではリストラの嵐が吹き始めている。テレビ東京の『たけしの誰でもピカソ』もリストラにあって、メイン司会のビートたけしが頭を抱えているというのだ。
『誰でもピカソ』は97年4月にスタート。当初はアートをテーマにした珍しいバラエティ番組だったが、その後は、音楽やお笑いなど、あらゆるジャンルに渡って企画を取り上げてきた。
「サブ司会には吉本興業の今田耕司、芸術家の"熊さん"こと篠原勝之、タレントの渡辺満里奈を加えて4人でやってきたんです。ところが12月に入って、番組プロデューサーから、たけしに『今田ら3人を降ろして、若いアシスタントを入れませんか』という相談があったんですよ。たけしは、『それって、3人の首を切るリストラじゃないの?』と返しました。情が厚い彼としては、受け入れられる話ではないですよ」(番組スタッフ)
しかし、たけしが拒否しようが、折からのテレビ不況による制作費削減でリストラは避けられない状況。制作費が削られ、出演者の質が落ちればテレビのさらなる視聴率低下は免れないだろうが、この悪循環はしばらく続きそうだ。
http://www.trend-review.net/bbs/bbs.php?i=200&c=400&m=195539
●【ヒットで振り返る2008年~テレビ編~】 ドラマもバラエティも転換期を迎える - エンタ - 日経トレンディネット 2008年12月22日
昨年、この欄で視聴者の「テレビ離れ」の警鐘を鳴らしたが、2008年のテレビ界はさらに深刻な事態に見舞われた。スポンサーの「CM離れ」である。
・テレビCMの危機
2008年は、スポットCMが大きく落ち込む1年になった。なんと前年比1割減。
CMは大きく分けて、番組を提供する「タイム」と、番組と番組の間に流す「スポット」に分けられるが、タイムは番組の制作費に当てられるため、これまでテレビ局はスポットから利益を生み出してきた。
ところが、このスポットが落ち込み、収益が大きく悪化したのである。在京キー局5社の9月中間決算では、日本テレビとテレビ東京が赤字に転落。フジテレビ以外の4社が営業減益になった。
そこで、この秋からテレビ局はこれまで不文律で禁止してきた業種のCMを解禁し始めた。パチンコホール、宗教法人関連、そして金融商品のFXなどがそう。しかし、利益を追求するあまり、安易にそれらの解禁に走る行為は、改めてテレビ局のモラル・ハザードが問われそうである。
悪い話は止まらない。CM離れは、来年、さらに深刻化すると見られている。
「100年に1度」と言われる不況で、既にトヨタ自動車は広告費の3割削減を打ち出している。CM出稿量5位のトヨタだけに、その影響は計り知れない。また、そんなリーディングカンパニーの行動が他の企業へ波及する恐れもある。そうなると、50年間築き上げてきたテレビというビジネスモデル自体に、黄信号が点りかねない。
・NHKの台頭
そんな中、今年、CMに左右されないNHKが大きく視聴率を上げたことは象徴的である。今年度の上半期(3月31日~9月28日)のゴールデンタイムの視聴率が、1963年の調査以来、フジテレビを抜いて初めて1位となったのだ。
その要因として、全話20%を超えた大河ドラマ『篤姫』の存在、開会式(37.3%)や女子ソフトボール(30.6%)など高視聴率を連発した北京オリンピックの中継、昨年より1.4ポイントも視聴率を上げた『ニュース7』の健闘などが挙げられるが、同時に視聴者の“民放バラエティ離れ”もNHKをアシストした要因の一つと言わざるを得ない。
どの局を回しても、似たような企画に似たようなタレント。そんな安易な番組の乱造に、視聴者が食傷気味になっているのだ。そこで仕方なく、消極的理由でNHKが選ばれるようになったのである。
だが、民放もこのままではいけないと思ったのだろう。この秋からゴールデンタイムでドキュメンタリーをいくつか始めている。NHKに流れた視聴者を戻そうとの狙いだろうが、残念ながら苦戦しているのが実情である。
鳴り物入りで始まったTBSの『水曜ノンフィクション』は、5%前後の視聴率で低迷。関口宏の影響力に翳(かげ)りが見られた。
また、テレビ朝日の『報道発ドキュメンタリ宣言』も、初回こそ長門裕之・南田洋子夫妻の老いと向き合う姿を報じて22.9%の高視聴率をあげたものの、翌週から題材が一般人になったところ、一ケタにダウン。結局、芸能人以外では苦戦している。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20081222/1022123/
●J-CASTニュース : 朝日新聞100億円赤字に転落 広告大幅落ち込み、部数も減少 2008/11/21
朝日新聞社が、半期ベース(連結)で100億円以上の赤字に転落したことがわかった。単体ベースでみても売り上げが約142億円減少しており、販売・広告収入の落ち込みが裏付けられた形だ。新聞業界では「比較的勝ち組」とも言われる朝日新聞でさえ、苦境に立たされていることが浮き彫りになった。ほかの大手の新聞社の決算も悪化するのは確実だ。
・広告・販売とも、収入は「右肩下がり」
朝日新聞社(大阪市)は2008年11月21日、子会社のテレビ朝日(東京都港区)と朝日放送(大阪市)を通じて08年9月中間期(08年4月~9月)の連結決算を発表した。単体ベースの決算もあわせて発表されており、それによると、前年同期には1857億6900万円あった売上高が、7.7%減の1715億3200万円にまで減少。営業利益は前年同期が42億1800万円の黒字だったものが32億3000万円の赤字に転落している。純利益は同92.6%減の2億5300万円だった。
新聞各社の経営状態をめぐっては、広告・販売とも、収入は「右肩下がり」の状況が続いており、先行きが見えない情勢だ。今回の朝日の決算でも、売上高は約142億円も落ち込んでおり、そのかなりの分が広告収入の落ち込みによるものとみられ、関係者からは「前年比、通年ベースで広告だけで200億円近くは落ち込むのでは」との声も根強い。さらに、このところ部数も徐々に落ち込んでおり、ダブルパンチで売り上げが減る形だ。
・連結ベースでも大幅赤字
朝日新聞社は、不動産を大量に所有し、財務体質がいいことから「新聞業界の中では比較的勝ち組」と言われてきたが、11月20日発売の会員制経済誌「ザ・ファクタ」08年12月号が
「2009年3月期、創業130周年にして初の営業赤字転落という憂き目にあう」
などと大々的に報じており、通年ベースでも赤字転落が確実な情勢だ。
一方、連結ベースでは、売上高は前年同期比4.4%減の2698億7100万円、営業利益は前年同期74億4800万円だったものが5億400万円の赤字に転落。中間純利益に至っては、同47億6300万円の黒字だったものが、実に103億2500万円の赤字を記録している。
項目別にみていくと、「持分法による投資利益」が21億7300万円から6億100万円に激減しているほか、営業外費用として寄付金を50億1300万円を計上しているのが目立つ。さらに、特別損失として投資有価証券売却損44億6900万円を計上してもいる。
http://www.j-cast.com/2008/11/21030835.html
●J-CASTニュース : 毎日・産経が半期赤字転落 「新聞の危機」いよいよ表面化 2008/12/26
朝日新聞社の赤字決算が新聞業界に波紋を広げるなか、その流れが他の新聞社にも波及してきた。毎日新聞社と産経新聞社が相次いで半期の連結決算を発表したが、両社とも売り上げが大幅に落ち込み、営業赤字に転落していることが分かった。両社とも背景には広告の大幅な落ち込みがある。景気後退の影響で、さらに「右肩下がり」になるものとみられ、いよいよ、「新聞危機」が表面化してきた形だ。
・「販売部数の低迷、広告収入の減少など引き続き多くの課題」
毎日新聞社は2008年12月25日、08年9月中間期(08年4月~9月)の連結決算を発表した。売上高は前年同期比4.2%減の1380億3100万円だったが、営業利益は、前年同期26億8300万円の黒字だったものが、9億1900万円の赤字に転落。純利益も、同12億5600万円の黒字が16億1900万円の赤字に転じている。
単体ベースで見ると、売上高は前年同期が734億2500万円だったものが、6.5%減の686億8400万円に減少。営業利益は同5億4100万円の黒字が25億8000万円の赤字に転じ、純利益は1億8900万円の赤字がさらに拡大し、20億7800万円の赤字と、約11倍に膨らんだ。
発表された報告書では、
「当社グループを取り巻く新聞業界は、若年層を中心として深刻な購買離れによる販売部数の低迷、広告収入の減少など引き続き多くの課題を抱えている」
とし、業績不振の原因として、販売部数と広告収入の落ち込みを挙げている。
毎日新聞社の常務取締役(営業・総合メディア担当)などを歴任し、「新聞社-破綻したビジネスモデル」などの著書があるジャーリストの河内孝さんは、
「『上期で赤字が出ても、下期で巻き返して通期では黒字にする』ということは、これまでにもあった」
と話す。ところが、今回は事情が違うといい、広告の大幅落ち込み傾向もあって、通期でも赤字が出る可能性が高いと予測している。河内さんは、
「仮に通期で赤字が出たとすれば、事実上倒産し、1977年に現在の『株式会社毎日新聞社』に改組されて以来、初めての事態なのでは」
と話している。
・産経新聞も営業赤字に転落
産経新聞も08年12月19日に、08年9月中間期の連結決算を発表している。こちらも、毎日新聞と同様、不振ぶりが読み取れる。
子会社の「サンケイリビング」をフジテレビに売却した関係で、売上高は978億500万円から17.4%減の808億1900万円にまで落ち込んだ。9億2900万円の黒字だった営業損益は、4億3400万円の赤字に転落。特別損失として「事業再編損」16億8400万円が計上されており、純利益は前年同期では1億1700万円の黒字だったものが、19億8400万円の赤字となっている。
単体ベースでは、売上高は前年同期が588億1200万円だったものが539億4300万円に8.3%減少。営業利益は9億2700万円の黒字が10億7800万円の赤字に転落。一方、純利益は、特別利益として「関係会社株式売却益」39億100万円が計上されたことなどから、前年同期は2億2900億円の黒字だったものが、5億8300万円に倍増している。
同社の報告書では、業績不振の背景として、毎日新聞と同様、広告・販売収入の落ち込みを指摘している。また、同社は新聞社の中ではウェブサイトへの積極的な取り組みが目立つが、報告書でも
「(同社グループ)5サイトは月間合計8億ページビューを記録するなど順調に推移している。『MSN産経ニュース』は産経新聞グループの完全速報体制が構築されており、新聞社系のインターネットサイトの中でも特にユーザーの注目を集めている」
と、自信を見せている。一方で、ウェブサイトが同社の収益にどのように貢献したかについての記述は見あたらない。
http://www.j-cast.com/2008/12/26033024.html
●同じような内容の番組を、同じ時間帯にどのチャンネルも放送するという現象が起きたのである - 株式日記と経済展望 2008年11月14日
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/1682c233c850803d01beeb9ec6a6384d
●広告に頼った経営というのは不況に対するリスクは高いです。 - 株式日記と経済展望 2008年12月23日
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/a4c8b3547c0dca9c8dc2d877cc907ec3
【私のコメント】
インターネットの台頭と世界不況の影響で、新聞・民放テレビ・雑誌といったマスコミ業界に大不況の嵐が訪れている。偏向報道を繰り返してきたマスコミの不況転落は朗報との受け止め方も多い。しかし、事態はそれほど単純ではないように思われる。
私も含めた一般庶民は、自分の専門とする分野以外では、マスコミの報道を鵜呑みにする傾向が強い。報道が真実かどうかを判定する知識がないのだから已むを得ないことではある。しかしながら、その結果として、世論はマスコミの論調を鵜呑みにしたものになっていく。日本の支配階層はこのメカニズムを利用して国民世論を操作し、主権者たる国民は自分の意志で行動しているつもりになっているが、結果的には日本支配階層が国政をほぼ完全に支配することになるのだ。このシステムは恐らく日本だけではなく、あらゆる民主主義国で機能しているのではないかと想像する。
現在起きているインターネットというメディアの台頭は、決して革命的なものではない。産業革命期の欧州で新聞という最も古いマスメディアが誕生した後、1895年に映画がフランスで、1920年にラジオが米国で、1941年にテレビが米国で、それぞれ商業的活動を開始している。これらの新しいメディアが台頭する度に、マスメディアの世界の中で既存のメディアとの役割分担が変化するという事件が起きている。例えば、日本におけるテレビの台頭は従来花形のメディアであった映画産業の低迷を作り出している。インターネットの台頭もそれらの事件の繰り返しに過ぎない。テレビや新聞といったレガシーメディアはデジタル化に適したデータの送信という観点から見てインターネットと言う環境に適しており、徐々にその活動の場をインターネットの世界に移しつつある。課金の問題がクリアされればその移行は一気に進むだろう。無論、インターネット上の無料ニュースサイト(新聞のホームページを含む)に視聴者を奪われる新聞やテレビは収益が悪化し、社員の給与引き下げやリストラ、救済合併による弱小企業の消滅といった変化が起きることは確実だ。ただ、取材する・記事を書くという記者の仕事は決してなくなることはない。そして、世論を作り出すことで支配階層が国政を支配するというマスメディアの機能も変化することはないだろう。仮に大手マスコミや主要地方紙などの経営危機が起きるならば、場合によっては日本支配階層は公的資金を注入してもその破綻・消滅を回避すると想像する。
インターネットは自由な空間であり、そこは日本支配階層も大手マスコミも影響力を及ぼせない、と考える人もいるだろう。しかしながら、インターネットに流れるニュースのほとんどは大手マスコミの記事である。また、インターネット上で記事を公表し活動する人々の中で、多くの人々からのアクセスを集める質の高い記事を書く人々の大部分はマスコミ関係者であるように思われる。例えば国際ニュース解説で有名な田中宇氏は元共同通信記者だし、池田信夫ブログの主催者である池田信夫氏は元NHK社員である。株式日記のTORA氏は素性不明だが、彼は(表向きは元銀行員と名乗っているが、実際には)電通関係者ではないかと私は想像している。TORA氏がマスコミや電通を時に激しく非難するのも、逆に彼がマスコミ関係者であることを示しているように思われる。
2chの様な匿名掲示板はどうだろうか?一見すると一般大衆が自由に書き込んでいる様に見える。しかし、ニュース系の板に限定すると、一定の論調をもった書き込みが多いことが分かる。それによって、いわば2chの世論らしきものが形成されており、アクセスした一般大衆はそれに洗脳されていくのだ。これは自然な現象ではあり得ないことであり、日本の支配階層が関与していることは間違いない。恐らくは電通関係者の指令の元に多数の人々が雇用され、2chのニュース系の板に24時間体制で書き込みを行っているのだと思われる。そもそも、著作権法から見て違法の可能性が高いニュース等の全文引用が大量に行われている2chに対してマスコミ各社による法的措置が行われず、未だに閉鎖されていないのは、2chが日本支配階層の影響下に置かれているから、としか考えられないのだ。
結論を言おう。一見するとマスコミはインターネットの台頭で危機に瀕しているように見える。しかし、実際にはインターネットもマスコミ関係者の強い影響下に置かれている。そして、一般大衆はインターネットを含めたマスメディアに洗脳されて、マスメディアの流す記事を鵜呑みにして、それをあたかも自分の意見であるかの様に思い込み、それによって日本支配階層は自由自在に国民世論を形成して民主主義国家日本を隠然と支配し続けるのだ。全体としては何も変わらない。変わったのは、マスメディアの種類に新たにインターネットが加わったことだけなのだ。
↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。














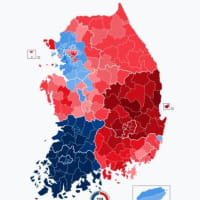
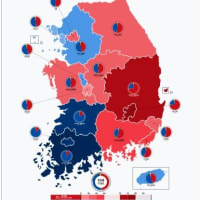

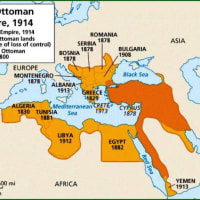










> 現在起きているインターネットというメディアの台頭は、決して革命的なものではない。産業革命期の欧州で新聞という最も古いマスメディアが誕生した後、1895年に映画がフランスで、1920年にラジオが米国で、1941年にテレビが米国で、それぞれ商業的活動を開始している。これらの新しいメディアが台頭する度に、マスメディアの世界の中で既存のメディアとの役割分担が変化するという事件が起きている。
インターネット自体はメディア(媒体)ではないと思います。むしろほとんどは1次的な情報の集まり、ひどく散漫で分散型のシステムです。ただ、インターネットにあるいくつかのサイトやコンテンツは、分散のシステムを統合する役割を果たし、媒体的な役割を果たしています。この場合は既存メディアとの交代ともいえる。分散型システムと媒体的な役割、両方の性格をもつことが分析を困難にしている。
毎日新聞の「変態問題」は時期を考えると、謀略的な臭いがプンプンします。集中的なシステムと分散型の双方の誘導ができるとネット世論も簡単に誘導できる。権力はネットとの関係をどうするかいま模索中かもしれません。同じ興味などある目的をもつものが離れていたり、それまで知らなくても連帯することが可能になっている。振り込め詐欺など犯罪にも使われていますが、こうしたことは政治的には無視できない変化です。活版印刷で聖書を印刷できるようになった後、カトリック教会で起きた変化くらいは起こるのかもしれません。変化の程度は、ラジオやテレビの登場という変化とは違ってくると思います。
TORA氏がどう反応するかは興味がありますが。
TORA氏は「私の拙い文章でマスコミ関係者ではない事が分かると思います。」と否定しています。
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/cmt/c6265808d505be8b3da6f8a5bba8acef
しかし、株式日記で取り上げられる話題の幅広さと的確な分析は彼がただ者ではないことを示しています。一般の会社員や官僚ではこれだけ幅広い分野をカバーできないでしょう。やはり、ニュースの専門家であるマスコミ関係者であると私は思います。
>インターネット自体はメディア(媒体)ではないと思います。むしろほとんどは1次的な情報の集まり、ひどく散漫で分散型のシステムです。ただ、インターネットにあるいくつかのサイトやコンテンツは、分散のシステムを統合する役割を果たし、媒体的な役割を果たしています。この場合は既存メディアとの交代ともいえる。分散型システムと媒体的な役割、両方の性格をもつことが分析を困難にしている。
インターネットの分散型の部分では、国民世論扇動を実行することはまず不可能だと思います。アクセスの集中する少数のサイトやコンテンツにしか世論扇動はできない。そして、その様なサイトやコンテンツの多くはマスコミ関係者が作っている、あるいはマスコミ関係者の影響下にあるのではないか、というのが私の想像(妄想?)です。厳しい選抜をくぐり抜け、記者等として長年の経験を積んだ記事書きのプロであるマスコミ関係者に対抗できるレベルの記事を書ける一般庶民の数はそう多くないでしょう。
洗脳のシステムは変わらないでしょうな。
ところで、王子様。もっと更新してください。
イスラエルの暴走が始まりましたよ。
意外とテレビ頑張ってます。
でもその中で、テレビがなくても平気だという人にテレビの魅力を伝えるにはどうすればいいと思いますか?
テレビは知能の低い人々向けの娯楽という位置づけが定まりつつあるように思います。これは、不特定多数の一般庶民を対象にしているからであり、テレビの特性上避けられないことです。従って、テレビが無くても平気な人々はテレビを見ることはありません。テレビを見ない人は、テレビに魅力を感じていないから見ないのです。