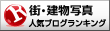『昨日も秋にはときどきある、朝もひるもずうつと夕暮れのやうな空模様のまま夜になるとしぐれが来ましたが、まだ東京近くでは木の葉の散るしぐれやまがうころではないと知りながら、私は落ち葉の音もまじっているやうに聞えてなりません。しぐれは私を古い日本の悲しみに引き入れるものですから、逆にそれをまぎらはそうと、しぐれの詩人と言われる宗祇の連歌など拾ひ読みしてをりますうちにも、やはりときどき落ち葉の音が聞えます。
葉の落ちるには早いし、また考へてみますと私の書斎の屋根に葉の落ちる木はないのであります。してみると落ち葉の音は幻の音でありませうか。私は薄気味悪くなりましてじっと耳をすましてみますと落葉の音は聞えません。ところがぼんやり読んでをりますとまた落葉の音が聞えます。私は寒気がしました。この幻の落ち葉の音は私の遠い過去からでも聞えて来るやうに思ったからでありました。』
これは川端康成の「しぐれ」という作品の中の一節である。
僕などが百万言弄するよりも三島由紀夫が的確な感想を彼の「文章読本」に残しているのでそれを載せてみたい。
『このさりげない詠嘆の中に、作者は文章を鴎外のやうにも、また鏡花のやうにも使はず、極度に明晰に物体を指示するのでもなく、また自分の感覚を、いろいろな修飾語で飾り立てるのでもなく、ただ淡々と情念の流れを述べながら、その底に深い抒情的悲しみや、鬼気をひそませています。
川端氏がこのやうな文体に達したのは『雪国』以後のことでありますが、氏の文章はますます小説的でなくなりながら、ますます作品としては傑作を生みだしていくといふ、不思議な傾向をたどっています。』
ここで僕が三島に深く共鳴するのは「ただ淡々と情念の流れを述べながら、その底に深い抒情的悲しみや、鬼気をひそませています。」という部分だ。
日本語の伝統の中では大雑把に分けると、文章を短くきることによって文章と文章の空白に余韻を残す名文と、この川端の文章のように、文章を巧みにつなげることによって情念、思念の「流れ」のようなものを生み出し、あたかも山深きところを流れる清流のような動的な美しさを生み出す名文があるように思う。
前者の例が夏目漱石や志賀直哉、そして森鴎外などもこの範疇に入るだろう、一方後者の代表的な例がこの川端康成だと思う。
日本ではやはり俳句や和歌の伝統があるせいだと思うが、前者の文章のほうが評価が高いような気がする。漱石や鴎外の評価はまるで神様のような扱いだし、志賀直哉なども小説の神様などといわれた。
僕もそういう日本の伝統的な「好み」はよくわかる。漱石や志賀直哉の文章などのもつ「余韻」、簡素な表現のなかに表わされた深淵との対比には今でもほれぼれとする。だがである、だが、もし誰か一人をとれといわれたら数秒迷って川端康成を僕はとる。
とにかくこの「思念、情念の流れ」というものに僕はどうしようもなく魅惑されるのだ。
山登りをしていて深い林の中をあるいていると、どこからともなくかすかにサラサラと水の流れる音が聞こえる。
どこかと思い音のするほうに歩いていくと、深い草叢の下に実に美しい清流が流れていた……
一言で川端の文章の印象を現すとこういう感じだろうか。
そして、三島が「深い抒情的悲しみ」や「鬼気」と表現したものも感じ取れるだろうか。
僕はこれらも川端の文章のもつ独特のあじわい(そう表現するのはためらわれるが…)だと感じる。
この「ところがぼんやり読んでおりますとまた落葉の音が聞えます。私は寒気がしました。この幻の落ち葉の音は私の遠い過去からでも聞えて来るやうに思ったからでもありました。」という言葉に、まさに三島が言った「深い抒情的悲しみ」「鬼気」というものがにじみ出ている。
三島は(意識的にか無意識的にか)それ以上ここでは語ってないが、僕は実はこの一節の中に川端康成という人のなにがしかというものがあますところなくあらわされていると思えてならない。
いずれにしても、悲しみや鬼気、というものをこれほどまでにうつくしく高めた作家は川端以外にはいないのではないだろうか。