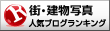理由はわからない。
健康オ〇クと一時は言ったこともあるが、いまは健康マニアと呼ぶことにしている。
タバコは15の時遊びですって、気分が悪くなり嘔吐して熱が出たのでやめた。タバコはまぁ、自殺行為といっていい。
僕は家族ががんで闘病している姿を見ているので、たばこを吸っている人を見ると、「私はがんになりたい」と言っているのと同じなわけで、とうていそんな人の気がしれない。
たばこを吸っている人に辞めさせる一番いい方法は、癌で闘病している人のドキュメンタリーでも見せるのが一番いいだろう。自分がやっていることがどれほど恐ろしいことかわかるはずだ。
それらの人にとっては、たとえば原発賛成派の人の原発事故に対する姿勢と同じで、「自分や家族が実際に」その被害を受けて症状が出てみないかぎり人ごと、あるいは人ごとであってほしいと思っているだけなのであろう。
酒は…これは若いころは無茶もした。
飲みすぎて路上で寝たことが2回ほどある、幸い友達がそばにいたので助けてくれたが。
僕は寝つきが悪いので、以前外で働いていた時は朝が早い仕事をしていたため、どうしても眠るために寝酒をしていた。
その時も「健康を考えて」ワインを主に飲んでいたが、ワイングラス4~5杯重ねてから寝ていたので、身体には悪かったに違いない。
今は、朝早く起きる必要はないので寝れなければ起きて仕事でもしていればいいのでそんなことはしてない。グラス2杯ほどである。
グラス2杯ぐらいは体にいいことが統計的に証明されているので実行している。
今はいろんなことをしている。
玉ねぎの皮はふつう、捨ててしまうと思う。
でもそれはもったいないのだ。
以前も書いたように、我々の体には長寿遺伝子というものがある。
ところがほとんどすべての人は(95%ぐらい)その遺伝子が活動しておらず眠ったままだ。
これを活動させるには25%ほどのカロリー制限か、定期的な断食などが必要だといわれる。
断食はできる人とできない人がいるし、25%ものカロリー制限はそんなに簡単なことではない。だからこそ5%ぐらいの人の体の中でしか活動していないのだ。
ではどうすればいいかというと、100%ブドウジュースかブドウを皮ごと食べる、赤ワインを一日2杯ぐらい、玉ねぎの皮を摂取すること、ナッツやアーモンドを皮ごと食べると活性化するかもしれないという。
僕は最近、食塩のついてない皮付きのアーモンドをスーパーで買ってきて食べている。
皮付きということろがミソで、玉ねぎにしろ、ナッツ、アーモンドにしろ、リンゴにしろ、皮のところに最も体にいい成分があるという。
ところが玉ねぎの皮は調理のしようがない。
でも調理できなくてもお茶にして飲むという手があるし、サプリメントも発売されている。
僕がもっぱらやっているのは、お湯で煎じる方法だ。

このようにして土瓶に皮と水を入れて1時間ほど煎じて、一日1杯ほど飲んでいる。
もう一つの健康法は、またまた玉ねぎとショウガを使ったもの。
玉ねぎとショウガをざく切りにして、黒酢に1週間ほどつけて一日大さじ2杯ほど飲んでいる。

これに加えて(笑)オリーブオイル(できれば無農薬・オーガニック)を一日大さじ1杯いただいている。
これはアメリカの研究で証明された方法で、心臓病を予防する効果があるという。
このほかにも定番であるケフィアヨーグルトにラブレ菌を入れて発酵させて愛犬とともに食べている。もちろん別々の皿でだが。
ほかにもやりたいことはあるのだが、どうしても財布と相談しなければいけないので、あきらめなければならないものも多い。
僕は医者嫌いなうえに、自分の母親を明らかな医者の誤診で失った。
その経験から、自分の命を海のものとも山のものともしれない他人(医者)にゆだねるということ自体が大きなリスクだと思うようになった。
ただし、もちろん名医もいるだろう。いるにしても、よほど普段から情報を集めてでもいない限り、どの病院にいるかなんてわからない。
また、世間で既に有名になっている医者にはそう簡単にはかかれないかもしれない。
それと、もっと根源的なこととして、僕は西洋医学はあくまでも対症療法であり、病気を発生させた根本・本質的原因を治療するものではない、という考えを持っている。
むしろ、病気の本質的根本原因を治療することによりフォーカスしている治療法は東洋医学だと思っている。
どちらが優れているかということを言っているのではない、役割分担が重なる部分を持ちながらも、そのアプローチの仕方、むずかしくいえば哲学が違うとおもう。
西洋医学というのはだから、発病してからの医学であり、一方東洋医学というのは「未病」という漢方の言葉にもあるように、発病させないための医学であり、発病してしまった場合は、症状をいやすだけでなく、その症状を生み出しているもっと根源的な「本質」、いいかえれば、身体全体の健康を維持・制御しているメカニズムの「ゆがみ」をいやしていく医学だと思う。(このことは西洋医学ではまだその全体像をとらえられておらず、ようやくその端緒についたばかりだというのが僕の印象)
このことから、僕は発病してしまってからあたふたするのではなく、まず発病させないということに注力したいので、東洋医学や自然療法により強い関心を持っている。
僕の自然療法に対する強い関心とその実践は、すべてこの考えから生まれている。
自分のみは自分で守ることがまず肝要である。
自分の命を、どれほどの技能・経験を持っているかわからない人にゆだねるような状態に、まずならないことが大事だと思う。
そして普段から予防に心掛けて、それでも病気になったら、そのときは医者に(よき医者にあたるように幸運を祈りながら)お任せするしかない。
徳川家康も健康には気を使っていて、自分で漢方薬を調合して飲んでいたという。
だからこそ人間50年といわれていたあの時代に、70有余年という長寿を全うできたのだろう。
彼は知っていたのだ、天下をとれるかどうかは、秀吉よりも長く生きるかどうかにかかっていると。
僕の好きな五木寛之も医者嫌いで知られている。
レントゲンを最後にとったのが、大学入試の時だという!
そして彼も、健康法に関しては人並み外れた知識を持ち、それを実践している。おかげで80歳を優に超える今も、歯医者以外は一度も医者にかかっていないという。
おそるべし!である。
そしてそれと同時に(たぶんどれだけ生きるか以上に)大切なのが、人生の質 Quality of Lifeだろう。
僕はこれには決まった答えはないと思う。
なぜならそれはその人その人それぞれの中に独自のものが刻まれているはずだからだ。
僕の母は抗がん剤の副作用に耐えきれず、途中から抗がん剤を飲まなくなった。
僕は飲んでほしかったが、その副作用のつらさはあくまで母にしかわからない。それを第三者が飲めと強要できるものではないから、それを受け入れた。
母も覚悟の上で決めたことだろう。
たとえ少しだけ長く生きることができたとしても、それが毎日不快な嘔吐感やその他の苦しみとともにある毎日であれば……
まさにQuality of Life人生の質の崩壊である。
ひとつだけいえることがあるとすれば、それはどれだけ個々の人が「自分自身に、そして自分の家族に誠実に正直になれるか」ということじゃないだろうか。
抽象的になって申し訳ないけど…