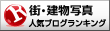フェルメール東京展も2月3日で終幕を迎えるので、一度見たのだが、再び見ることにした。
何よりもあれだけの規模のフェルメール展は日本ではめったにないことと、再び巡り合える機会のない作品もあるかもしれないので一生後悔しないようにしっかりともう一度見ておきたいと思った。
場内でたちどまらないで前列の人は見終わったら後ろの人に譲るためいったん後ろに下がってくださいと、案内役の女性が何度もおっしゃってくれていた。
しかし、それがあまり功を奏さない一番の要因はやはりあの音声ガイドだろうと思った。一つの絵ごとに説明が流れるのでみんなそれが終わるまではその絵の前に張り付いて動かない。当然動きがそこで停滞する。
音声ガイドを必要とするひとが圧倒的多数なので、やめてほしいと迄は言わないが、せめてもう少し改善策はないものかと思う。
特に今回は入場料が高く設定されていて、全員が音声ガイドを借りられるところを見ると、すでに入場料に音声ガイド料が含まれているのだと思うが、僕のようにそれを聞かないものにとっては余分に払う必要のない料金を払わされているわけでそれが不満だった。
まぁ、それはともかく、再びいってよかった、というのがしみじみとした腹の底からの僕の想いである。
今回、僕のもっとも好むフェルメールの三点(真珠の首飾りの女、リュートを調弦する女、手紙を書く女)が室内中央に並んでかけられていて、これを配置した人と僕の好みが奇しくも一致したのか、それともただの偶然なのかはわからないが、いずれにしても、そのことがうれしかった。
というのも、フェルメールの絵が集められた部屋で、ほぼ殆どの時間を大きく移動することなく1カ所に立ったままで鑑賞できたからだ。
見ていて思ったのは、これがいま実際に僕の眼で見ていなければ、これらの絵がこの世に本当に存在しているとは信じられないだろう、ということだった。
この言葉で僕の感動がどれほどのものだったかわかっていただけるだろうか……
何度書いても書きすぎることはないのであえて書くが、今まで何枚も(それが絵画以外のものなら何個も)美術品と名の付くものを僕の生涯を通じてみてきたが、その全体験、全邂逅の中であれほどのレベルのものは……正直見たことがない、すくなくとも西洋美術の範疇に入る作品では。すくなくとも現在発見されているものの中では最高峰といってほぼ間違いないと信じる。それほどまでの体験だった。
前回の記事の中でも書いたのだが、とにかく際立っている、その作品群の質の高さが。
ちょうどフェルメールの絵と一緒に同時代のオランダ絵画の作品が置かれているのだが、たいへん失礼な表現であることを承知の上で申し訳ないと思いながらあえて書くが、それらの絵はフェルメールの作品群がいかにずば抜けたものであるかということを示すために置かれているとしか思えないほど、フェルメールの作品群の質の高さが印象に残った。
それらの違いはどこから来るのか、もちろん技量の高さは言うまでもない、しかしながら、それだけではないことも明白である。
あれらの作品群が内在的に持つ精神性の際立った高さ…技量が他の画家と比べてずばぬけて卓越して見えるのは、実際には技量の問題というよりも、フェルメールという人物が持つ精神・魂の質、在り方ゆえではないか…そして彼には奇跡的にそれを視覚的に表現するすべ(絵画的技量)が備わっていた、というほうがよりしっくりとくる。
本当に大切なものは眼には見えない、といったのは星の王子様だが、実際に自分の目の前にありながら、僕はどこかで自分がいま見ているものは実際には眼に見えないものではないか、それが何らかの奇跡的な力の影響で見えているのではないかとずっといぶかっていた。しかし、どんなに目をしばたいてもそれはそこにある。言い換えればそれほどまでに「精神的な体験」だった。この不思議な、神秘的な恍惚感に会場内で満たされていた。
こういう経験は人生でめったにできるものではない。少なくとも僕の人生でもほんの数回ほどしかない。
本当に行ってよかった。見てよかった。
フェルメール展はこれから大阪に移っていく、そしてまた、海の向こうのそれぞれの所有者のもとに帰っていく。