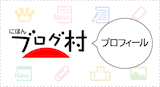2017年1月11日 水曜日
釣りの続きである。かくし玉である。
マタナゴ(ウミタナゴの亜種)である。


狙い通りに釣れたわあ!
こういうときは気分がいいねえ。
実は、おじさんにもらったアミエサが余って仕方がなかったのである。
使い切ろうにもなかなか食わんし・・・・・・壊れかかった通路をたどり、岩礁帯の突端に出てみる。
そこは潮の満ち引きに関係のない突然の落ち込みになっとる。
幸い最干潮の時間とも重なり潮もとまっとる。
何度かエサの一部だけ食い散らかされた後にウキがスーッと沈んだのである。
手応えも十分楽しめたわ。
タナゴ仕掛けはタナさえ届けば海でも十分通用するな。
なんせ「海でののべ竿釣り」自体が40年ぶりじゃもん、分からんことばかり。
分かったのは仕掛けも針もちっちゃいので「あまり警戒されんで食いついてくれる」ということと
めったな所で「そこまで届かん」ということである。(届かんのかいっ!)
やりとりは「めちゃくちゃ楽しいがな!」と付け加えておこう。
ちなみに、このウミタナゴ、2007年にいくつかの種・亜種に分けられている。
赤みを帯びているものを別種としてアカタナゴに、
青みを帯びているものを別亜種としてマタナゴに、である。
また、ウミタナゴという名は「体型が淡水のタナゴ類に似ている」ことから付けられたという。
似とるかなあ?
強いてあげればウロコの感じがゼニタナゴに似とらんでもないけど・・・・・・。
スズキ目とコイ目。胎生と卵生。
生まれも育ちも体つきもまったく違うけんねえ。
「タナゴ釣りが好きです」というとしょっちゅう誤解されるんは困ったもんである。
釣りの続きである。かくし玉である。
マタナゴ(ウミタナゴの亜種)である。


狙い通りに釣れたわあ!
こういうときは気分がいいねえ。
実は、おじさんにもらったアミエサが余って仕方がなかったのである。
使い切ろうにもなかなか食わんし・・・・・・壊れかかった通路をたどり、岩礁帯の突端に出てみる。
そこは潮の満ち引きに関係のない突然の落ち込みになっとる。
幸い最干潮の時間とも重なり潮もとまっとる。
何度かエサの一部だけ食い散らかされた後にウキがスーッと沈んだのである。
手応えも十分楽しめたわ。
タナゴ仕掛けはタナさえ届けば海でも十分通用するな。
なんせ「海でののべ竿釣り」自体が40年ぶりじゃもん、分からんことばかり。
分かったのは仕掛けも針もちっちゃいので「あまり警戒されんで食いついてくれる」ということと
めったな所で「そこまで届かん」ということである。(届かんのかいっ!)
やりとりは「めちゃくちゃ楽しいがな!」と付け加えておこう。
ちなみに、このウミタナゴ、2007年にいくつかの種・亜種に分けられている。
赤みを帯びているものを別種としてアカタナゴに、
青みを帯びているものを別亜種としてマタナゴに、である。
また、ウミタナゴという名は「体型が淡水のタナゴ類に似ている」ことから付けられたという。
似とるかなあ?
強いてあげればウロコの感じがゼニタナゴに似とらんでもないけど・・・・・・。
スズキ目とコイ目。胎生と卵生。
生まれも育ちも体つきもまったく違うけんねえ。
「タナゴ釣りが好きです」というとしょっちゅう誤解されるんは困ったもんである。