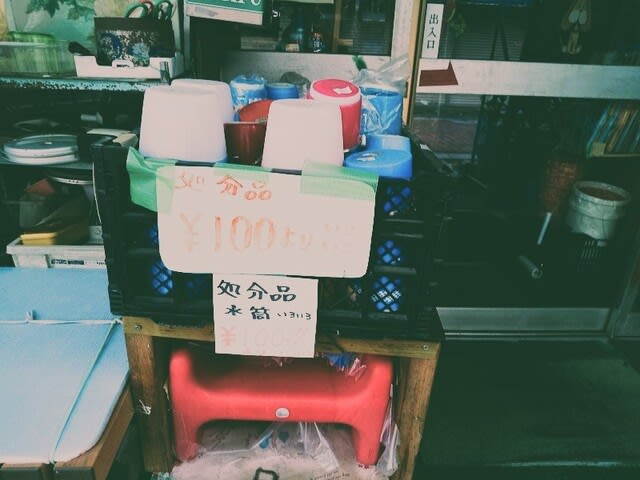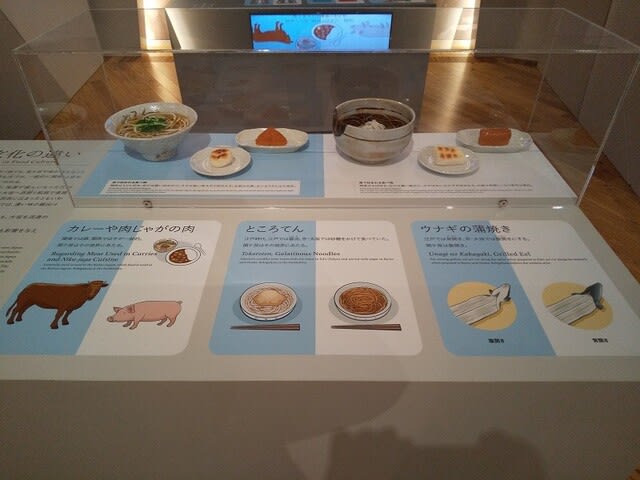<はじめに>
先日、旅をした。
行先は兵庫~京都、かつて播州・但馬・丹波・丹後と呼ばれたあたり。
これから数回に亘り、旅の様子を投稿したい。
個人的な視点で綴る記録だ。
冗長や偏りを感じたりするだろうが、よろしかったらお付き合いください。
そして、何かしら共感や関心を呼び起こし、思いを致してもらえたなら嬉しい限りである。
ではいざ---。
<本 編>
最初の訪問地は、兵庫県南部の播州平野ほぼ中央に位置する加西市(かさいし)。
人口4万人あまりの市域は、東西12km強、南北20km弱。
瀬戸内式気候に属する。
市の中心部を流れる川の西、鶉野(うずらの)台地には、昔、飛行場があった。
第二次世界大戦時、戦局が悪化しはじめた昭和18年(1943年)、
パイロットを養成する「姫路海軍航空隊」の基地が開設されたのだ。
訓練飛行に加え、ランウェイに隣接した工場で組立てた機体の試験飛行も実施された。
--- その傍に、加西市地域活性化拠点施設「soraかさい」がオープンしたのは2年前である。


館内には、戦闘機の“実物大模型”を展示。
前述「川西航空機 姫路製作所 鶉野工場」で組立ていた「紫電改(しでん・かい)」と、
パイロット訓練に用いられた「九七式艦上攻撃機」だ。

「紫電改」は、紆余曲折を経て大空に辿り着いた傑作機。
開発史は、海軍が飛行艇や水上機に強い川西航空機に対し、
飛行場が造成できない島嶼部(とうしょぶ)で運用する水上戦闘機を求めたことに始まる。
高すぎる性能リクエストに苦しみながら「強風(きょうふう)」を完成させたが、
時間を要したため、既に他社の機体が採用されてしまっていた。
ならばと「強風」をベースにした陸上局地戦闘機「紫電(しでん)」を製造。
急ごしらえが災いしたのか--- 難点と利点、優と劣が共生する同機の評価は芳しくない。
しかし、川西のエンジニアたちはあきらめない。
技術的改良を加え、生産しやすさ資材節約の観点から部品数を大きく減らし簡略化。
名機「紫電改」が誕生した。
・2000馬力級エンジンが叩き出す最高速は、時速630km。
・操縦者を守る防弾装備、20mm機関砲4門の重武装。
・目まぐるしく変化する戦闘中の機体に最適な揚力を与える機構、自動空戦フラップ。
これら高性能を以て強力な米機と互角に渡り合い、
B29による本土空襲が激しさを増す大戦末期、日本の防空を担った。

上掲画像の天井から吊り下げられた機体「九七式艦上攻撃機」は、
日本海軍初の全金属製の低翼単葉機。
昭和16年(1941年)12月8日、鮮烈なデビューを飾る。
日本海軍機動部隊によるハワイ・真珠湾への奇襲で、
米太平洋艦隊に対し魚雷攻撃を仕掛け大打撃を与えた。
ちなみに「トラ・トラ・トラ(ワレ奇襲ニ成功セリ)」の暗号電は、
この機体から打電されている。
大戦初期は戦場各地を飛び回るも、速力不足などから戦争半ば以降は主役の座を降り、
姫路海軍航空隊では、訓練機材として転用されていた。

だが、戦局悪化に伴い「九七艦攻」は、再び第一線に駆り出されることになる。
昭和20年(1945年)2月、姫路の練習航空隊は実戦部隊に再編。
特別攻撃隊「白鷺隊(はくろたい/姫路城別名・白鷺城から命名)」として、鹿児島へ進出。
“時代遅れの艦攻”は800kg爆弾を抱いて、若者たちと共に沖縄の空に散った。

「soraかさい」前に、白鷺隊、飛行場建設について刻んだ平和祈念の碑が建つ。
また滑走路跡周辺には、戦時遺構が点在。
ざっと紹介していきたい。


【機銃座跡】
滑走路を越え、左右に田園を眺めながら歩くうち機銃座跡の囲いが視界に入る。
低空から侵入してくる敵機に対する対空機銃。
飛行場周辺には5ヶ所設置された。
温室のようなガラス張りの中には実物大の対空機銃模型が展示。
平成17年(2005年)公開の映画『男たちの大和』の撮影に使用されたものだ。

【巨大防空壕跡】
上部が草で覆われ、遠目には小さな丘のように見えるのはカモフラージュのため。
地下に広がる、奥行き14.5m、幅5m、高さ5mの空間は発電施設として使われていた。
そこを利用し、令和2年から巨大防空壕シアターを開設。
CGを交えた映像で「白鷺隊」隊員たちの遺書を公開しているとのこと。
入場無料で、ガイドによる説明、映像の視聴が可能ながら、事前予約制で日程限定。
あいにく僕の訪問時はタイミングが合わなかったのが残念でならない。

【防空壕跡】
コンクリート製の強固な防空壕。
内部は30名ほどが入れるスペースで、換気口も設けられていた。
竹藪に覆われた2つの出入口の中は凸型に屈曲して繋がり、爆風を防ぐ構造である。


【爆弾庫跡】
見るからに頑丈そうな分厚い1mコンクリート造。
アーチ状の天井部はショックに強く、前面には爆風から格納品を守る土堤。
強度は、今尚健在との事だ。

姫路海軍航空隊鶉野飛行場が、歴史上に存在した期間は僅か3年に満たない。
甲子園球場およそ70個分に相当する広大な敷地にはパイロット以外にも、
整備、兵科、運用、主計、航海、機関、通信、工作、兵器、砲術、医務など、
多岐に及ぶ任務をこなす兵士たちがいた。
全長1200m、幅45mの滑走路跡に佇み、
彼らの息遣いを胸いっぱいに吸い込んだ時、
僕の心は束の間---79年前の夏の空へ飛んだ。
<次回に続く>