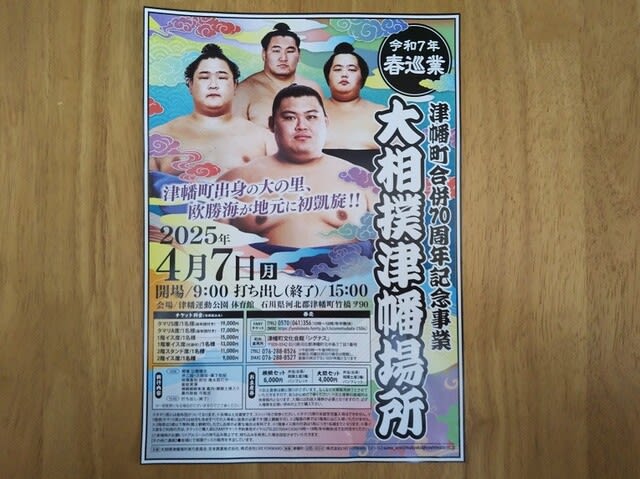津幡町で見聞した、よしなしごとを簡潔にお届けする不定期通信。
今回は、以下の1本。
【凍晴の街歩き。】
今投稿の内題に選んだ「凍晴(いてばれ)」は、冬の季語である。
2月の記事には相応しくないが、まさにピッタリ。
放射冷却によって凍りつくように寒い快晴の今朝、
久しぶりに小一時間の散歩を楽しんだ。

最初の写真はご近所の歩道の様子。
あちこちに雪が融け残っている。
無理もない、ほんの1週間前は一面の雪景色だったのだ。
左手前、薄氷がお分かりになるだろうか?
路面のちょっとした窪みに張った氷は、一種のトラップ。
気付かずに勢いよく踏み出し滑ったりしたら、転倒~ケガに繋がりかねない。
故に、歩みは自然とスローテンポに。
また、不安定な一本足の滞空時間を短くするため歩幅は狭くなる。
安全第一。僕は慎重に津幡川を目指して進んだ。

対岸から「弘願寺(ぐがんじ)」を望む。
大屋根の下には、甍を滑り落ちて出来上がった堆い雪の山。
流れる水は勿論冷たい。
もし、僕が落ちたりしたら1分と留まってはいられないだろう。
川面を覗き込んでも観止める魚影もない環境だが、ここを棲み処にする生きものがいる。

川がS字カーブを描き淀む一角には、大勢の水鳥たち。
羽毛が断熱材として空気層を作り、冷たい外気温から守っているのに加え、
彼らは体内に「ワンダーネット」という仕組みを持つ。
動脈に静脈が絡まった構造によって動脈が静脈を温める。
外気(水)の影響で冷えた血液が、体の芯まで冷やしてしまうのを防いでいるのだ。
まったく、自然の偉大さには叶わないと思う。

自然の偉大さ--- 言い換えるなら強大さの現れの1つが「地震」だ。
清水八幡宮の第一鳥居は、あの揺れによってダメージを被り撤去された。
案内看板にある石材「赤戸室石(あかとむろいし)」は、
金沢市の郊外の戸室山周辺で採掘されている青・赤色系の安山岩。
硬質で耐火性・耐凍結性に強いのが特徴で、金沢城の城壁などにも使われている。
看板背後、同材らしきの石灯籠も無傷ではいられなかったのか?
竿(さお)に補強のためと思われる部材を発見。
この分野に疎い僕の杞憂に終わればいいが、これからも佇んでいて欲しいものだ。

さて、寒いとはいえ、季節の巡りは春に差し掛かっている。
梅の一輪でも綻んでいないかと考え、思い当たるところを訪ねてみたが開花は見つけられず。
やはり、今、眼福を与えてくれるのは、やはり冬の季語である花「山茶花」だ。

山茶花や 土気はなれて 雪のいろ - 加賀千代女
<津幡短信 vol.128>