最近、個人的に何かと気になる話題の一つが「ウクライナ情勢」だ。

ウクライナの位置は、日本から遥か9000km。
国の東にロシア。
西にポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバ。
北にベラルーシ。
南には黒海を挟んでトルコがある。
国土面積は60万平方キロメートル(日本の1.6倍)。
人口は4200万人あまり(2021年現在)。
首都は、キエフ。
国土の大半が肥沃な平原、高原地帯。
山岳地帯が少なく、古くから農業が盛ん。
一方、国土が平坦なため、攻めやすく守りにくい。
紀元前から、何度も為政者が入れ替わってきた。
現在の姿になる以前は「ソ連邦」の一員。
簡潔に述べるなら、ロシアに支配されていた。
ソ連崩壊後、ウクライナは独立したが、
「親ロシア派」VS「親EU派」で、今も国内は二分しているという。
そのウクライナとの国境周辺地域で、ロシアが軍備を増強して3ヶ月あまり。
いよいよ軍事侵攻が始まるのではないかと懸念されている。
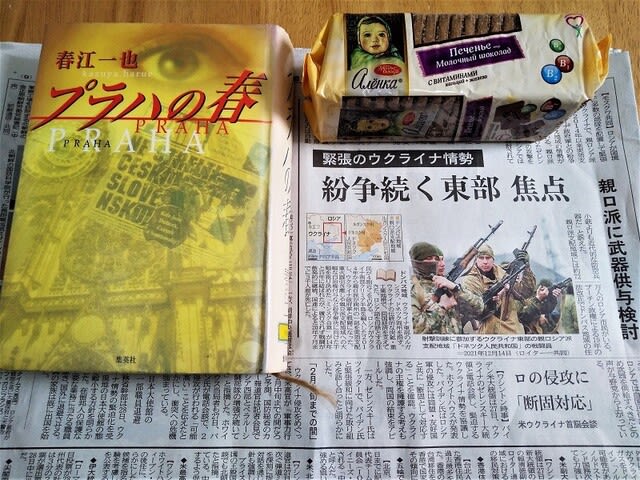
最近、東ヨーロッパから届く緊張感漂うニュースを耳すると、
ある小説を思い浮かべてしまう。
それは「春江一也(はるえ・かずや)」著、「プラハの春」という。
物語の舞台は、東西冷戦下のチェコスロバキアの首都プラハ。
主人公は、在プラハ日本大使館職員の青年「堀江亮介」。
ヒロインは、東ドイツ出身の美女「カテリーナ」。
2人の恋愛と、歴史に翻弄される国家の激動をメインに描いた大作で、
僕は大変気に入っている。
--- 小説について詳しくは別の機会に譲りたい。
やがて不定期イラスト連載「手すさびにて候」で取り上げようと考えている。
今回は、作品のタイトルでもある「プラハの春」の話だ。
1968年当時、彼の地では変革運動が起こっていた。
低迷した経済、硬直した体制の立て直しに向け、
「社会主義の枠内で社会・政治制度の民主化」を目指したのだ。
それまでの重苦しさから解放される比喩として、
明るい季節を当てはめ「プラハの春」と呼ばれた。
試みは上手く行くかに見えた。
しかし、ワルシャワ条約機構軍(ほゞソ連軍)の軍事介入によって頓挫。
わずか8ヶ月の短命に終わる。
ソ連の言い分はこうだった。
「社会主義陣営の国が一つでも危機に陥ると、影響は全体に及ぶ。
そのため他の国家は無関心でいることはできず、
陣営の利益を守るために一国の主権を乗り越えることができる」
要は“飼い主の忠犬であれ!”ということ。
忠義を守らない犬には、容赦なくムチを振るう。
この考え方は、ソ連の対東欧政策に一貫している。
現在、ウクライナに牙をむいているのはロシア。
ソ連ではないが、本質に変わりはないのかもしれない。
今頃、キエフは憂いの虜(とりこ)になっているだろう。
イワン共は来るのか、来ないのか。
54年前のプラハに似て、戦々恐々としているに違いない。
(※上掲画像は、書籍とロシア製ビスケットと新聞記事)

































