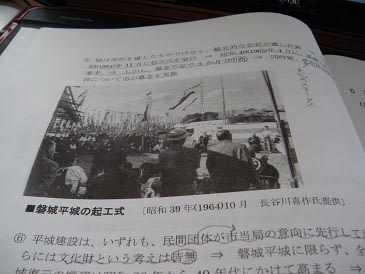知人から
いただいた里芋を洗い干しました。
煮物にしておいしくしていただきました。
今から221年前の1799年(寛政十一年)に
長谷川安道さんにより書かれて
私達「なるほど歴史塾」で現代訳にしました。
寛政十一年農家年中行事・・・長谷川安道著より
一.三月三日の雛事とは、
子供の節句として、草もち、白酒、あさつきや
乾し大根のなますなどは、第一の献立である。
その他、いろいろな備え物は
分量にしたがって思い思いのおくりものとしては
内裏雛、小山人形行列の箱入りなどあるいは、
菓子・せんべい等見つくろってやるのである。
一.桃、桜の花盛りにて、面白おかしく花見、遊山など百姓は、
そんな風には、やるものではない。
一.今月の土用は、節分より七十五日目になる。
この時期、稲の種は種井から揚げ昼は外に出し、
夜は、内に入れて、むしろ、こもをかけてよく萌して蒔くことである。
ただし萌しすぎては風に寄せられて悪い。そのかげんが大切だ。
なわしろは、
よく土を細かくして、よく肥しを入れて、なわしろを広くして、
種をまばらに播き、稲苗を太らせて植えれば稲はよくできる。
なわしろを狭くして、種を播けば苗はやせ、風に吹き折られてしまう。
(そうすると)水が腐り、心葉が萌えても青虫に食われ、稲ことごとくおくれて、
秋風にあっては
青米になり、、納米、飯米にも甚だ悪くなる。
よくこれを考えて、蒔き物・植物は、大切にしなければいけない。
※土用:立夏・立秋・立冬・立春の前のそれぞれ十八日間をいう。
一.今月は、農(繁期)中の米・麦をついたりして、
蓄えておく心掛けが必要である。
と農家の心がけを書いています。