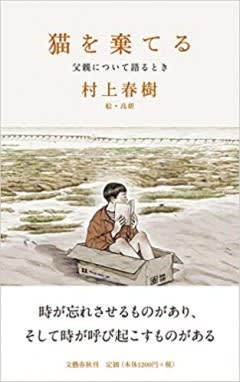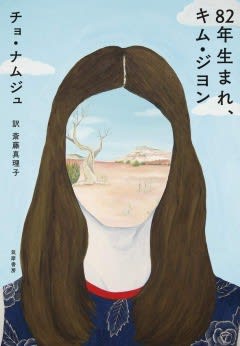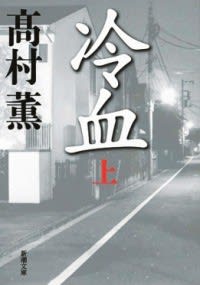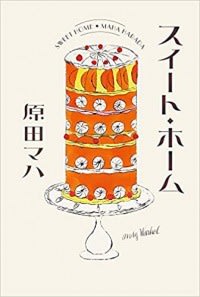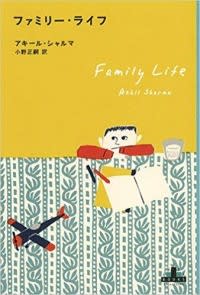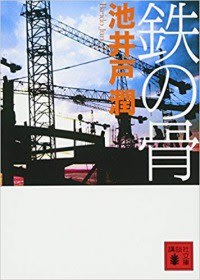少年と犬
第163回 (2020年) 直木賞受賞作。ある一匹の犬と出会った人たちの運命の物語が、バトンのようにつながっていく連作小説集です。

馳星周さんはお名前は存じ上げていましたが、作品を読むのは本作が初めてです。そしてなんとなく既視感のあるお名前と思ったら、ファンである香港の俳優、映画監督の周星馳さんのお名前を逆にしてペンネームにされているそうです。
馳さんは、もともと裏社会に生きる人々を題材に描いたノアール小説がご専門のようで、それで私とは接点がなかったんだなーと納得しましたが、何故に犬の物語を??と思いましたら、馳さんは大の犬好きでいらっしゃるのだそうです。
***
読んでみると、犬が主人公といっても、そこに甘く感動的な物語の展開はありません。ひとつひとつの小説に登場する人たちは誰もがやっかいな問題を抱えていて、犬=多聞と出会うことで、幸せな結末を迎えるわけではないのです。
犬が主人公ということで、感動を求めて泣く気満々?で読み始めると、ある意味裏切られるかもしれません。この小説では、犬=多聞が旅先で出会う人々が、ことごとく犯罪と結びついていて、この作品が実はまぎれもないノアール小説であることに気づかされます。
ただ、どこにでもいるような人々、ふつうに生活していて起こりうるできごとが書かれているわけではないので、私にとってはなかなか共感しづらい部分がありました。
***
6つの連作の中で、私が一番気に入ったのは「老人と犬」です。この物語には裏社会の人が登場しないので、そういう意味で私にはとっつきやすかったのかもしれません。
ラストに向けては結末を予測しながらはらはらと引き込まれ、私は「ごんぎつね」を思い出しました。