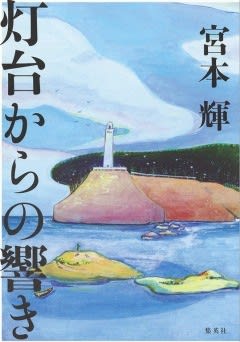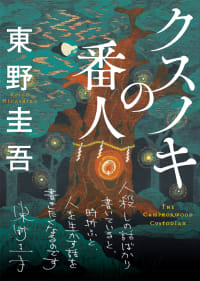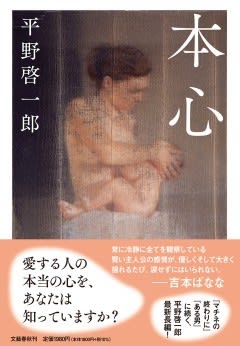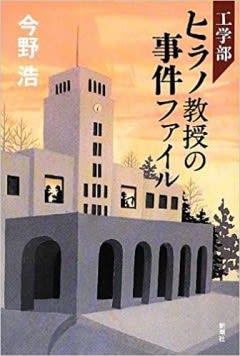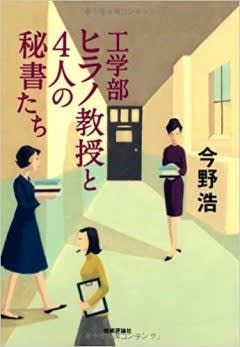1986年に刊行された、ハンガリー出身の作家アゴタ・クリストフのデビュー作です。

アゴタ・クリストフ 堀 茂樹 (訳) 「悪童日記」
Agota Kristof “Le Grand Cahier”
感想を書くのがだいぶ遅くなってしまいました。本作は、9月に反田さんのコンサートに行った際、オペラシティの熊沢書店で購入しました。気になっていた映画の原作だったので、まずは小説を読んでみようと思い、手に取りました。
***
アゴタ・クリストフは、1956年に社会主義国家となった母国ハンガリーを捨て、西側へ亡命しました。本作は彼女のデビュー作で、フランス語で執筆されています。
少年たちの目を通して描かれる、戦争を生き抜くサバイバルとも言うべき作品です。ただし、主人公の少年たちを純真無垢でいたいけな存在だと想像すると、良い意味でその期待を裏切られるかもしれません。
***
主人公である「ぼくら」は、子どもでありながら、子どもではない。戦争という大人たちの都合で引き起こされた悪行の中で、大人たちの弱さやずるさを冷静に見抜いているように感じました。
ストーリーはまったく異なりますが、私は古い戦争映画「禁じられた遊び」を思い出しました。(訳者解説によれば、本作を読んでジュール・ルナールの「にんじん」に通じると感じる読者が少なくないそうです。)
***
最初は「なんて意地悪なおばあちゃんだろう!」と思っていましたが、小説を読み終える頃には、実はこの作品の中で最もまともな大人だったのではないか、と感じたのがおもしろい発見でした。
主人公のふたりが、周囲の大人たちを冷ややかに見据えつつ、彼らを非難するわけでもなく、自分たちの境遇を悲しむこともなく、ただ生き残るために感情を排除し、頭脳と身体を鍛え続ける姿には圧倒されました。
***
また、この日記が「作文の内容は真実でなければならない」という、少年たちが決めたルールに基づいて書かれている点も、興味深かったです。
でも私は、ただ真実だけを記したとしても、どの部分を切り取り、どのように表現するかはその人次第で、それによって無意識に心の動きを描くことができる、と思いました。それに、読む人がどう捉えるかによっても、解釈は変わりますよね。
***
本作には暴力、差別、貧困、そして性描写も容赦なく描かれています。そのため、私は「よくぞこの小説を映画化したなあ」と驚きました。そして、映画に出演した子役たちへの影響も気になりました。
私は小説だけで十分満足したので、読み終わった時には「映画は見なくてもいいや」と思ったのですが、映画は映画で見た方たちの評価が高いので「やっぱり見てみようかな」と心が動いています。