山梨県・日本中部南東の県。縄文大泉天神遺跡、弥生時代の韮崎宮の前遺跡、古墳時代の甲府加牟那塚古墳、672年の弘文の「壬申の乱」甲斐人騎馬兵の活躍と甲斐黒駒神馬献上、甲斐国国分寺建立、864年に富士山大爆発が・・・。
県は、甲府盆地を中心と富士川流域を国中地方と呼んだ。
大菩薩峠・笹子峠・御坂山地の東部を(桂川・相模川上流)郡内地方と呼んだ。郡内は、大月・都留地域に小山田氏で、国中の武田氏臣従しながらも
領地を守った。
国中は、南アルプスの山々に囲まれ、郡内と地形も気候も自然条件は異なり、交流にも不便、そのため習慣・風俗・伝統など違いが多い。
国中は、富士川水運・駿州街道(国道52号線)で静岡県・長野県と交流・郡内は関東地方が進んだ。
甲斐の武田氏は、暴れ川の富士川上流の釜無川や、笛吹川の治水に成功させ、流域の水田開発に大きく貢献したと云われ、武田氏から徳川氏とうけつがれ、金の採掘やいろいろな産業を生んでいる。「金・紙など」
「甲府市」 県中央部・市名は、武田信玄の父「武田信虎」が、石和から市内府中市に居館を移し、甲斐の国の府とした。
市は、南笛吹川から北金峰山まで、東西6km・南北32kmを占めている。

甲斐の国は、古代国府(現東八代郡御坂町国衙)武田氏躑躅ヶ崎に館を構え「甲府」と呼んだことに発する。
静岡の駿府・山口の防府のような意味はない。その後「武田勝頼」が、韮崎に新甲府の「新府城」を築き、武田氏滅亡後「舞鶴城・公園」が築城され
武田氏の旧域地は、古府中・上府中と呼ばれている。

「韮崎市」 県北西・峡北地方の中心都市。甲府盆地の西部。
北東に、茅ヶ岳南西麓・南西部は、南アルプスで、地名は、八が岳裾野丘陵「七里が岩」の台地が「ニラ」の葉のように突き出ている・また「ニラ」が群生する突端の意と云われる。地理的には、甲州街道、佐久往還と駿信往還の分岐点・釜無川と塩川の合流点で「韮崎宿」を起源。
信州諏訪藩の年貢米・塩・海産物の中継地として発展した。
江戸初期は、富士川水運も開かれ、1905年の中央本線開通で活気を失ったが、大正8年バス運行で峡北地方の中心にもだった。
今では、先端技術産業の工場が進出・観光でも南アルプス・奥秩父山地・八ヶ岳の基地に。

「暴れ川・御勅使川」
県西端の山間部である南巨摩郡早川町と南アルプス市の境にある巨摩山地のドノコヤ峠(標高1,518m)東麓に発し、北流して山間部ではV字谷を形成南流してきた金山沢川を合わせて東流し、山間部を過ぎて盆地西部に南北10km、東西7.5kmの広大な扇状地(御勅使川扇状地)を形成。
左岸の韮崎市と右岸の南アルプス市の境界を流れ、支流の割羽沢川を合わせ、双田橋付近で盆地北西部から流れる富士川(釜無川)へ合流する。
流路の歴史と変遷は、流路を変化させ、最も北に位置する現在の本流路のほか北から前御勅使川、御勅使川南流路、下今井流路、十日市場流路の5本の旧河道痕跡が発見されている。
古代から流域に水害を及ぼす洪水を起しており、増水時には釜無川を押流して水害は盆地一帯にまで及んだ。
考古遺跡は右岸の微高地上にわずかに大塚遺跡、立石下遺跡、石橋北屋敷遺跡などわずかに古墳時代から古代の集落遺跡が点在する程度であり、氾濫原である流域への定住は遅れていたと考えられていたが、近年は、中部横断自動車道建設に際して百々遺跡などの遺跡群が発見され、遺跡の埋没原因となった流路変遷に関する研究が行われている。
下今井流路は縄文時代晩期から弥生時代前期の最も古いもので、弥生後期から古墳時代後期の十日市場流路、奈良・平安時代の南流路が続く。
15世紀から16世紀初頭には閃光洪水により南流路を埋没させる大氾濫が発生しており、中世には前流路と新流路(現流路)のふたつが本流となる。
この大氾濫で付近一帯に堆積し、砂礫層は近世以降に「原七郷」と呼ばれる干魃地帯となった原因であると考えられている。

「武田信虎」 1494-1574 甲斐国戦国大名、武田信縄の子 甲斐国を統一
居館は府中に移し家臣を集住、娘を今川義元に嫁がせ同盟。嫡男「信玄」に追放される。謀反で今川氏追放・晩年は、武田勝頼の庇護を受け「高遠」で余生を送っている。
武田信虎像

「武田信玄」 1521-73 甲斐の英雄・無敵の名将 信虎の長男。
三国同盟「今川氏・豊穣氏」、越後「上杉謙信」川中島で数度対決、大きく領土拡張する。上洛陣中病死・「甲斐軍艦」残す。
人は城、人は石垣 人は堀 情けは味方 仇は敵なり 信玄像

「甲府城・別名舞鶴城」
甲府城の築城は豊臣大名時代に本格化している。
羽柴秀勝は、天正18年、甲斐を拝領するが、翌天正19年、美濃へ転封されているため在国期間が短く、秀勝時代の甲府城築城に関する史料は天正18年羽柴秀勝黒印状写のみ。
秀勝の次に甲斐を拝領した加藤光泰時代には天正19年、加藤光泰黒印状や年未詳正月14日付加藤光泰書状などの史料が見られ、杣工に動員をかけ甲府城築城を行っており、城内の殿舎の建設も開始されている。
光泰時代に甲府城の築城は本丸・天守曲輪・稲荷曲輪・館曲輪など中心部分が竣工されていたと考えられ、次代の浅野長政・幸長時代にも築城は継続されているが、このころには秀吉の朝鮮出兵が行われ、甲府城の築城は困難にさしかかっており、甲斐では農民の逃散も発生している。
光泰・浅野氏時代には一条小山の一蓮寺をはじめ、寺社の移転も行われている。
江戸時代には甲府藩が設置される。1704年、甲府藩主・徳川綱豊(家宣)が将軍・綱吉の後継者になると、綱吉の側用人であった
柳沢吉保は、甲斐・駿河領国に15万1200石余りの所領と甲府城を与えられる。
翌年4月には駿河国の知行地が替えられ甲斐国国中三郡を支配した。
吉保は大老格の立場であったため甲斐を訪れることはなかったが、家老の薮田重守に対して甲府城と城下町の整備のほか、甲斐国内の検地や用水路の整備、甲州金の一種である新甲金の鋳造などを指示している。
甲府城の整備では新たに花畑曲輪を設置し、楽屋曲輪や屋形曲輪には御殿を建設した。
柳沢氏時代の甲府城下の繁栄を「兜嵓雑記」に、「棟に棟、門に門を並べ、作り並べし有様は、是ぞ甲府の花盛り」と記している。

1603年、徳川義直(家康の九男)が城主、1607年 義直が清洲へ転封。城番制に、1616年、徳川忠長(秀忠の二男、駿府城主)の支城。
1632年、忠長死去。1661年、徳川綱重(家光の三男)が城主、1678年、徳川綱豊(綱重嫡男)が城主、1704年、 綱豊が将軍世嗣として江戸城に入り、徳川家宣と改名・1705年、柳沢吉保が城主、1724年、柳沢吉里(吉保嫡男)が大和郡山へ転封、甲斐一国が幕府領に、甲府勤番の設置。
1727年、甲府城大火。1734年、城内に盗賊が侵入し1400両の公金が盗難される甲府城御金蔵事件が発生・犯人は不明で、当日に博打をしていた甲府勤番士の怠慢が指摘され17名が処罰される。
1742年、高畑村の百姓次郎兵衛が捕縛され、事件は解決、事件は人々の間で関心を呼び、作者成立年代は不明で出版もなされていないが、フィクションを交えた勧善懲悪の物語として構成された実録小説・甲金録となった。1866年、勤番制を廃止し、城代を設置。1868年、明治維新。板垣退助らが無血入城。1873年の明治6年、 廃城となる。

甲府城公園











「武田勝頼」 1546-82 信玄の4男 母諏訪頼重の娘・信長の大軍に攻め込まれ天目山で自害した。
織田・徳川鉄砲隊に大敗。
「武田信繁」 1525-61 信玄に愛された侍大将 信玄忠節を説いた百カ条「信繁家訓」を残している。
信玄画

「浅野長政」 1547-1611 五奉行筆頭・安井重継の子・信長の家臣長勝の養子、秀吉正室ねねの妹を娶る。
若狭ー甲斐国ー朝鮮出兵軍艦を務める。
秀吉が自ら朝鮮渡海すると云いだし・長政は、「最近の殿下の振る舞いは全くおかしい、まるで古狐が化けているようだ・・」と放言、秀吉は激高し、長政は、なおも諫言を続け国内の荒廃を説いたと云う。秀吉は、長政の言を入れて出陣を中止。
家康と長政の囲碁は知られている。長政死後、家康は生涯囲碁を絶ったと云う。甲斐国22万5千石領有
「柳沢吉保」 1658-1714 犬公方に仕えた御用人 徳川綱吉館林藩主時から小姓 甲府15万石城主ー老中まで累進した。
駒込六義園で隠居生活。
柳沢吉保
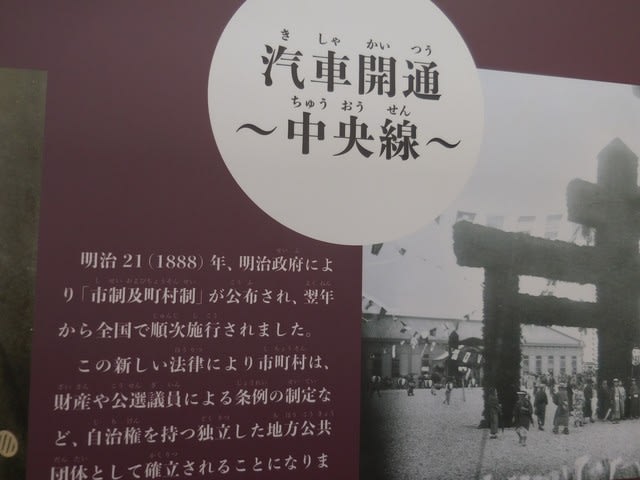
中央本線の貨物車

「太宰治」 1909-48 無頼派作家、青森県津軽の大地主家庭に育つ。
弘前から東大フランス文学ー思い出・晩年・富嶽百景・お伽草紙・斜陽・人間失格・グッドバイなど。39歳で入水自殺。
太宰と妻・美知子は昭和14年,甲府に移り住み新婚時代を過ごした。
8か月という短い期間、昭和20年の甲府空襲で新居は焼けている。
「村岡花子」翻訳家
村岡とモンゴメリとの出会いは、日本を去る宣教師のミス・ショーに手渡された「赤毛のアン」の原書、1908年の冬版であった。。
この出会いは1939年のことで、村岡は灯火管制のもと翻訳を続けて終戦の頃に訳し終え、1952年に三笠書房から出版された
「赤毛のアン」は、読者にも広く受け入れられた。
村岡はその後、アンシリーズ、エミリーシリーズ、丘の家のジェーン、果樹園のセレナーデ、パットお嬢さんなど、モンゴメリの作品翻訳を次々と手がけ、村岡の最後の翻訳作品となった「エミリーの求めるもの」は、彼女の没後、1969年に出版されている。
90年前の甲府の街で

「甲府五山」
信玄公は、広く仏教を信仰し、寺院、僧侶を崇敬保護。中でも禅法を尊び、禅済宗に深く帰依し、その教えを政治、軍政に大きく反映させている。
鎌倉五山にならい、府中五山を定めています。
長禅寺・東光寺・能成寺・円光院・法泉寺の五寺。









