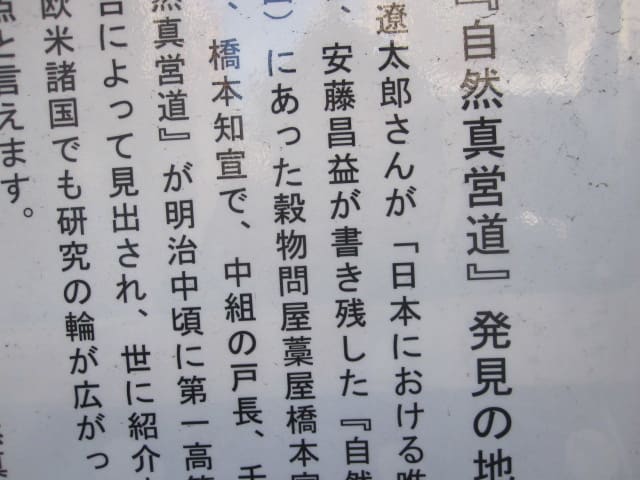「千住宿場町横山家に残る彰義隊士の刀痕」
横山家は、日光奥州街道に面しており、その街道に面する軒を支える柱に刀痕が見られ、柱の現在は、同家のガレージに取り込まれたため、ガレージを囲う塀内になって道路からの外見は出来ない。 柱の材質は檜材、太さは一辺15cm位角で、地上80cm位の位置に認められ、痕跡は2段の打込み傷。
横山家は屋号を「松屋」といい、江戸時代から続く商家で、戦前迄は手広く地漉紙問屋を営んでいたと云う。 現在の母屋は、江戸時代後期の建造であるが、昭和11年に改修が行われ、間口が9間、奥行きが15間あり、大きくてどっしりとした桟瓦葺の二階建てである。
広い土間、商家の書院造といわれている帳場、二階の大きな格子窓等に、一種独特の風格を感じる。
上野の戦いで、敗退する彰義隊が切り付けた玄関の柱の刀傷や、戦争中に焼夷弾が貫いた屋根等、風雪に耐えて来た百数十年の歴史を語る住居。
千住には、旧家や当時の雰囲気を残す医院の建物等が、今でも散見できる。
円通寺

境内に、今でも風雨に晒され「上野黒門」が、片隅にある。
1868年上野彰義隊の戦いで激戦の場となった「上野山本門」いたるところに弾痕や刀傷がのっこて寂しく残っていた。

当時の激しい戦いが生々しく物語っている。

彰義隊は、上野寛永寺を本拠に官軍と戦い、壊滅したが、戦死者200数10人は、みせしめのため放置された云う。

上野公園内の清水寺(官軍の砲弾が展示されている)

清水寺画

上野戦争の画

上野公園内、彰義隊供養塔と墓(薩摩西郷隆盛像の裏に)

これを見た円通寺「仏磨和尚」が上野の山でダビに付し、現在地円通寺に収め墓石死節之墓を建てたという。

上野黒門

彰義隊戦士の墓

墓

墓

墓

「岩倉具視」 1825-83 倒幕運動と王政復古を成し遂げた。
「能久親王」 1847-95 皇族・軍人
伏見宮邦家親王第9王子ー寛永寺山主・輪王寺宮の能久親王、宮様をを朝敵した。
岩倉は、
能久親王宮様と和宮(孝光天皇妹・14代将軍家茂と結婚)宮様・和宮皇族の二人は、戦を避けるため京都入りしたかったが、岩倉は、天皇に会うことを禁じ阻止した。

江戸の治安の組織として武士300名の彰義隊が存在していた。
将軍 徳川慶喜・宮様・和宮様の警護で彰義隊は2000名以上に増えている。

「大村益次郎」 1824-69 長州藩士兵学・蘭学者。
慶応2年幕長戦争で参謀を務め、戊辰戦争で、彰義隊攻撃のあたって激戦を予想し、薩摩兵を配置、西郷隆盛が驚いたと云う。
益次郎は、西郷に「そうです、激戦のため、最強の兵を投入、、」

勝てば官軍・負ければ賊軍(上野戦争から)

旧幕府軍は、すでに大政奉還しており「最後まで天皇に、戦いを避け話し合いを求めるべく親王と和宮をお守りし京に」。
それに対し、岩倉は、倒幕のみと、長州の大村氏を参謀に置き「京に行かせず、敵は、賊軍、、」それが上野戦争であった。

横山家は、日光奥州街道に面しており、その街道に面する軒を支える柱に刀痕が見られ、柱の現在は、同家のガレージに取り込まれたため、ガレージを囲う塀内になって道路からの外見は出来ない。 柱の材質は檜材、太さは一辺15cm位角で、地上80cm位の位置に認められ、痕跡は2段の打込み傷。
横山家は屋号を「松屋」といい、江戸時代から続く商家で、戦前迄は手広く地漉紙問屋を営んでいたと云う。 現在の母屋は、江戸時代後期の建造であるが、昭和11年に改修が行われ、間口が9間、奥行きが15間あり、大きくてどっしりとした桟瓦葺の二階建てである。
広い土間、商家の書院造といわれている帳場、二階の大きな格子窓等に、一種独特の風格を感じる。
上野の戦いで、敗退する彰義隊が切り付けた玄関の柱の刀傷や、戦争中に焼夷弾が貫いた屋根等、風雪に耐えて来た百数十年の歴史を語る住居。
千住には、旧家や当時の雰囲気を残す医院の建物等が、今でも散見できる。
円通寺

境内に、今でも風雨に晒され「上野黒門」が、片隅にある。
1868年上野彰義隊の戦いで激戦の場となった「上野山本門」いたるところに弾痕や刀傷がのっこて寂しく残っていた。

当時の激しい戦いが生々しく物語っている。

彰義隊は、上野寛永寺を本拠に官軍と戦い、壊滅したが、戦死者200数10人は、みせしめのため放置された云う。

上野公園内の清水寺(官軍の砲弾が展示されている)

清水寺画

上野戦争の画

上野公園内、彰義隊供養塔と墓(薩摩西郷隆盛像の裏に)

これを見た円通寺「仏磨和尚」が上野の山でダビに付し、現在地円通寺に収め墓石死節之墓を建てたという。

上野黒門

彰義隊戦士の墓

墓

墓

墓

「岩倉具視」 1825-83 倒幕運動と王政復古を成し遂げた。
「能久親王」 1847-95 皇族・軍人
伏見宮邦家親王第9王子ー寛永寺山主・輪王寺宮の能久親王、宮様をを朝敵した。
岩倉は、
能久親王宮様と和宮(孝光天皇妹・14代将軍家茂と結婚)宮様・和宮皇族の二人は、戦を避けるため京都入りしたかったが、岩倉は、天皇に会うことを禁じ阻止した。

江戸の治安の組織として武士300名の彰義隊が存在していた。
将軍 徳川慶喜・宮様・和宮様の警護で彰義隊は2000名以上に増えている。

「大村益次郎」 1824-69 長州藩士兵学・蘭学者。
慶応2年幕長戦争で参謀を務め、戊辰戦争で、彰義隊攻撃のあたって激戦を予想し、薩摩兵を配置、西郷隆盛が驚いたと云う。
益次郎は、西郷に「そうです、激戦のため、最強の兵を投入、、」

勝てば官軍・負ければ賊軍(上野戦争から)

旧幕府軍は、すでに大政奉還しており「最後まで天皇に、戦いを避け話し合いを求めるべく親王と和宮をお守りし京に」。
それに対し、岩倉は、倒幕のみと、長州の大村氏を参謀に置き「京に行かせず、敵は、賊軍、、」それが上野戦争であった。