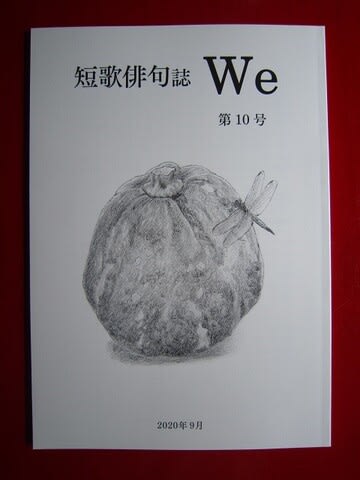大獄の灯や豊年を招く贄 竹岡 一郎
稲妻が豊作につながるように、大量の弾圧、投獄がなされる時代があってこそ、その犠牲がそのまま豊かな次代をかたちづくる。この賑やかな監獄の灯は、そういう収穫への足音であることよという。
元号が変わり、新天皇の即位に伴って恩赦がある。その目線はもちろん上からのものであるが、この句の視点は「贄」である。褒章と恩赦のように、国の隅々にまでその目線は行き渡っているよという微笑ましさを、この「贄」は見返している。
戦後の復興から繁栄へと浮かれている傍ら、『マッチ売りの少女』という別役実の芝居があった。平凡な市民生活に持ち込まれた過去の痛ましい傷が、その虚偽の現実を激しく揺さぶる。そんな寸鉄がここにも「贄」一文字にあると感じた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
昨日から梅雨明けの感があります。
やっと存分にお天道様が拝めます。
夜空もお月様も見上げられます。
稲も無事に育ってほしいです。
We第10号
いま、初校校正中ですが
昨日は昼間頑張ったので、
夜はGYAO無料で日中合作映画「敦煌」(1988年)を観ました。
原作は、皆さまご存知の井上靖の『敦煌』
二時間半もの長編の映画は
最後のクライマックス、西夏によって敦煌が攻められたとき、
敦煌の太守?が収集した文献や経典、美術絵画など
(後に「敦煌文献」と言われる)が
難を避けるために持ち出されて敦煌の岩窟に隠されたいうところに収束。
そのときの名も無き人々の思いの賜物、約4万点が、
その九百年後の1900年頃に発見されたそうです。
その多くは
イギリス、フランス、日本、ロシア、アメリカによって持ち出されたということでした。
中国の宋の時代、
西夏の傭兵は、漢人など異民族の烏合の衆とはいえ、
訳あって漢人の隊長が敦煌の城に立てこもり、
西夏の大将(皇太子)を迎え撃ちに失敗し
打ち取りに突っ込んっで死にに行くところなどは、
日本人の感性によるものだろう。
ウィグルの王女への思いの果たしかたとかも。
味付けは日本料理だったので
見易かった。
戦さの場面が多く
砂漠の中での撮影には俳優さんも裏方さんも
かなり苦労があったのではと思いました。
砂漠やその砂嵐などは映像でみたくらいではその何分の一しか・・・。
佐藤浩一が若くて初々しかった。
西田敏行も佳かった。