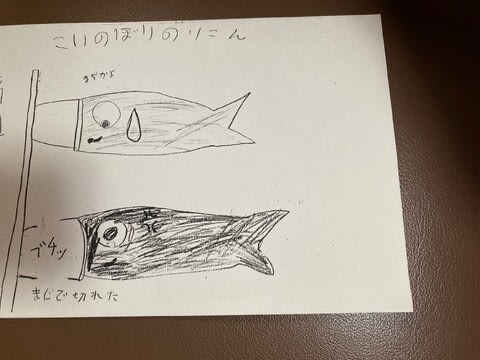<<前号短歌評>>
(2024年11月07日 16時56分)
*北辻 一展・評者
父親も夫も息子も警察官二人の境遇良く似てる
芳樹 景子
「友来る」という連作の一首である。旧友が二人鹿児島にやってきて観光をしながら近況を話す。友人二人とも、父親、夫、息子が警察官だという。面白い家系である。散文になっているところが少し残念であった。警察官一家として、友人二人に共通する面白い点があったはずなので、そのような点に焦点を当てて詠むと歌がより引き立ったのではないだろうか。
鐘の音は楽しみ探しゆくかたち今日の紅葉明日は散りゆく 加藤 朱美
夕方に寺の鐘の音があたりに響き渡る。「楽しみ探しゆくかたち」は不思議な表現で惹かれた。鐘の音がよく響いており、好奇心旺盛なこどものように元気なのだろう。鐘の音はもちろん見えないが、「かたち」というのもその存在感から頷ける。鐘の音は、その地域に楽しいことがないか探してまわるように広がっていく。奇しくも、そろそろ紅葉が散り始めの頃となり、鐘の音も今年最後の紅葉を愛でているのかもしれない。
イザナギやイザナミのイの母音どこかでなにか始まる呪文
加藤 知子
古事記で有名なイザナギとイザナミの国産み、神産みの物語。作者は直感で、イの母音に何か霊性が宿っていると感じている。とても面白い気づきである。調べてみると、本居宣長は、「いざな」は誘うに由来するのではないかと説いている。イザナギは死んだイザナミを追いかけて黄泉国までやって来る。死体である体を見られたイザナミは怒って大軍でイザナギを追いかける。イザナギは黄泉平良坂で追っ手が来られないように大岩で道を塞ぐ。「イ」の母音は黄泉国へ誘う恐ろしい呪文なのだろうか。
砂を撲(う)つごとくに朱夏の陽暮れゆきぬ慟哭すべき別れなき身に
山口 雪香(織江市改め)
連作は、作者独自の世界観に満ち溢れている。この歌では、砂漠を想像してみた。夏の暮れの太陽は、砂の地面を撲って慟哭するような感情の高ぶりがあると詠んだ。この表現はとてもよかった。太陽がそのように感情をあらわにして暮れてゆく。その一方で、自分には慟哭するような別れを経験したことがないという。自然あるいは世界と自分との距離感を感じている。
*斎藤秀雄・評者
イスラエルは嫌いと電話くる友怒りの矛先我に向く
弟子丸 直美
ガザにおけるジェノサイドに怒る《友》。最終的に《友》は《怒り》そのものに、独特の存在感を湛えた《怒りの矛》に、一個のかたまりに、変成する。本作のユニークな点は、《我》の知覚領域に対してありありと現れてくる《友》の、強烈な存在感が、《電話》という遠隔的なメディアを経由している点だろう。《友》は声として、眼前に到来する。連作の次の作では《同じ思いと》伝え返すことになるが、《友》の声のみを一首にした本作に、独立した詩情が宿る。
好きなもの夕焼けよりも朝焼けよコンビニパンはこのハムチーズ てらもと ゆう
感傷的なニュアンスのこびりつきがちな《夕焼け》よりも、晴れやかな「始まり」を感じさせる《朝焼け》を好むという語り手。下の句のカタカナの多さが、軽やかな気分への「意志」を感じさせる。また、《コンビニパンは》に、とくに《は》に、よろしさがある。おいしい《コンビニパン》は数あれど、私は《このハムチーズ》が好きなのだ。《ハムチーズ》の食感、匂い、色彩が、やはり「始まり」を感じさせて晴れやかだ。
時間かけカマキリ進む足元に夕日が射して茜に染まる 永田 義彦
老いをテーマとした連作「喜寿の会」のなかにあって、本作は寓意的な趣をもつ。本作の次の歌には、この《カマキリを見つめるカラス》が、寓話的なニュアンスを湛えて登場し、必然的に「死」が迫る気配を感じさせる。《夕日》の《茜》が晩年を彩るものだとしても、しかし《時間かけ》《進む》ことにより、《カマキリ》は今まさに生きている。生の「いまここ」を、喜寿を祝うように寿ぐ歌と読んだ。
使ひ切り書けなくなりし芯を抜き新しい芯を入れ終はりたり 服部 崇
連作には魅力的な作品が並んでいるが、シャープペンシルの芯を入れ替えるという徹底してミクロな動作にとどまった本作は、一種異様な感触を湛えている。古いものが捨てられることは寂しいようでもあり、しかし同時に新しいものが入ってくる様は清々しくもある。《芯》同士はバラバラなのに、詠みぶりは継ぎ目がないようであり、ぬめりのようなものさえ感じさせる。動詞の多用によって、「いま」が時間をかけて、読みの空間に連続して到来してゆく。
不動のモノがある、というリテラルな歌意と、ぬめりに満ちた読後感との、不思議なギャップが、魅力になっている。
*服部崇・評者
翡翠は電波に乗りやすき鳥ならん川へと皆が携帯向ける
北辻 一展
冒頭の「翡翠」はカワセミの別称である。カワセミは「翡翠」の名のごとく綺麗な色の羽を有している鳥である。「電波に乗りやすき鳥」とは如何なることかと読み進めると川縁にその姿を写真や動画に収めようと大勢が携帯電話のカメラを向けているところであることが明らかになる仕組みとなっている。携帯電話のカメラで撮影されたカワセミの写真や動画はアップロードされて電波に乗ってインターネット上をさまようことになる。
淡雲に日の滲みたる空の底ミルクのごとく人流れゆく
斎藤 秀雄
薄い雲に覆われている空からは日の光がうっすらと透けて見える。地上を「空の底」と表現したのが妙味。その「空の底」を大勢の人が歩き去って行く様子を液体のミルクに喩えているところも独特である。コップが倒れてミルクがテーブルに流れ出てしまったイメージ。行く人々はこの一首では液体と化している。淡雲のかかった空の色とミルクの色とが淡く混ざり合っている。
カーテンのそよぐ隙間に影ひとつ頬切る沈黙輪廻のかけら 阪野 基道
そよぐ風にカーテンの裾が動き、そこに影ができる。ひとり部屋にいる作者は沈黙の中にいる。「影」を見つめる状態から「沈黙」という音のない世界へ移行する。「頬切る」という身体表現が現実的な手触りを読者にもたらしている。作者は、結句に至って、そこに「輪廻のかけら」を見いだした。三句切れに加えて、四句切れとなっているのだろうか。あるいは沈黙が「輪廻のかけら」なのか。難解ながらも一首の展開に引きつけられた。
イベントが終わればすぐに散歩する、あの物件は未だに残る 西田 和平
「令和5年のおわりに」と題された一連は口語、日常の日記風。この一首のイベントとは、作者が準備に携わった俳句大会のことを指す。俳句大会は「笑顔があふれて」いた模様で成功裡に終わったようだ。俳句大会を終えたところで、この一首の場面に来る。何をするかというと、「散歩する」のである。それも「すぐに」である。下句で登場する「あの物件」。作者は俳句大会の準備をしている間ずっと気になっていたのだろう。作者は引っ越しをするのだろうか。この一首のあとでは「近所の人と会話」して「外構補修」をすることとなる。