小学館 ウィーン・フィル魅惑の名曲第8巻を聴き直しました。 カラヤンの“惑星”と“ペール・ギュント”です。
1961年の演奏です。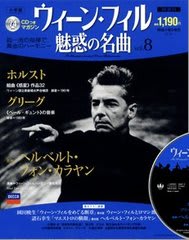
ホルストはイギリスを代表する作曲家。
イギリスは、不思議と作曲家が育たず、ホルストの他、パーセルやエルガー、ブリテンぐらいしか知られていません。
そのホルストでさえ、吹奏楽をやっている者には2つの「組曲」が有名ですが、管弦楽曲では「惑星」しか知られていません。
しかし、その管弦楽法は巧みで、例えば映画音楽のジョン・ウィリアムスなどには大きな影響を与えています。
カラヤンは、1956年から64年までウィーン国立歌劇場の芸術監督をしており、その間の録音です。
以前にも紹介しましたが、ウィーン・フィルはウィーン国立歌劇場管弦楽団の選抜メンバーです。手兵なのです。
『惑星』録音史上に燦然と輝く、カラヤンの名演!
と言われている61年盤です。
大陸のオーケストラにとって、ホルストは低く見られていた気がします。
ウィーン・フィルは、おそらくこの1回しか録音をしていません。(フランスのオケは1回、ベルリンフィルは3回か?)
ブラームスやモーツアルト、ベートーベンを演奏しているウィーンフィルのメンバーから見ると、ホルストの曲は、ポップスの感覚なのでしょう。
今ではあまりにも有名なこの曲を、現在の地位に押し上げたのは、このカラヤンの演奏です。
最新の録音技術に関心を向けていたカラヤンならではの録音で、50年前の録音とは思えないほどの高音質です。
演奏は、まるでバーンスタインのライブみたい。
アップテンポで、ぐいぐい引っ張ります。
打楽器・低音が異様に大きく、ホール全体に鳴り響いています。その点で、まさにライブのような臨場感です。
カラヤンにしては荒々しく、メンバーも高揚していることが音から伝わってきます。
カラヤンは、20年後にもベルリンフィルと「惑星」をデジタル録音しています。
その演奏は、高度に洗練されていますが、迫力はこの61年版が断然上。
聴き比べるとカラヤンの成長が分かります。
どちらを好むかは好みの問題でしょう。
次のサイトを発見しました。
ホルスト 「惑星」 所有盤 ディスコグラフィ
http://www.geocities.jp/planets_tako8_ma_vlast/planets00.htm
「ペール・ギュント」は、「惑星」に比べて、比較的丁寧に描いています。









