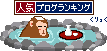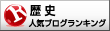己に自信のある者ほど、他人を頼らない。
けれども自信と劣等感は表裏一体である。
豪放磊落であるように見える人が、実は繊細な神経の持ち主だったという例などはよく聞くところだ。
野口英世。
この人ほど、自信と劣等感の中で揺れ動いた人もいないのではないだろうか。
心の叫びがまるまる外に聞こえてしまうような人だったと思う。
有名なところでは幼児の時に囲炉裏に手を突っ込んでしまい、火傷のせいで左手の指が全てくっ付いた状態になってしまった。
周囲からは「手ん棒」とからかわれた。
成人後、指を離す手術を行って貰ったことから、英世は医学への道を歩もうとするが、途中から細菌学者としての道を歩む。
化学しろ、細菌学にしろ、気が遠くなるような失敗の上に、ごくごく少ない成功が得られる分野だ。
猪苗代出身の野口英世には、粘り強い東北の血が伝わっていたのだろう。
「ヒデヨはいつ寝ているんだろう」
と周囲に言われるほど、寸暇を惜しんで行った地道な試験の後に、英世はアメリカで学者としての名声を轟かせていく。
英世の妻はメリー・ロレッタ・ダージス。通称、メージー。貧しいアイリッシュ系の移民の娘であった。
メージーには悪妻説も付きまとった。ひどいものになると、娼婦だったなどという噂も飛び交う。
だが、英世がアフリカに行き、黄熱病に罹った英世の手紙によって、メージーが悪妻であったかどうか分かる。
1928年4月5日
しばらく手紙が来ないので心配している。
どうしているか、すぐに電報で知らせてほしい(後略)。
1928年4月7日
今、満月だ。研究所から帰りながらあなたのことを思って。とても悲しい。でも、それも、もう終わり。心配しないで(後略)。
1928年4月10日
あなたの電報と手紙が届いて、とても嬉しかった。あなたが元気でアンディと一緒なのが嬉しい。彼もあなたも十分気をつけてもらいたい。仕事は難しいが、元気だ。五月中頃まで、ここにいるだろう。
夫がこんな手紙を出す相手が悪妻である訳がない。
もしかしたら、世間の言うところの『良妻』とはズレがあったかもしれない。
それでも、世間の『良妻』が自分にとっての『良妻』とは限らない。
人生の最期に「いいパートナーだった」と素直に言えるなら、その夫婦は素晴らしい関係にあったと思う。
野口英世は聖人君子ではなかった。
若い頃には放蕩もしたし、ロックフェラー研究場では助手との不倫も噂された。
助手の名は、エブリン・ティルディン。
後にノースウエスタン大学医学部の教授となり、一生を独身を通した女性だ。
不倫の噂の真偽はさておき、背の高いマサチューセッツ生まれのアメリカ娘は、英世に心酔した。
メリーも英世の死後は、悲しみのあまり、常軌を逸したような行動をとっている。
東洋の小男のどこにこんなに西欧女性を夢中にさせる魅力があったのだろう。
外見的魅力ではない。
仕事に集中して取り組む姿勢、生き方そのものにカリスマ的な魅力があったに違いない。
 メリー・ロレッタ・ダージス
メリー・ロレッタ・ダージス
参考:
野口英世とメリー・ダージス 飯沼信子 (水曜社)
↓ よろしかったら、クリックお願いします!!
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
<script type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=tadious-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4880652008&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>