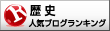昭和初期の頃、銭湯の脱衣所では、多くの女性が忙しく働いていたと言う。
数が多かったのは、「板の間稼ぎ」=衣服泥棒を防ぐ目的が大きかった。
この女性たちは、新潟出身者が多かった。
東京でイロハ風呂と呼ばれる四十七軒もの銭湯を経営していた新潟出身者の細川力蔵が、同郷者を雇ったからだ。
細川の経営する銭湯は、玄関から脱衣所に至るまで、天井に豪華な花鳥画を飾ってあった。
働く若い娘の愛嬌と、設備の豪華さで、はやりに流行ったという。
なかには、三十六代横綱になった羽黒岩政司なども、新潟出身であり、銭湯で働いていたことがあった。
同郷者を雇う細川式経営方法は、この頃流行となり、群馬出身者による蕎麦屋、愛知出身者によるパン屋などが次々と現れた。
自宅に風呂が設置されるようになったのは、昭和も下ってからの話であり、江戸の昔から昭和の中頃まで、銭湯はなかなか優れたビジネスであった。
たとえば、明治の時代、福沢諭吉も銭湯を経営していた。
福沢は「熱い湯は健康に悪い」といって、湯温をぬるめにしていたので、東京っ子の評判が悪かったという。
「マキをケチっている」と陰口を叩かれたが、案外、そのとおりなのかも知れない。
前述の細川はその後、目黒に一般客も入れる料亭を造る。
これが「目黒雅叙園」である、
その雅叙園も、今では外資系の経営となっている。
参考文献:骨董屋アルジの時代ばなし(翠石堂店主)
↓よろしかったら、クリックお願いいたします!
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
数が多かったのは、「板の間稼ぎ」=衣服泥棒を防ぐ目的が大きかった。
この女性たちは、新潟出身者が多かった。
東京でイロハ風呂と呼ばれる四十七軒もの銭湯を経営していた新潟出身者の細川力蔵が、同郷者を雇ったからだ。
細川の経営する銭湯は、玄関から脱衣所に至るまで、天井に豪華な花鳥画を飾ってあった。
働く若い娘の愛嬌と、設備の豪華さで、はやりに流行ったという。
なかには、三十六代横綱になった羽黒岩政司なども、新潟出身であり、銭湯で働いていたことがあった。
同郷者を雇う細川式経営方法は、この頃流行となり、群馬出身者による蕎麦屋、愛知出身者によるパン屋などが次々と現れた。
自宅に風呂が設置されるようになったのは、昭和も下ってからの話であり、江戸の昔から昭和の中頃まで、銭湯はなかなか優れたビジネスであった。
たとえば、明治の時代、福沢諭吉も銭湯を経営していた。
福沢は「熱い湯は健康に悪い」といって、湯温をぬるめにしていたので、東京っ子の評判が悪かったという。
「マキをケチっている」と陰口を叩かれたが、案外、そのとおりなのかも知れない。
前述の細川はその後、目黒に一般客も入れる料亭を造る。
これが「目黒雅叙園」である、
その雅叙園も、今では外資系の経営となっている。
参考文献:骨董屋アルジの時代ばなし(翠石堂店主)
↓よろしかったら、クリックお願いいたします!