「空母いぶき」という映画を観ました。
主演は西島秀俊さんと佐々木蔵之介さん。
架空の「東亜連邦」という国が日本の初島を占領し、戦争行為を仕掛けてくるという設定です。
この行為を空母いぶきを主艦とする自衛隊が防衛するというシナリオになっています。
専守防衛というのがキーワードになっていて、自衛隊員のじりじりとした緊迫感が伝わってきます。
限られた予算の中で作られたであろう戦闘シーンもなかなか迫力があります。
映画のレビューを見てみると、賛のほうが多いものの、賛否両論となっています。
その中で、個人的に思うことは、この映画は「娯楽映画」なのであるという点です。
リアリティさがあったとしても、それはあくまでも「リアリティっぱさ」です。
テレビの時代劇でバッタバッタ主人公が相手を切り斃しても、文句を言う人はいないと思います。
悪人がいきなり改心しても、「ああ、そうなのかなあ」と思う程度です。
乱暴な言い方になりますが、この手の映画も基本的にはテレビの時代劇と同じだと考えています。
これは決してこの映画をけなしているのではありません。
一種のメルヘンとして、「こうであればいいな」と思う気持ちは製作者と一緒です。
ただし、あくまでもメルヘンです。
戦争に真心は通用しません。
もし真心が通用するのであれば、中村哲医師は殺されることがありませんでした。
以前にこのブログでも書きましたがジェームス・フォーリー氏のような悲劇もなかったでしょう。
UNの力は「ルワンダの涙」や「ホテルルワンダ」を観ても分かるように、まったく無力です。
鋭くえぐった小説としては大岡昇平の「俘虜記」や「野火」、あるいは漫画になりますが、水木しげるの「総員玉砕せよ!」や「ラバウル戦記」などがありますが、日本人が敵に行った野蛮な行為についてはほとんど書かれていません。
その中で、「戦場とペンダント」という本があります。
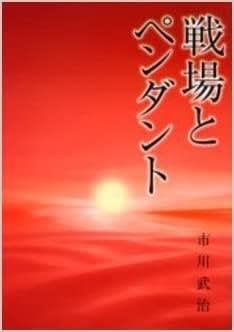
著者の市川武治氏は長野の郷土史研究家です。
第二次大戦中は、26歳のとき招集を受け、フィリピンで従軍しています。
前書きの中では、
戦争は罪悪であることを肝に銘記し、断じて再び起こしてはならない。
誰もそう考えるのは同じであるが、長い時間をかけ、ズルズルと、泥沼へ踏み込むように始められていくもので、一部の有力な権勢を握らせるのが、一番恐ろしい結果を招く。いかに恐ろしいかを、かつて戦争に従軍したものは、ありのままを伝えなければならないのであるが、口をつむぎあまり語りたがらないのは、敗戦により一転して戦争という罪悪に参加しての、引け目であろうか。
応召し北支で一か月足らずの実地訓練をうけ、前線に出勤したものであるから、いわゆる現役兵や志願兵とは異なり、徹底した軍国教育を受けたものとは違い、戦争には終始批判的であり、無抵抗の住民殺害には命を賭けてまでこれを拒み続けてきた。
と書いておられます。
たしかにその通りで、思い出すのも嫌な記憶でしょうし、小説にしろ、ノンフィクションにしろ、触れたがらないジャンルです。
下記のような描写を残すのは勇気がいったと思います。
を抜けてもまだ椰子林は続いている。ここまで連れてきた老人や女子供は非戦闘員で、当然、安全なところまで避難させるかと思った矢先、小隊長は急に全員の射殺を命じた。
そして道路からしばらく入った木立の中へ連れて行くと、小隊長が腰の拳銃を抜いた。殺されると意識してか、あご髯の長い老人は皆の前に立ちふさがった。小隊長の拳銃が火を噴くと、老人は硝煙の中で一回転しながら倒れた。割れた頭蓋骨から塩辛色の脳味噌が、大量に散乱した。女子供がそちこちで泣きわめき、兵につぎつぎに射殺される場は、まさに地獄絵図の再現であった。
昨今のコロナ渦の状況を見ていると、日本人のあやうさを感じていまいます。
文句は言うけど、選挙には行かない。
ばれなければいい、と思う心。
個々の事情を鑑みないで、全体論で「裁こう」とする人々。
ズルズルと時間を掛けて泥沼に足を突っ込まないようにしないといけないと思います。

主演は西島秀俊さんと佐々木蔵之介さん。
架空の「東亜連邦」という国が日本の初島を占領し、戦争行為を仕掛けてくるという設定です。
この行為を空母いぶきを主艦とする自衛隊が防衛するというシナリオになっています。
専守防衛というのがキーワードになっていて、自衛隊員のじりじりとした緊迫感が伝わってきます。
限られた予算の中で作られたであろう戦闘シーンもなかなか迫力があります。
映画のレビューを見てみると、賛のほうが多いものの、賛否両論となっています。
その中で、個人的に思うことは、この映画は「娯楽映画」なのであるという点です。
リアリティさがあったとしても、それはあくまでも「リアリティっぱさ」です。
テレビの時代劇でバッタバッタ主人公が相手を切り斃しても、文句を言う人はいないと思います。
悪人がいきなり改心しても、「ああ、そうなのかなあ」と思う程度です。
乱暴な言い方になりますが、この手の映画も基本的にはテレビの時代劇と同じだと考えています。
これは決してこの映画をけなしているのではありません。
一種のメルヘンとして、「こうであればいいな」と思う気持ちは製作者と一緒です。
ただし、あくまでもメルヘンです。
戦争に真心は通用しません。
もし真心が通用するのであれば、中村哲医師は殺されることがありませんでした。
以前にこのブログでも書きましたがジェームス・フォーリー氏のような悲劇もなかったでしょう。
UNの力は「ルワンダの涙」や「ホテルルワンダ」を観ても分かるように、まったく無力です。
鋭くえぐった小説としては大岡昇平の「俘虜記」や「野火」、あるいは漫画になりますが、水木しげるの「総員玉砕せよ!」や「ラバウル戦記」などがありますが、日本人が敵に行った野蛮な行為についてはほとんど書かれていません。
その中で、「戦場とペンダント」という本があります。
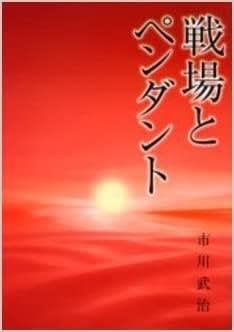
著者の市川武治氏は長野の郷土史研究家です。
第二次大戦中は、26歳のとき招集を受け、フィリピンで従軍しています。
前書きの中では、
戦争は罪悪であることを肝に銘記し、断じて再び起こしてはならない。
誰もそう考えるのは同じであるが、長い時間をかけ、ズルズルと、泥沼へ踏み込むように始められていくもので、一部の有力な権勢を握らせるのが、一番恐ろしい結果を招く。いかに恐ろしいかを、かつて戦争に従軍したものは、ありのままを伝えなければならないのであるが、口をつむぎあまり語りたがらないのは、敗戦により一転して戦争という罪悪に参加しての、引け目であろうか。
応召し北支で一か月足らずの実地訓練をうけ、前線に出勤したものであるから、いわゆる現役兵や志願兵とは異なり、徹底した軍国教育を受けたものとは違い、戦争には終始批判的であり、無抵抗の住民殺害には命を賭けてまでこれを拒み続けてきた。
と書いておられます。
たしかにその通りで、思い出すのも嫌な記憶でしょうし、小説にしろ、ノンフィクションにしろ、触れたがらないジャンルです。
下記のような描写を残すのは勇気がいったと思います。
を抜けてもまだ椰子林は続いている。ここまで連れてきた老人や女子供は非戦闘員で、当然、安全なところまで避難させるかと思った矢先、小隊長は急に全員の射殺を命じた。
そして道路からしばらく入った木立の中へ連れて行くと、小隊長が腰の拳銃を抜いた。殺されると意識してか、あご髯の長い老人は皆の前に立ちふさがった。小隊長の拳銃が火を噴くと、老人は硝煙の中で一回転しながら倒れた。割れた頭蓋骨から塩辛色の脳味噌が、大量に散乱した。女子供がそちこちで泣きわめき、兵につぎつぎに射殺される場は、まさに地獄絵図の再現であった。
昨今のコロナ渦の状況を見ていると、日本人のあやうさを感じていまいます。
文句は言うけど、選挙には行かない。
ばれなければいい、と思う心。
個々の事情を鑑みないで、全体論で「裁こう」とする人々。
ズルズルと時間を掛けて泥沼に足を突っ込まないようにしないといけないと思います。










