
上州国定村の忠治は博徒の親分として名高い。
忠治の晩年は中風を患い、知り合いの間をたらいまわしにされるというみじめなものであった。
不自由な身体のまま縄を受けた忠治は、大戸の関所に併設された処刑場で磔にされた。
だが、この磔にされるまでの立ち振る舞いが見事で人々の脳裏に強烈な印象を残した。
唐丸駕籠で運ばれた忠治であるが、その駕籠の中には高級品である更紗の座布団を二枚重ね、その上に真っ赤な座布団を重ねるという豪華仕様であった。
また忠治のいでたちは、無地の浅黄に白無垢を重ね着し、白い手甲と脚絆を着け、首からは大きな数珠を掛けていた。
そして、磔のあと、いよいよ槍を突き刺される段になっても動じたところを見せず、逆に役人を励ましたというエピソードは忠治の人気を高めた。
さらに芝居で取り上げられるようになり、忠治の人気は不動のものとなる。
ここには、幕府側の「忠治は神妙であった」という認識があったのではないかと思われる。
さて、その忠治であるが、女性関係は華やかであった。正妻の鶴のほかに、よく知られたところだけでも愛妾の町、徳などの女性がいた。
大久保一角という武家崩れの娘に生まれた貞も忠治の妾のひとりである。
その貞と忠治の間に生まれたのが寅二である。
元服して国次と改名するようになったが、さらには真言宗の寺である出流山万願寺に入門し、千乗と名乗る。
下って、時は慶応三年(1867年)十一月。
明治になる一年前。
藩主島津の病気全快を祈りに来たという薩摩藩士が万願寺に入った。
薩摩藩士は寺に入るやいなや、実は自分たちは勤王の志を抱いており、この上州の地で討幕軍を決起するという決意を語りだす。
その決意に共感した千乗こと国定国次は、以来、大谷刑部と名乗り、志士たちに合流する。
当の本人たちは本気で討幕を試みていたが、薩摩の上層部としては、幕府を威嚇して戦闘の口火を切らせるための陽動作戦でしかなかった。
赤報隊の悲劇にも共通するが、いわば切り捨てられた部隊なのである。
国次は志士たちの群れに参加してからわずか一か月ほどした慶応三年十二月十八日、処刑され、24年という短い生涯を終えたのであった。
処刑されるとき、国次の脳裏に浮かんだのはどのような考えであったのだろうか。





忠治の晩年は中風を患い、知り合いの間をたらいまわしにされるというみじめなものであった。
不自由な身体のまま縄を受けた忠治は、大戸の関所に併設された処刑場で磔にされた。
だが、この磔にされるまでの立ち振る舞いが見事で人々の脳裏に強烈な印象を残した。
唐丸駕籠で運ばれた忠治であるが、その駕籠の中には高級品である更紗の座布団を二枚重ね、その上に真っ赤な座布団を重ねるという豪華仕様であった。
また忠治のいでたちは、無地の浅黄に白無垢を重ね着し、白い手甲と脚絆を着け、首からは大きな数珠を掛けていた。
そして、磔のあと、いよいよ槍を突き刺される段になっても動じたところを見せず、逆に役人を励ましたというエピソードは忠治の人気を高めた。
さらに芝居で取り上げられるようになり、忠治の人気は不動のものとなる。
ここには、幕府側の「忠治は神妙であった」という認識があったのではないかと思われる。
さて、その忠治であるが、女性関係は華やかであった。正妻の鶴のほかに、よく知られたところだけでも愛妾の町、徳などの女性がいた。
大久保一角という武家崩れの娘に生まれた貞も忠治の妾のひとりである。
その貞と忠治の間に生まれたのが寅二である。
元服して国次と改名するようになったが、さらには真言宗の寺である出流山万願寺に入門し、千乗と名乗る。
下って、時は慶応三年(1867年)十一月。
明治になる一年前。
藩主島津の病気全快を祈りに来たという薩摩藩士が万願寺に入った。
薩摩藩士は寺に入るやいなや、実は自分たちは勤王の志を抱いており、この上州の地で討幕軍を決起するという決意を語りだす。
その決意に共感した千乗こと国定国次は、以来、大谷刑部と名乗り、志士たちに合流する。
当の本人たちは本気で討幕を試みていたが、薩摩の上層部としては、幕府を威嚇して戦闘の口火を切らせるための陽動作戦でしかなかった。
赤報隊の悲劇にも共通するが、いわば切り捨てられた部隊なのである。
国次は志士たちの群れに参加してからわずか一か月ほどした慶応三年十二月十八日、処刑され、24年という短い生涯を終えたのであった。
処刑されるとき、国次の脳裏に浮かんだのはどのような考えであったのだろうか。

























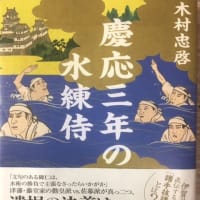




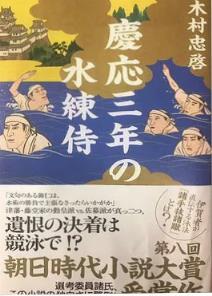

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます