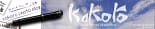庄内平野では稲刈りが進んでいます。
稲の刈り取り適期は大凡決まっていて、その刈り取りによって、収穫・品質・食味に
大きく影響するので農家は神経を使います。
刈り取りの基準としては、
(1)穂が出てからの積算温度(穂が出てから毎日の平均気温を足した累積の気温)が
ほぼ1000度に達していること。
(2)全体の籾の中で青い籾の割合が15~20%くらいであること。
(3)籾の中の水分が25%前後であること。
この3つの条件に達した時が刈り取りの目安だそうです。
(参照:JA全農山形「おいしい国、庄内」より)
近年の稲刈りは、おもにコンバインを使って刈り取りと脱穀(稲から籾だけをとる)を同時に行い、
籾を乾燥機で乾燥させます。 庄内地方でも現在は98%が乾燥機で乾燥させるそうですが、
昔ながらの天日乾燥を行っている農家もいます。
天日乾燥の良いところは、お米の味が良くなるところ。稲が天日している間に雨や朝晩の露と
風や日光に繰り返し繰り返しさらされながら、少しずつ乾いていき、そしてその間に、稲は葉や
くきに貯まった栄養分を籾に移すために、天日で自然乾燥させると味が良くなるといわれている
のです。
天日乾燥の方法は、一本の杭(クイ)に稲を重ねていく「杭掛け」と、材木を横に1~5段ぐらいに
組み立ててその横棒に稲を掛けてゆく「稲架(ハサ)掛け」する方法などがありますが、庄内地方
はほとんどが「杭掛け」です。
「杭掛け」は、杭一本に稲を掛けていきますので手間暇や材料がかからない利点がありますが、
稲を重ねるので何回か掛け直しをしないと良く乾燥しない欠点が有り、「稲架掛け」は、稲を重ね
ないので乾燥しやすくなりますが、稲架を作る手間や材料費がよけいにかかるし、上の段に掛け
るには数人必要になってしまう欠点があるようです。
その点、庄内地方は風がよく吹く地方ですので、杭掛けしても稲が良く乾くためこの方法が最適の
ようです。乾燥方法は、その地域の自然のありようによって選択されているので、どちらの方法が
優れているかという問題ではありません。
ただ、どちらの方法でも天日乾燥は農家の苦労であり、また、乾燥させる期間に長雨が続いたり、
台風が来たりすると、乾燥させるはずの籾から芽が出たりして品質が著しく落ちるなどの心配も絶
えませんし、専業農家の減少問題もありますので、現在の機械乾燥に移行するのは自然の流れだ
と思います。
私も子どもの頃は、田んぼ仕事を手伝わされたこともあり、今は少なくなってしまった杭掛けの風景
を見かけると、ついつい撮影してしまうのです。 (以前のエントリー→ここ)



撮影地:酒田市本楯
撮影DATA
Nikon D300s
Tokina AT-X 124 PRO DX F4
Nikkor AF-S DX 17-55mm F2.8G![]()
![]()


小野リサさんのボサノバにはいつも癒やされます。
おすすめです。
↓
 |
ジャポン |
| クリエーター情報なし | |
| ドリーミュージック |