
長谷寺より材木座方向を眺望
久方の
空青くして雲白く湘南の海
春近きかな

長谷寺に上りて
仰ぐみ仏は
黄金も眩し観音菩薩
閑話休題 <鎌倉日記はまた別の機会にして。>
今回の旅は、湘南啄木文庫の佐藤先生の歌会に出ることが主目的であった。
と言うよりも、佐藤先生に会いたかったからかも知れない。
この日は、「グランドホテル神奈中秦野」に投宿。
駅界隈の居酒屋で、ひとり少しばかりのお酒を。
フロントへ明朝8:10にタクシー予約。
佐藤先生から、「歌会の前に家へいらっしゃい」とのお言葉を頂いていたので。

啄木関連の蔵書だけで3000冊!湘南啄木文庫にて。
詠題は「青」だった。出席を決めたのは詠草の締め切り直前だったこともあり、前に詠んだものを送信させて頂いた。
青き海 見え隠れして
石見路の 無人の駅に
百日紅咲く
である。
短歌の作法、と言うよりもセンテンス的にも、おかしいのだが、好きな自作である。
啄木流に「我を愛する歌」ってところかな。
歌会では一番多く入れて頂いた。佐藤先生の選評でのご指摘も、私自身が気がついていたことと同様であった。
この表現だからこその味わいがあって、必ずしも作法に則ることはないとのことだった。
蛇足ながら、
これは先年、島根県浜田市に講演に訪れた時に、山陰線の電車の中で詠んだものである。まずは、
「見え隠れ」
電車が動いているということである。つまり私は車中の人。電車は海辺を走ってはいるが、ずっと海が見え続けている訳ではない。
木立や家があると車窓から海は隠れる。
次いで、
「無人の駅」
無人でも有人でも「駅」は駅である。見え隠れもしていない。
つまり静止そのものである。だから「見え隠れ」との整合性の問題である。
そして、
「石見路」
鉄道だから「路」はおかしいと言えばおかしい。
しかしこれも、山陰は石見地方を旅しているのだな、という意味でOKだった。
「山陰の無人の駅に」でもいいかなとも思ったのだが、山陰線はかなり長いので、敢えて石見に。
また、駅に百日紅は咲かない。駅の敷地に咲いているのだ。
海が見え隠れしながら電車は走っている。
ある無人駅に停車した。窓越しに見ると、紅の花が咲いているよ。
と、誰だってそのように理解してくれると思う。
いささか、自己弁護になった感じ。
佐藤先生から更に、私の歌が源実朝の、
箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ(金塊和歌集)
の雰囲気だと紹介された。何となくそうかもね。
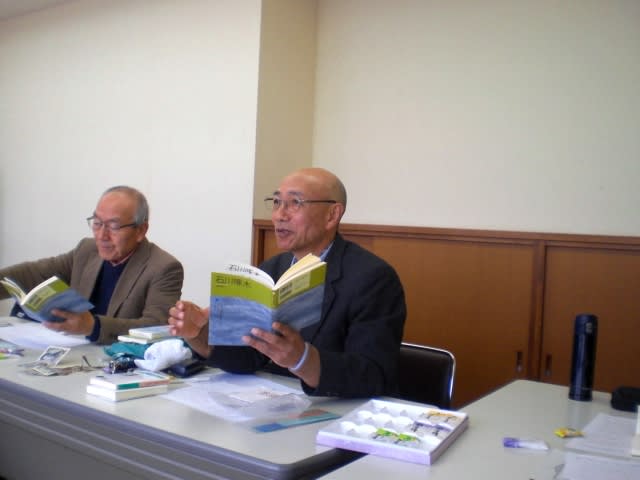
佐藤先生から啄木の歌についての講義
それでは、つづきは、どうするかな。もう、いいっか・・・。















