
そう言えば・・・・。
まだ芭蕉を松島へ出立させておりません。
どうも、芭蕉の足取りをたどっているうちに、故郷、塩竈へ語っている本人が帰って来てしまったわけですから、寄り道もしたくなろうというものです。
と、上記、言い訳です。
塩竈神社へは、ほぼ毎日と言っていいくらい通っております。
朝の神社の凜とした空気は何とも言えない清々しさを運んでくれます。
カメラを片手に境内を散策しております。
つい最近まで、都会の満員電車の中で過ごしていた時間をこうした事に使っております。
「贅沢な時間」なのでしょうね。
「おくのほそ道」に戻ります。
早朝、塩がまの明神に詣ず。国守再興せられて、宮柱ふとしく、彩殿きらびやかに、石の階九仭に重り、朝日あけの玉がきをかかやかす。
かかる道の果、塵土の境まで、神霊あらたにましますこそ吾国の風俗なれと、いと貴けれ。神前に古き宝燈有。かねの戸びらの面に、文二三年和泉三郎寄進、と有。
五百年来の俤、今目の前にうかびて、そぞろに珍し。渠は勇儀忠孝の士也。佳命今にいたりてしたはずといふ事なし。誠「人能道を務、義を守べし。名もまた是にしたがふ」
と云り。日既午にちかし。船をかりて松島にわたる。

三度目の登場です。
この「文治燈籠」とも「文治の神燈」とも呼ばれております。
この「和泉三郎」とは誰かと申しますと「藤原忠衡」です。
奥州藤原氏三代「秀衡」の三男です。
この宝燈を奉納した時期が藤原氏にとって大変微妙な時期に当たります。
と、申しますもの、「源義経討伐」と深い関係があると言うことなのです。
掻い摘んで申し上げます。
文治三年(1187年)2月源頼朝に追われた義経は平泉に逃れます。秀衡を頼りにしたわけです。
頼朝は、しつこく、義経を討ちにかかります。
この燈籠が寄進されたのが、同年の七月。
そして10月に秀衡が急逝し、後継ぎとなった奏衡は、頼朝に屈します。
そうして文治五年(1189年)四月に義経を襲います。
(もう弁慶の立往生が名場面ではありますが・・)
忠衡は最後まで義経をかばいますが、義経死後6月に、兄によって滅ぼされました。
この燈籠を寄進した、忠衡はどんな思いで寄進したのでしょう。
「塩竈様」への祈りの気持ちがいかばかりか。
この燈籠を見るたび、忠衡の気持ちに触れたような気がしてまいります。
芭蕉もおそらく、こうした史実を知っていて「おくのほそ道」に記したのでしょう。
奥州藤原氏が、塩竈神社を尊崇していたことを物語る燈籠として貴重な遺産なのですね。
しかし、この燈籠は歴史の中で翻弄されることとなります。
形が問題となります。
「松島眺望集」では「一丈一尺の鉄燈有。昔秀衡三男和泉三郎建立、再興寛文年中仙台堺氏宗心、荘厳美也」と記されてます。
この「再興」というところです。
「鹽竈神社」(押木耿介氏著 昭和47年)によれば「当初は仏教の経軌にのって九輪、風鐸、露盤が屋上に架されてあり、これが長い年月を経て損傷したため、法蓮寺僧宥覚が再興し、元禄年間には、燈内に鋳造仏が安置されてあった」と述べられております。
上記、二つの「再興」の関係はどうなのでしょうか。
芭蕉がこの燈籠の形を少しでも語っていてくれてたら、当時の形がわかり、歴史の謎が少しでも解決するのに。と現代に生きる酔漢は思ってしまいます。
仏塔形式の燈籠が、神前にある。この事実の不思議さも思います。
現在、40本の石柵で覆われておりますが、大場雄淵(おおばおぶち)という俳人が寄進したものとされております。文政十二年(1829年)の没ですから、この柵にも歴史を感じるところですね。
早朝の塩竈様は、冒頭でお話しました通り、気持ちが凜となります。
玉砂利を踏む自身の足音が一森山に響くようなそんな中、多くの鳥達の声が境内に聞こえて参ります。
丁度、昨日は、梅が七分咲となっておりました。

椿がそろそろ終わりですね。
春の花が咲いてまいりました。

茶屋の前の庭園の「まんさく」が満開。
千賀浦が遠くに見えてますね
そして、四季桜がほんのり花を着けております。

芭蕉と曽良は、小船に乗り、松島へ向かいました。
しかしながら、この塩竈様の「不思議なところ」は、沢山有りすぎて、全てが明らかになることはないのでしょう。
街中からは一切見ることが出来ない社。
深い森の中に存在しているかのような佇まいは、これからもこだわって語っていきたいところです。
身近に、こんなスポットがある。
故郷を肌で感じている自分がおります。
日既に午にちかし。船をかりて松島にわたる。その間二里余、雄島の磯につく。
船の中の様子の記述がありません。
曽良日記でもそうです。
陸に近いところを漕いで松島へ向かったとするのが自然なのですが、どんな風景を見ていたのか。
気になります。
もしかしたら、船の上で「うたた寝」していた二人なのかもしれませんね。
今とは全く違った「千賀浦」であったはずです。
次回は、その船の跡を少しばかり辿ってみたい。
こう思っております。
まだ芭蕉を松島へ出立させておりません。
どうも、芭蕉の足取りをたどっているうちに、故郷、塩竈へ語っている本人が帰って来てしまったわけですから、寄り道もしたくなろうというものです。
と、上記、言い訳です。
塩竈神社へは、ほぼ毎日と言っていいくらい通っております。
朝の神社の凜とした空気は何とも言えない清々しさを運んでくれます。
カメラを片手に境内を散策しております。
つい最近まで、都会の満員電車の中で過ごしていた時間をこうした事に使っております。
「贅沢な時間」なのでしょうね。
「おくのほそ道」に戻ります。
早朝、塩がまの明神に詣ず。国守再興せられて、宮柱ふとしく、彩殿きらびやかに、石の階九仭に重り、朝日あけの玉がきをかかやかす。
かかる道の果、塵土の境まで、神霊あらたにましますこそ吾国の風俗なれと、いと貴けれ。神前に古き宝燈有。かねの戸びらの面に、文二三年和泉三郎寄進、と有。
五百年来の俤、今目の前にうかびて、そぞろに珍し。渠は勇儀忠孝の士也。佳命今にいたりてしたはずといふ事なし。誠「人能道を務、義を守べし。名もまた是にしたがふ」
と云り。日既午にちかし。船をかりて松島にわたる。

三度目の登場です。
この「文治燈籠」とも「文治の神燈」とも呼ばれております。
この「和泉三郎」とは誰かと申しますと「藤原忠衡」です。
奥州藤原氏三代「秀衡」の三男です。
この宝燈を奉納した時期が藤原氏にとって大変微妙な時期に当たります。
と、申しますもの、「源義経討伐」と深い関係があると言うことなのです。
掻い摘んで申し上げます。
文治三年(1187年)2月源頼朝に追われた義経は平泉に逃れます。秀衡を頼りにしたわけです。
頼朝は、しつこく、義経を討ちにかかります。
この燈籠が寄進されたのが、同年の七月。
そして10月に秀衡が急逝し、後継ぎとなった奏衡は、頼朝に屈します。
そうして文治五年(1189年)四月に義経を襲います。
(もう弁慶の立往生が名場面ではありますが・・)
忠衡は最後まで義経をかばいますが、義経死後6月に、兄によって滅ぼされました。
この燈籠を寄進した、忠衡はどんな思いで寄進したのでしょう。
「塩竈様」への祈りの気持ちがいかばかりか。
この燈籠を見るたび、忠衡の気持ちに触れたような気がしてまいります。
芭蕉もおそらく、こうした史実を知っていて「おくのほそ道」に記したのでしょう。
奥州藤原氏が、塩竈神社を尊崇していたことを物語る燈籠として貴重な遺産なのですね。
しかし、この燈籠は歴史の中で翻弄されることとなります。
形が問題となります。
「松島眺望集」では「一丈一尺の鉄燈有。昔秀衡三男和泉三郎建立、再興寛文年中仙台堺氏宗心、荘厳美也」と記されてます。
この「再興」というところです。
「鹽竈神社」(押木耿介氏著 昭和47年)によれば「当初は仏教の経軌にのって九輪、風鐸、露盤が屋上に架されてあり、これが長い年月を経て損傷したため、法蓮寺僧宥覚が再興し、元禄年間には、燈内に鋳造仏が安置されてあった」と述べられております。
上記、二つの「再興」の関係はどうなのでしょうか。
芭蕉がこの燈籠の形を少しでも語っていてくれてたら、当時の形がわかり、歴史の謎が少しでも解決するのに。と現代に生きる酔漢は思ってしまいます。
仏塔形式の燈籠が、神前にある。この事実の不思議さも思います。
現在、40本の石柵で覆われておりますが、大場雄淵(おおばおぶち)という俳人が寄進したものとされております。文政十二年(1829年)の没ですから、この柵にも歴史を感じるところですね。
早朝の塩竈様は、冒頭でお話しました通り、気持ちが凜となります。
玉砂利を踏む自身の足音が一森山に響くようなそんな中、多くの鳥達の声が境内に聞こえて参ります。
丁度、昨日は、梅が七分咲となっておりました。

椿がそろそろ終わりですね。
春の花が咲いてまいりました。

茶屋の前の庭園の「まんさく」が満開。
千賀浦が遠くに見えてますね
そして、四季桜がほんのり花を着けております。

芭蕉と曽良は、小船に乗り、松島へ向かいました。
しかしながら、この塩竈様の「不思議なところ」は、沢山有りすぎて、全てが明らかになることはないのでしょう。
街中からは一切見ることが出来ない社。
深い森の中に存在しているかのような佇まいは、これからもこだわって語っていきたいところです。
身近に、こんなスポットがある。
故郷を肌で感じている自分がおります。
日既に午にちかし。船をかりて松島にわたる。その間二里余、雄島の磯につく。
船の中の様子の記述がありません。
曽良日記でもそうです。
陸に近いところを漕いで松島へ向かったとするのが自然なのですが、どんな風景を見ていたのか。
気になります。
もしかしたら、船の上で「うたた寝」していた二人なのかもしれませんね。
今とは全く違った「千賀浦」であったはずです。
次回は、その船の跡を少しばかり辿ってみたい。
こう思っております。















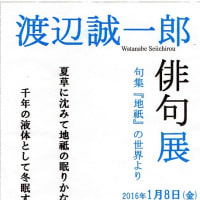










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます