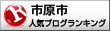前回のブログで案内した認知症に関するイベントが昨日行われました。
午前中は認知症カフェで、午後は医療介護の専門職向けの講演会でした。

大きなテーマは「高齢者とくすり」。
まず、東京大学医学部附属病院・老年病科の秋下雅弘先生から、ポリファーマシーの問題について。

「ポリファーマシー」とは、必要以上に多種類のくすりを飲んで有害事象が起こっている状態のことを指します。日本ではおおむね6種類以上とされています。
75才以上の後期高齢者の救急の15%以上はくすりが原因とのことですから、深刻ですよね。
高齢になるほど、代謝や排せつ機能は衰えていきます。
例えばお酒も、若いころのように量が飲めなくなった、残りやすくなったという方は多いと思いますが、くすりも同じなんです。
さらに、複数の疾患を抱えて掛け持ちで医療機関に通うようになったり、認知機能や視力・聴力が低下して正しく服用できなくなるなど、リスクはどんどん高くなります。
後期高齢者によくみられる症状(ふらつく、転びやすい、物忘れ、興奮しやすい、ボーっとする)も、案外ポリファーマシーのせいかもしれませんよ。それを知らずにまた医者に行って更にくすりが増える・・・。
悪循環です。
これまでこの問題は、医療従事者の間でもあまり意識されなかったのですが、近年ようやく注目されるようになってきました。
医療や介護に携わる専門職は当然のことですが、患者側も正しい知識を持って、なにか思い当たることがあれば医師や薬剤師に相談することも大切ですね。
二番目の講演では、市原市薬剤師会の小室裕保先生が、実際に薬剤師が服薬支援を行っている例をたくさん紹介して下さました。

今年4月から診療報酬が改定されて、「かかりつけ薬剤師制度」がスタートしました。
患者さん自身が信頼する薬剤師を選び、書面で同意をかわすことで、自分が服用しているくすり(市販薬やサプリメントなどの健康食品も!)をすべて把握してもらい、24時間いつでも相談することが可能になるものです(サービスごとに何十円かの負担あり)。
制度にかかわらず、くすりに関する相談にいつでも気軽に応じて健康をサポートするのは本来の薬剤師の務めですから、ぜひ多くの方にもっと気軽に薬局を活用してもらえればと思います。
午前中は認知症カフェで、午後は医療介護の専門職向けの講演会でした。

大きなテーマは「高齢者とくすり」。
まず、東京大学医学部附属病院・老年病科の秋下雅弘先生から、ポリファーマシーの問題について。

「ポリファーマシー」とは、必要以上に多種類のくすりを飲んで有害事象が起こっている状態のことを指します。日本ではおおむね6種類以上とされています。
75才以上の後期高齢者の救急の15%以上はくすりが原因とのことですから、深刻ですよね。
高齢になるほど、代謝や排せつ機能は衰えていきます。
例えばお酒も、若いころのように量が飲めなくなった、残りやすくなったという方は多いと思いますが、くすりも同じなんです。
さらに、複数の疾患を抱えて掛け持ちで医療機関に通うようになったり、認知機能や視力・聴力が低下して正しく服用できなくなるなど、リスクはどんどん高くなります。
後期高齢者によくみられる症状(ふらつく、転びやすい、物忘れ、興奮しやすい、ボーっとする)も、案外ポリファーマシーのせいかもしれませんよ。それを知らずにまた医者に行って更にくすりが増える・・・。
悪循環です。
これまでこの問題は、医療従事者の間でもあまり意識されなかったのですが、近年ようやく注目されるようになってきました。
医療や介護に携わる専門職は当然のことですが、患者側も正しい知識を持って、なにか思い当たることがあれば医師や薬剤師に相談することも大切ですね。
二番目の講演では、市原市薬剤師会の小室裕保先生が、実際に薬剤師が服薬支援を行っている例をたくさん紹介して下さました。

今年4月から診療報酬が改定されて、「かかりつけ薬剤師制度」がスタートしました。
患者さん自身が信頼する薬剤師を選び、書面で同意をかわすことで、自分が服用しているくすり(市販薬やサプリメントなどの健康食品も!)をすべて把握してもらい、24時間いつでも相談することが可能になるものです(サービスごとに何十円かの負担あり)。
制度にかかわらず、くすりに関する相談にいつでも気軽に応じて健康をサポートするのは本来の薬剤師の務めですから、ぜひ多くの方にもっと気軽に薬局を活用してもらえればと思います。