まつら長者(小夜姫)③
小夜姫だけを心のより所として生きてきた御台様は、一人打ち捨てられて、泣き明かしておりましたが、やがてもの狂いとなり、両眼を泣き潰してしまいました。小夜姫を捜し求めるように奈良の都を徘徊して、松浦の狂女と呼ばれるようになってしまいます。かつての栄華を考えれば、御台所のなれの果てを、哀れと思わない人はいませんでした。
さて、そうとも知らず小夜姫は、権下の太夫に連れられて、どこまで行くとも知らないまま、やがて木津川を渡ると山城の国に差し掛かりました。故郷の大和の国ともお別れです。
「後を問う その垂乳根の憂き身とて 我が身売り買う 泪なりけり」
と歌うと、泪に潤む目に故郷の景色をしっかりと焼き付けました。
【ここから、いわゆる、「東下り」の「道行き」と言う記述になります。現在も残る旧東海道の宿や地名を辿りながら、旅慣れぬ姫の苦労が語られます。四百年前の旅路を、記述に従って辿ることにします。】
①命めでたき長池や(京都府城陽市)
②小倉つつみの野辺過ぎて(京都府宇治市小倉)
③四条河原
④祇園林の群烏(むらがらす)
⑤経書堂(きょうかくどう:石に一字づつ経を書く)
⑥清水寺
⑦秋風吹けば白川や(京都市左京区)
⑧粟田口とよ悲しやな(京都市東山区)
⑨日の岡峠を早過ぎて(京都市山科区)
⑩人に会わねと追分けや山科に聞こえたる四ノ宮河原を辿り(京都市山科区四ノ宮)
⑪行くも帰るも逢坂の この明神のいにしえは蝉丸殿にて御座ある(滋賀県大津市)
※ここで説経らしく、小夜姫は蝉丸宮に詣でています。
⑫大津、打出の浜(琵琶湖畔)より志賀、唐崎の一つ松(近江八景唐崎夜雨)
⑬石山寺の鐘の声(近江八景石山秋月【三井寺の三井晩鐘が混じっているようです】)
⑭なおも思いは瀬田の橋(近江八景瀬田夕照)
⑮時雨も抱く守山や(滋賀県守山市)
⑯風に露散る篠原や(滋賀県野洲市 小篠原・大篠原)
⑰くもりもやらで鏡山(野洲市と竜王町の境:標高384m)
⑱馬淵、縄手を早過ぎて(滋賀県近江八幡市)
⑲多賀の浮き世の中厭いつつ(滋賀県近江八幡市)
⑳無常寺よと伏拝み(不明)
21 入て久しき五じょう宿(不明)
22 年を積もるが老蘇の森(滋賀県近江八幡市)
23 愛知川渡れば千鳥立つ(滋賀県東近江市・愛壮町)
24 小野の細道摺針峠(滋賀県彦根市)
25 番場、醒ヶ井、柏原(滋賀県米原市)
26 寝物語を打ちすぎて(美濃と近江の国境)
27 お急ぎあれば程もなく山中宿へお着きある(岐阜県関ヶ原町、今須付近)
先を急ぐ太夫の足についていけない小夜姫は、疲れ果てて遂に、山中の宿で足の痛みに耐えかねて、
「いかに太夫殿、憂き長旅のことなれば、急ぐとすれど歩まれず。この所に二三日逗留してくださるようにお願いします。」
と、言います。太夫は、大きに腹を立てて、
「奈良の都より奥州までは、百二十日もかかる旅であるぞ。どんなに嘆いても逗留はならん。」
と、手に持つ杖でさんざんに打ちつけるのでした。小夜姫は、打たれる杖のその下よりも、
「情けも無い太夫殿。打つとも、叩くとも、太夫の杖と思えば、真に恨むことはありません。冥途にまします父上様の教えの杖であると知っていますから。」
と、手を合わせて言うのでした。これには、さすがの太夫も参りました。ここまで歩き詰めに歩かされてきましたが、三日間の休養を許されたのでした。
28 嵐、木枯らし不破の関(岐阜県関ヶ原町)
29 露の垂井と聞くなれば(岐阜県垂井町)
30 夜はほのぼの赤坂や(岐阜県大垣市)
31 杭瀬川にぞお着きある(岐阜県大垣市)
32 大熊河原の松風(不明)
33 尾張なる熱田の宮を伏し拝み(愛知県名古屋市熱田区)
34 三河の国に入りぬれば、足助の山も近くなり(愛知県豊田市)
35 矢作の宿を打ち過ぎて(愛知県岡崎市)
36 かの、八つ橋にお着きある(国道1号線矢作橋付近)
37 先をいづくと遠江、浜名の橋の入り潮に(静岡県 浜名湖大橋付近)
38 明日の命は知らねども池田と聞けば頼もしや(静岡県浜松市 天竜川)
39 袋井縄手遙々と(静岡県袋井市)
40 日坂過ぐれば音に聞く、小夜の中山これとかや(静岡県掛川市)
41 いかだ流るる大井川
42 岡部の松は少しあれ(不明)
43 神に祈りの金谷とや(静岡県島田市)
44 四方に神はなけれども島田と聞くは袖寒や(静岡県島田市)
45 聞いて優しき宇津の山辺(静岡県藤枝市:静岡市 宇津ノ谷峠)
46 丸子川、賤機山を馬手に見て(静岡県静岡市駿河区)
47 いかなる人か由比の宿(静岡県静岡市清水区)
48 蒲原と打ち眺め(静岡県静岡市清水区)
49 富士のお山を見上げれば・・・略・・・南は海上、田子の浦(静岡県富士市)
50 原には塩屋の夕煙(静岡県沼津市)
51 伊豆三島を打ち過ぎて(静岡県三島市)
52 足柄、箱根にお着きあり(神奈川県箱根町)
53 相模の国に入りぬれば、大磯小磯は早過ぎて(神奈川県平塚市)
54 めでたきことを菊川や(不明)
55 鎌倉山はあれとかや(神奈川県鎌倉市)
56 行方も知れぬ武蔵野や(横浜・川崎付近カ)
57 隅田川にお着きある
げにや誠、音に聞く、梅若丸の墓印
(木母寺(謡曲「隅田川」の寺):東京都墨田区堤通2丁目16番1号)
58 東雲早く白河や、二所の関とも申すらん(福島県白河市)
59 恋しき人にあいずの宿(不明)
60 お急ぎあれば程も無く、遙か奥州日の本や、陸奥の国、安達の郡に着き給う。
以上の道行きは上方版による記述ですが、江戸版では、関東近辺の記述がやや詳しくなっています。さながら、四百年前の旅行ガイドといったところでしょうか。小夜姫と共に百二十日に及ぶ東海道と奥州街道の旅にお付き合いいただきました。
つづく










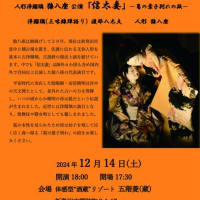


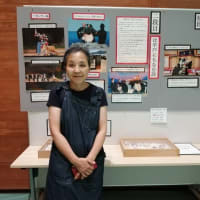
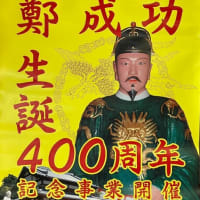




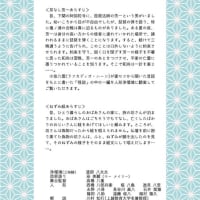
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます