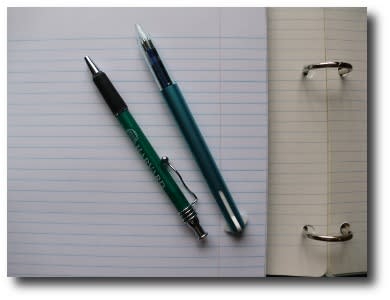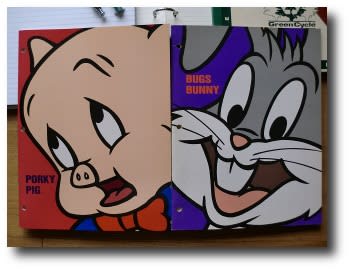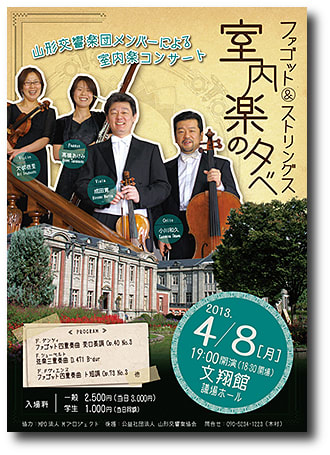葉室麟著『いのちなりけり』(文春文庫)の始まりは、きわめて映画的と言うか、ドラマティックです。水戸の徳川光圀が家老を誅殺し、家中が騒然とする中で、奥は森閑と静まり返っている。これを指図したのが、肥前小城藩の重臣・天源寺家の娘で才識と美貌で名高い咲弥だ、というのです。光圀は、咲弥に、その夫を呼び寄せるようにと命じます。咲弥の手には一通の書状が届いており、そこには
の歌が記されていたのでした
ここで、咲弥の夫である雨宮蔵人のことが紹介されます。鈍牛のような、と形容されるにふさわしい人となりで、およそ才媛の釣り合いには似つかわしくないのです。咲弥の前の夫が色白で美男で学識ある人だっただけに、咲弥もなぜ父親がこんな男を婿に選んだのか、よくわかりません。そんなわけで、咲弥は、自分の好きな歌は
だけれども、あなたの好きな歌は何かと問い質します。これは、再婚資格試験のようなものでしょうか。蔵人は目を伏せ、浅学にて好きな歌はと問われてもわからないと答えます。すると咲弥さんは「それなら寝所も一緒にしないでネ」と宣言します。なんともはや、よくわからない展開です。石頭の理系人間には、考えれば考えるほど、「なんでそうなるの?」と不思議でしかたがない。多分、ここを認めないと物語が成り立たないのだろうと無理に納得することにして、後を読み進めました(^o^)/
咲弥が幼い頃に迷子になったこと、桜の枝を持って帰ってきたこと、千鳥の透かし彫りの鍔を付けた刀を持っていた少年に、桜の枝を切ってもらったことなどを、ずいぶん後に鮮明に思い出すのに、それまでは全く記憶がなかったというのも、ヘンといえばヘン。
うーむ、ストーリーはなかなかおもしろく読ませる力があり、咲弥と蔵人の夫婦が再びめぐりあうまでの物語はけっこう感動的ではあるのですが、どうも基本的なプロットが、なんかヘン。よくわからないタイプの才媛と、鈍牛の陰にかくされたスーパーヒーローの物語は、おもしろく楽しみながらも、ストンと腑に落ちないものが残るようです。それはたぶん、作劇上の無理なのかも。
春ごとに 花のさかりはありなめど
あひ見むことは いのちなりけり
の歌が記されていたのでした
ここで、咲弥の夫である雨宮蔵人のことが紹介されます。鈍牛のような、と形容されるにふさわしい人となりで、およそ才媛の釣り合いには似つかわしくないのです。咲弥の前の夫が色白で美男で学識ある人だっただけに、咲弥もなぜ父親がこんな男を婿に選んだのか、よくわかりません。そんなわけで、咲弥は、自分の好きな歌は
願はくは 花の下にて春死なん
その如月の 望月のころ
だけれども、あなたの好きな歌は何かと問い質します。これは、再婚資格試験のようなものでしょうか。蔵人は目を伏せ、浅学にて好きな歌はと問われてもわからないと答えます。すると咲弥さんは「それなら寝所も一緒にしないでネ」と宣言します。なんともはや、よくわからない展開です。石頭の理系人間には、考えれば考えるほど、「なんでそうなるの?」と不思議でしかたがない。多分、ここを認めないと物語が成り立たないのだろうと無理に納得することにして、後を読み進めました(^o^)/
咲弥が幼い頃に迷子になったこと、桜の枝を持って帰ってきたこと、千鳥の透かし彫りの鍔を付けた刀を持っていた少年に、桜の枝を切ってもらったことなどを、ずいぶん後に鮮明に思い出すのに、それまでは全く記憶がなかったというのも、ヘンといえばヘン。
うーむ、ストーリーはなかなかおもしろく読ませる力があり、咲弥と蔵人の夫婦が再びめぐりあうまでの物語はけっこう感動的ではあるのですが、どうも基本的なプロットが、なんかヘン。よくわからないタイプの才媛と、鈍牛の陰にかくされたスーパーヒーローの物語は、おもしろく楽しみながらも、ストンと腑に落ちないものが残るようです。それはたぶん、作劇上の無理なのかも。